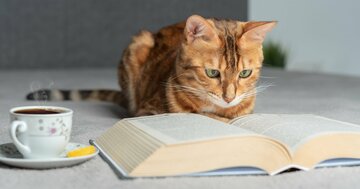ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
イヌとオオカミ
現在の知見によれば、地球に生物が誕生してから約四十億年の時間が経過しており、その膨大な時間を自然淘汰は使うことができた。一方、人間が品種改良に使う時間は数年から数十年、もっとも長くても数万年である。
現在のところ、いちばん古い家畜と考えられている動物はイヌである。確実にイヌだと分かる最古の化石は約三万三千年前のもので、ロシアのアルタイ地方で見つかっている。
これは化石中のDNAを解析して、イヌだと確認されたものだ。形態からイヌであろうと考えられているベルギーの化石はさらに三千年ほど遡るけれど、初期のイヌに関しては、形態だけから確実にイヌだと判定することは難しい。
ともあれ、品種改良の歴史はおそらく四万年を超えないので、約四十億年にわたって働き続けてきた自然淘汰とは比べるべくもない。
東アジアのハイイロオオカミ
ちなみに、ダーウィンは、イヌは複数の野生種を祖先に持つと考えていたようで、そのことを『種の起源』の第一章や第五章や第八章で繰り返し述べている。
しかし、現在のゲノム解析による知見によれば、イヌの起源が一つであることは確実視されている。
イヌの祖先はハイイロオオカミで、その中でもおそらく東アジアにいたものを祖先に持つ可能性が高い(ただし、イヌの家畜化は複数回起きたかもしれない)。
とはいえ、ダーウィンはゲノムデータなど使うことはできなかったので、これは仕方のないことだ。
それはともかく、『種の起源』でもっとも重要な主張である「生物を変化させる強力な力である自然淘汰が、自然界で実際に働いていること」を、ダーウィンはここで論証しているのである。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。