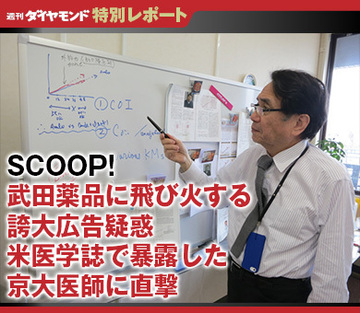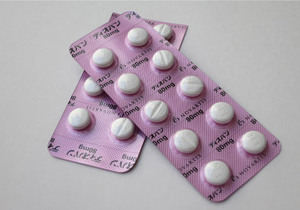創業家・OBから上がった
反乱の狼煙
「第138回定時株主総会の事前質問状」。4月24日、6ページにわたる質問状が国内製薬最大手である武田薬品工業に提出された。6月27日に大阪で開催される定時株主総会に向けたものだ。
質問権を行使するのは112人。その大半は武田OBだ。加えて武田の創業家一族が10人以上、名を連ねる。海外企業のM&Aと外国人幹部の登用で急速なグローバル化を推し進める現経営に対し、一部の創業家一族、そしてOBが反乱の狼煙を上げた。
質問状の内容は次の7項目。経営の問題を追及する内容のオンパレードだ。
①米バイオ企業ミレニアム・ファーマシューティカルズ買収の失敗に対する責任の所在
②スイスの製薬会社ナイコメッド買収の失敗に対する責任の所在
③グローバル化の在り方、および国内技術者のモチベーションが低下する経営への疑問
④長谷川閑史社長の後任に外国人であるクリストフ・ウェバー氏を選んだことへの疑問
⑤外国人が多くを占める経営幹部会議を重視して取締役会を形骸化していることへの疑問
⑥高配当金継続により財務が悪化することへの懸念
⑦糖尿病薬「アクトス」に関して、米連邦地方裁判所が武田に60億ドルの賠償を命じた陪審評決への対処と責任の所在
武田はなぜ、身内から反乱が起きるような事態に陥ったのか。
武田の業績のピークは2006年度だった。けん引したのは「4打席連続ホームラン」とも表現される大型4製品。これら主力品は10年前後に世界最大市場である米国で特許が切れてしまった。
医薬品は特許が切れた途端に売り上げが急減する。他社が同じ有効成分で価格の安い競合品を投入し、シェアを一気に奪っていくからだ。4製品で売り上げの6割以上を稼いでいた武田の業績は急落。08年度には4製品合計で1兆円以上あった売上高が、特許が切れた13年度には4300億円まで半減した。
特許切れラッシュがやって来ることは事前に分かっていた。だから次の大型品の開発に力を注いできた。それと並行してM&Aも模索した。