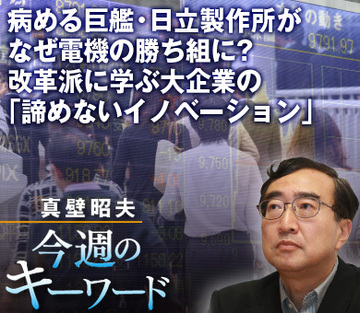日立の頑張りはよくわかったが
営業利益率はどこまで上げられるか?
「日立の頑張りはよくわかった。ただ、これで営業利益率はどこまで上げられるのか」
英語による鋭いコメントが、日立製作所の最高意思決定機関である取締役会の空気を一変させた。その声の主は、社外取締役のジョージ・バックリーだった。
この日は、日立社長、中西宏明(当時。現会長兼CEO)の肝いりプロジェクトの成果を取締役に向けて発表する晴れの舞台だった。それは、約950社ある日立グループで、全社横断で導入してきたコスト構造改革、スマート・トランスフォーメーション・プロジェクト(スマトラ)だ。
2011年後半から取り組んだ結果、まとまった改善成果が出てきたこともあり、取締役会でお披露目することになったのだ。
ところが、世界有数のコングロマリット企業である米3Mの前CEO、バックリーはスマトラ単独の成果よりも、それによる利益率の改善効果にこだわった。利益率2桁が当然のグローバル企業に対して、日立の5%前後という値は低過ぎるからだ。追い打ちをかけるように発言は続く。
「この方法では利益率2桁は達成できない。それよりも製品単価を上げるべきだ」
同じく社外取締役で、資源メジャーの英アングロ・アメリカン前CEO、シンシア・キャロルも同調。「値上げできないビジネスは整理すべき」という辛辣な意見に、取締役会は一時、紛糾した。
それでも、取締役会の活性化は日立が望んだ姿である。過半数を社外取締役とし、世界トップ企業のマネジメント経験者が持つ知見を反映させてきた。営業利益率20%以上をたたき出している3Mのバックリーの提言もまた、経験に基づいたものだった。
2桁をめぐる議論の中、取締役と執行役を兼任する唯一の人物としてその場にいた中西は、言葉を発せず、身じろぐこともできないでいた。「2桁利益率がグローバル企業の前提条件」と、かねて公言する中西にとって、2人の社外取締役の意見は、腹に落ちる話だったのではないか。