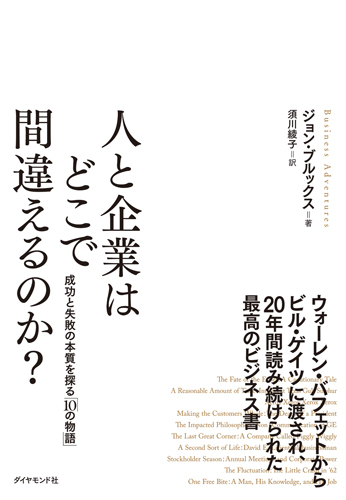2014年夏、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツは、自身のブログ「gatesnotes」で『Business Adventures』という1冊の本を紹介した。20年以上前にウォーレン・バフェットから推薦されたもので、以来「最高のビジネス書」として愛読し続けているという。世界で1、2を争う大富豪であり、伝説的なビジネスマンと投資家である2人がそろって絶賛する本ということで、世界的に大きな話題となった。
今回、その邦訳である『人と企業はどこで間違えるのか?』の出版にあわせ、ビル・ゲイツが「最も教訓的なストーリー」と評するエピソード、「ゼロックス、ゼロックス、ゼロックス、ゼロックス」を公開する。
本章の主な登場人物
マシュー・ディック・ジュニア:A・B・ディック・カンパニー、副社長
チェスター・カールソン:発明家、ゼログラフィの生みの親
オットー・コナーイ:物理学者、カールソンの助手
【ゼロックス社の関係者】
ジョセフ・ウィルソン:会長、創業者の孫
ソル・リノウィッツ::ウィルソンの右腕、弁護士
ジョン・デッサウアー博士:研究開発部門責任者、上級副社長
ハロルド・クラーク博士:ゼログラフィ開発の現場責任者
ホレス・ベッカー:ゼログラフィ開発の技術者
ピーター・マッカラー:CEO
アレン・ウォリス:ロチェスター大学学長
1887年、事務用書類のための最初の複写機となる謄写版印刷機[訳注 いわゆるガリ版]がシカゴのA・B・ディック・カンパニーから売り出されたが、すぐに市場に大旋風を起こすことはなかった。創業者のディック氏はもともと材木業を営んでいたが、価格表を手書きで写すのが面倒になり、自分で複写機を発明しようと思い立った。結局、謄写版印刷機を発明したトーマス・エジソンから製造販売権を取得して商品化することにしたのだが、いざとなるとマーケティング上の厄介な問題が立ちはだかった。
「そもそも書類を大量に複写したいとは誰も思わなかったんです」。ディック氏の孫のマシュー・ディック・ジュニアはそう説明する。彼は現在、さまざまなコピー機を扱うメーカーに成長したA・B・ディック・カンパニーの副社長を務めている。「発売当初は教会や学校、ボーイスカウトで使われるくらいで、一般企業には見向きもされませんでした。祖父たちは企業や専門職の人々に興味を持ってもらおうと必死で働きかけたそうです。ところが、機械で書類を複写するという発想はあまりに斬新すぎて、すんなりとは受け入れられませんでした。1887年といえばタイプライターが登場して10年ほどで、それさえまだ普及していませんでしたし、カーボン紙もめずらしかった時代です。ビジネスマンも弁護士も、書類の写しが5部必要なら事務員に5回写させていました─それも手書きで。祖父はよく言われたそうです。『いったいどうしてそんなに写しが必要なんだ。写しが増えれば事務所が手狭になるし、機密情報が漏れやすくなる恐れがある。貴重な紙をむだづかいすることにもなるぞ』、とね」
創業者のディック氏は社会的な壁にもぶつかった。それまで何世紀にもわたり、絵画を写すのは一般的に不道徳な行いとされてきた。そのため、英語の「写す(copy)」という言葉には好ましくない語感がつきまとっていた。オックスフォード英語辞典を見ると、この言葉には長らく虚偽を連想させるイメージがあったことがわかる。それどころか、16世紀後半からヴィクトリア時代にかけては、「写す」と「偽造する」はほとんど同義だった(中世には「写す」という名詞は「多量」や「豊富」といった肯定的な意味で用いられていたが、そういった意味は17世紀半ばまでに廃れ、この用法の名残は「豊富な(copious)」という形容詞に見られるばかりである)。17世紀のフランスのモラリスト、ラ・ロシュフコーは『箴言集』のなかで、「よい複製があるとすれば、悪しき原画の好ましからざる特性をさらけ出すものである」と記している。1857年には美術評論家のラスキンが、「絵画の複製を買ってはならない。それが人を欺くことになるからではなく、品位にもとる行為だからだ」と模倣行為を戒めている。
また、文書を写すことにもとかく疑いの眼差しが向けられてきた。「正確さが公証された記録の写しは有効な証拠になるが、写しの写しには正確さに疑義が生じるため、裁判では証拠として認められないだろう」。1690年、ジョン・ロックはそう記している。印刷業が誕生したこの時期、複写に対する揶揄を込めた表現として「下書き(foul copy=汚い写し)」という言葉が生まれた。また、ヴィクトリア時代には「二番煎じ(pale copy=薄ぼけた写し)」という表現が流行した。
20世紀になると、こうした見方は様変わりする。工業化の波によって複写の必要性が高まったことが主な要因だが、それにも増して、事務書類を複写する作業が急激に増えたのである(電話の普及と時期が重なっているのが意外に思われるかもしれないが、これは理にかなっている。コミュニケーションの手段が増えれば増えるほど、人はさらにコミュニケーションを活発にしたいと願うようになるのだ)。1890年ごろにはタイプライターとカーボン紙が普及し、20世紀に入ると謄写版印刷も事務作業に欠かせないものとなった。「エジソンの謄写版がなければ事務所とは言えない」――1903年にはディック社がそう豪語するまでになった。そのとき、同社が販売した謄写版はすでに15万台近くにのぼり、1910年には20万台を超え、1940年には50万台に迫った。1930年代から40年代になると、謄写版よりはるかに高品質を誇るオフセット印刷機が事務用機器として広く採用され、現在ではほとんどの大企業で使われている。
ところが、オフセット印刷機も謄写版と同じく、初めに特殊な原版を用意する必要があり、それをつくるのにかなりの費用と時間がかかるため、コスト面からオフセットが使われるのは印刷部数が多い場合に限られている。現在、事務機器業界では、オフセット印刷機と謄写版印刷機は「コピー機」ではなく「複写機」と呼ばれている。複写機は印刷枚数が多い場合に使われるのが一般的だ。
複写機とは対照的に、安価で速いコピー機の開発は遅々として進まなかった。原版を必要としない写真複写機(フォトコピー)が登場したのは1910年前後のことで、さまざまな製品が出たなかでもっとも有名だったのが(今でもそうだが)フォトスタットだ。しかし、どれもコストばかり高くて処理速度が遅く、操作も煩雑だったので、用途はおおむね建築や工学分野の設計図や法律文書に限られた。1950年より以前、業務用文書やタイプ原稿の写しを手軽に作成する機械といえば、カーボン紙をはさんだタイプライターだけだった。
ようやく1950年代に入って、事務用コピー機が登場しはじめた。原版がなくてもほとんどの書類を複製できる機器が短期間に相次いで発売されたのだ。しかも1枚につきたった数セントで、1分もかからずに複製できた。各社が用いた技術はさまざまだ。たとえば、1950年に登場したミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチャリング社(3M)のサーモファックスは感熱紙を使用し、アメリカン・フォトコピー社のダイアルアマティック・オートスタット(52年)は写真技術を応用した。イーストマン・コダック社のヴェリファックス(53年)には「転染」と呼ばれる手法が使われていた。いずれもディック社の謄写版とは異なり、あっというまに市場で受け入れられた。純粋に市場ニーズを満たしたということもあるが、あとから思えば、これらの機器がユーザー心理をくすぐったことも一因となっていたのは明らかだ。つまり、社会学者のいう「大衆社会」が、たった1つしかない特別なものを大衆化するというコピー機の概念に抗しがたい魅力を感じたのだ。
もっとも、初期のコピー機にはユーザーを苛立たせる深刻な欠陥があった。オートスタットとヴェリファックスは操作が難しく、湿った状態で紙が排出されるので乾かすのに時間がかかった。サーモファックスは熱が強すぎると印刷が黒ずんでしまう。また、いずれのコピー機も各メーカーが提供する特殊な加工紙を使う必要があった。コピー機を本当に愛される製品へと開花させるには画期的な新技術が不可欠であり、1950年代末、その新技術がついに登場した。つまり、ゼログラフィ(乾式複写法)という新たな原理が登場したのだ。普通紙で高品質が長持ちし、乾かす必要もなければ故障も少ない。反響はすぐに現れた。ゼログラフィ・コピー機が発売されたことで、アメリカ全体の年間コピー枚数は(複写機による印刷物は含まない)、50年代半ばには2000万枚だったのが1964年には5億枚、66年には140億枚と飛躍的に増えた――ヨーロッパ、アジア、ラテン・アメリカではさらに数十億枚がコピーされている。それだけでなく、印刷物に対する教育関係者の考え方や、書面による通信に対するビジネスマンの考え方も一変した。前衛的な哲学者たちはゼログラフィを自動車の発明に匹敵するほどの革命と賞賛し、雑貨店や美容院には硬貨投入式のコピー機が置かれるようになった。ゼログラフィの人気は最高潮に達した――短命に終わった17世紀のオランダのチューリップ熱とはちがい、人々の熱狂はどこまでも続きそうだった。
その偉大な技術革新を実現し、何十億枚ものコピーを生み出す装置を開発したのがゼロックス・コーポレーションだ。ニューヨーク州ロチェスターを拠点とするゼロックス社は、コピー機の成功によって1960年代にどんな企業よりも目覚ましい飛躍を遂げている。1959年、当時ハロイド・ゼロックス社という名前だった同社は、事務用自動ゼログラフィ・コピー機の第1号を発売すると3300万ドルの売上げを記録し、61年にはそれが6600万ドル、63年には1億7600万ドルと増え続け、66年には5億ドルを突破した。この成長率が数十年維持されたら(そんなことはありえないだろうが)、ゼロックスの売上げはアメリカの国民総生産を上回るだろうと最高経営責任者のジョセフ・ウィルソンが口にしたほどだ。
1961年にはフォーチュン500にゼロックスの名前はなかったが、64年には227位にランキングされ、67年には126位にまで順位を上げている。フォーチュン500の順位は年間売上高に基づいているが、ほかの指標で比べるとさらに順位が上がる。たとえば、66年の数字を見ると、フォーチュン500ランキングでは171位だったが、純利益では63位、売上高利益率では9位となる。株式時価総額では15位となり、USスティール、クライスラー、プロクター・アンド・ギャンブル、ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ(RCA)といった伝統ある大企業を追い抜いた。一般投資家はこぞってゼロックス株を購入し、同社の株は60年代の株式市場で金の卵を産むニワトリとなった。59年末に購入した株は、67年の初めには購入時のおよそ66倍の価値にまで跳ね上がり、ハロイド社時代の55年にいち早く購入していたが目端(めはし)が利く投資家は、元手が180倍に膨らむという驚異的な経験をすることになった。「ゼロックス長者」なるものが数百人規模で生まれ、そのほとんどがロチェスター周辺の住人か出身者だった。
ゼロックス社の前身は、1906年にロチェスターで創業したハロイド・カンパニーである。創業者の1人ジョセフ・ウィルソンは質屋を営み、ロチェスター市長を務めた経歴の持ち主だ――46年から社長としてゼロックスを率い、66年に会長に就任した同名のウィルソン氏は彼の孫にあたる。写真印画紙のメーカーだったハロイド社は、ロチェスターのほかの写真用品メーカーと同じく、イーストマン・コダック社の巨大な傘の下で生きながらえていたが、そんな日陰の存在でも、コダック社のおかげで大恐慌を比較的無難に乗り切ることができた。しかし、第2次世界大戦直後に競争が激しくなり、人件費が重荷になると、ハロイド社は新しい製品を開拓する必要に迫られた。そこで研究者が選択肢の1つとして注目したのが、オハイオ州コロンバスの非営利研究機関、バテル記念研究所において開発が進められていた複写技術だった。
ここで話の舞台を1938年のニューヨーク市に移そう。クイーンズ区のアストリア地区で、32歳の無名の発明家チェスター・カールソンが、酒場の2階の台所を実験室代わりにして研究に勤しんでいた。彼はスウェーデン系の理髪師の息子として生まれ、カリフォルニア工科大学で物理学の学士号を取得した。大学卒業後はインディアナポリスに本社を置く電気・電子部品メーカー、P・R・マロリー・アンド・カンパニーに入社し、ニューヨークの特許部門で働き始めた。だがそれだけでは飽き足らず、富と名声と自立を求め、余暇をすべてつぎ込んで事務用コピー機の開発に取り組んでいた。ドイツから亡命してきた物理学者のオットー・コナーイを助手に雇い、粗末な器具の山に囲まれ、煙と異臭を充満させながら研究に没頭した。そして38年10月22日、彼らの努力が実を結んだ。いささか地味なメッセージではあるが、ガラス板に書いた「1938年10月22日 アストリア」という日付と地名を紙に写すことに成功したのだ。
カールソンがエレクトロフォトグラフィ(電子写真術)と呼んだこの方法は、5つの基本的な工程から成り立っていた(基本原理は現在も変わらない)。まずは帯電性のある金属板を毛皮でこするなどしてマイナスの電荷を発生させる。次に原本に基づいて金属板を露光することにより、印刷したい部分がプラスの電荷に変化した鏡像をつくる。そこにマイナスの電荷を帯びた粒子をふりかける。金属板に紙を押しつけ、熱をあてて粒子を紙に固着させて写し取る。各工程はいずれもほかの技術分野で用いられているものだが、それを組み合わせたことが非常に斬新だった――実際、あまりにも斬新すぎて、業界の重鎮たちはその可能性をなかなか理解できなかった。カールソンは特許部門で得た知識を生かし、アイディアを守るために特許の網を張りめぐらし、さっそく売り込みを開始した(コナーイはまもなく別の仕事を見つけ、以後エレクトロフォトグラフィの仕事に関わることはなかった)。それから5年、彼は引き続きマロリー社で働きながら副業に打ち込んだ。国内の主要な事務機器メーカーを訪問し、そのプロセスを使用する権利をライセンスしようと奔走したが、ことごとく失敗に終わった。ようやく協力者を見出したのは、1944年のことだった。アイディアが製品化された際には販売やライセンスからもたらされる収入の4分の3を支払うという条件で、バテル記念研究所が開発費を負担してくれることになったのだ。
ここで話は戻り、いよいよゼログラフィの話に入ろう。1946年、バテル記念研究所で進められていた基礎研究は、ハロイド社から注目されるようになっていた。まもなく同社の社長を引き継ぐことになっていたジョセフ・ウィルソン(創業者の孫)は、親しくなってまもない友人ソル・リノウィッツに相談した。リノウィッツは公共心に燃える若く優秀な弁護士で、海軍での兵役から戻ってきたばかりだったが、保守的なガネット社[訳注 アメリカのメディア]への対抗勢力として、リベラルな見解を提供するラジオ局をロチェスターに立ち上げようとしていた。ハロイドには何人かの弁護士がいたが、ウィルソンはリノウィッツを気に入り、バテル記念研究所の調査を「単発」の仕事として依頼した。リノウィッツは「コロンバスの研究所に行って、猫の毛皮で金属板をこすっているところを視察した」と振り返っている。その後も何度か研究所を訪れて交渉を重ね、ハロイド社はカールソンが考案した技術を使用する権利を獲得した。カールソンとバテル記念研究所にロイヤルティを支払い、ハロイドとバテル記念研究所が開発費用を分担する条件だった。
この合意によってすべて滞りなく動き出したように見えた。1948年、バテルの研究員はオハイオ州立大学の古典語の教授の意見を聞きながら、古典ギリシャ語の2つの単語を組み合わせて「乾いた書きもの」を意味する「ゼログラフィ」という新しい名称を考え出した。ところが、技術改良を進めていたバテル記念研究所とハロイド社のささやかな科学者チームは、予想外の不可解な技術的問題に次々と遭遇していた。ハロイド社はすっかり自信を挫かれ、ゼログラフィの権利の大部分をインターナショナル・ビジネス・マシーンズ社(IBM)に売り渡そうとしたが、結局この交渉は成立しなかった。研究は継続していたものの費用がかさむ1方で、ゼログラフィはハロイド社にとって、しだいに生きるか死ぬかの賭けになっていった。55年、新たな合意が交わされた。ハロイド社はカールソンの特許をすべて譲り受け、研究開発費を全額負担することにした。ハロイド社は特許権の対価としてバテル記念研究所に対して新規株式を割り当て、その一部がカールソンに付与された。
開発費は莫大なものになった。1947年から60年にかけて、ハロイド社がゼログラフィの研究に投じた資金は約7500万ドルにのぼる。これは、同期間の営業利益のじつに2倍の額だ。会社は帳尻を合わせるため借り入れを増やし、普通株式を大量に発行し、よほど親切か無謀か、あるいは先見の明のある投資家に頼るしかなかった。なかでも、ロチェスター大学は苦戦している地元の産業を支援する方針から、寄付基金を使って大量の株を購入した。のちの株式分割を加味すると、1株あたりの取得価格は50セントになる。大学の職員が「数年後に株価が下落したら、損失を抑えるため株を売却せざるをえませんが、そうなっても気を悪くしないでくださいね」と不安げに言うと、ウィルソンはうなずいた。この時期、ウィルソンをはじめとする役員の報酬はほとんどが株で支払われ、なかには貯蓄を切り崩したり、自宅を抵当に入れたりして研究を支える役員もいた(このころ誰よりも貢献したのはリノウィッツだ。彼の仕事は単発では終わらなかった。やがてウィルソンの右腕となり、重要な特許関連の交渉や外国企業との提携を担当し、最終的に取締役会議長を務めるまでになった)。
1958年、ゼログラフィの技術を使った製品はいまだ商品化に至っていなかったが、ハロイド社は祈るような思いで社名をハロイド・ゼロックスに変更した。「ゼロックス(XeroX)」という商標は数年前にすでに取得していた――ウィルソンも認めているとおり、これは恥も外聞もなくイーストマンの「コダック(Kodak)」を真似たものだ。もともと最後のXは大文字だったが、誰も大文字で書いてくれないのでやがて小文字に格下げになった。だが少なくとも、コダックと同じように、前から読んでも後ろから読んでもよく似ているという面白さは残った。小文字か大文字かという問題はさておき、ウィルソンによると、ゼロックスという名称は大勢のコンサルタントから大反対され、それを押し切っての決定だったそうだ。そもそも読み方がわからないし、薬物の名前のような響きがあるというのが理由だった。あるいは、経済的にマイナスのイメージ、つまり「ゼロ」を連想させるという意見もあった。
ところが、1960年に状況は一気に好転した。そんな商品名で成功するだろうかという懸念は吹き飛び、関係者はむしろ成功しすぎることを心配するようになった。世の中では「ゼロックスする」という新たな動詞がやたらと使われるようになり、商標価値の希釈化を防ぐため、第三者によるゼロックス商標の使用を監視しなければならないほど製品が普及したからだ(61年、同社は「ハロイド」を削除して「ゼロックス・コーポレーション」と社名を変更した)。また、それまで自分や家族の将来を案じていた幹部たちは、親戚や友人から恨みがましい言葉を浴びせられるのではないかとひやひやするようになった。株価が1株20セントだったころ、彼らは相手のためを思って株を購入すべきではないと助言していたからだ。ところが、ゼロックスの大口株主はみるみる金持ちになっていった――生活を切り詰め、苦労を耐えしのいだ幹部たちやロチェスター大学、バテル記念研究所などに莫大な富が転がり込んだ。なかでも、チェスター・カールソンが保有していたゼロックス株は、68年には数百万ドルの価値を持つようになり、カールソンは(『フォーチュン』誌によると)アメリカで66番目の資産家になった。
こうして概観すると、ゼロックスの物語には19世紀的とも言える古めかしい雰囲気が感じられる――粗末な実験室でこつこつと研究に勤しむ発明家、家族経営の小さな会社、開発初期段階でのつまずき、1つのアイディアに賭けた事業モデル、古典ギリシャ語に由来する商品名、自由競争の正当性を証明する最終的な勝利。だが、それだけではゼロックスの全体像を理解したことにはならない。ゼロックスは株主、従業員、顧客に対してだけでなく、社会全体への責任を果たしたという意味で、19世紀の多くの企業とは対極にある――それどころか、20世紀の企業の先陣を切ったといっても過言ではない。「不可能と思うほど困難な目標に向かって、必ず達成できると周囲を鼓舞すること――これらはバランス・シートと同じくらい、いやそれ以上に重要だろう」とウィルソンは語っている。また、ほかの幹部たちも折に触れ、「ゼロックスの精神」とは目的を達成するための手段ではなく、「人間の価値」そのものに重きを置くことであると力説してきた。
もちろん、こうした社是は大企業では少しもめずらしくないし、それがゼロックスの幹部の口から出たとなれば懐疑的な見方をされてもおかしくはない――同社の莫大な利益を思えば、苛立ちさえ覚える人々もいるだろう。しかし、ただの美辞麗句ではないことを示す証拠がある。ゼロックス社が教育機関や慈善団体に寄付した金額は、1965年には163万2548ドル、66年には224万6000ドルにのぼる。どちらの年も、もっとも額が大きかったのはロチェスター大学とロチェスター共同募金基金への寄付で、両年とも寄付金の総額は同社の税引き前利益の約1.5パーセントに相当する。大企業が慈善活動に支出する金額としては異例の大きさだ。多額の寄付をすることで知られる企業の例を挙げれば、65年のRCAによる寄付総額は税引き前利益の約0.7パーセント、アメリカ電話電信会社(AT&T)も1パーセントには届かない。ゼロックスが気高い理想を追求していることは、66年に「1パーセント事業」に参加していることからもうかがえる。これは「クリーブランド・プラン」とも呼ばれ、クリーブランドの企業が利益の1パーセントを、通常の寄付とは別に地元の教育機関に寄付する取り組みだ――したがって、ゼロックスの利益が増加し続ければ、ロチェスター大学とその姉妹機関の将来は安泰である。
ゼロックスはこれ以外にも、利益には直結しない分野で果敢にリスクをとっている。ウィルソンは1964年のスピーチで次のように述べた。「企業は社会の重要な問題について、立場を表明することから逃げてはならない」。これはビジネスの世界では異端とみなされる発想だ。社会問題について立場を明らかにするということは、反対の立場をとる顧客を遠ざけることになるからだ。ゼロックスが明らかにしている社会的立場としてとくに目立つのは、国連への支持だろう――それは暗に、国連を中傷する人々に異議を唱えることにほかならない。64年の初め、ゼロックスは年間広告費に相当する400万ドルを費やし、国連に関するテレビ番組のスポンサーになった。このシリーズ番組にゼロックスのCMやその他の広告的な内容が盛り込まれることはなく、番組の最初と最後に「提供はゼロックス」とアナウンスが入るだけだった。
スポンサーに名乗りを上げてから3ヵ月ほどたった7月から8月にかけて、ゼロックスに番組から手を引くように迫る抗議の手紙が急に殺到するようになった。手紙は1万5000通にもなり、その口調は穏やかに理屈を説くものから感情的に辛辣な非難を書き連ねたものまでさまざまだった。内容としては、国連はアメリカ人から憲法で認められた権利を奪う道具であり、国連憲章の一部はアメリカの共産主義者によって起草され、それが共産主義の推進に利用されている、と主張するものが多かった。また、そう多くはないが、番組を中止しなければゼロックス製品をオフィスから撤去するという経営者たちからの脅しも見られた。そしてほんの数通、ジョン・バーチ協会[訳注 1958年に設立された極右反共団体]について触れているものがあった。どれも会員を名乗ってはいないが、状況証拠からして、山のような手紙はジョン・バーチ協会が周到に仕組んだものにちがいなかった。というのも、協会の最新の会報に、国連の番組に抗議する手紙をゼロックスに送るように呼びかける記事が掲載されていたからだ。そこには以前、手紙を大量に送りつけて、大手航空会社に飛行機から国連マークを除去させたエピソードも紹介されていた。また、ゼロックスによる分析の結果、1万5000通の手紙が約4000人の手によって書かれたことが判明し、抗議の背後にジョン・バーチ協会の力があることは明らかだった。
ゼロックスの上層部が屈することはなかった。1965年になると番組はABCテレビで放映され、多方面から賞賛の声が寄せられた。のちにウィルソンは、番組のおかげで――そして、抗議に屈しなかったことで――ゼロックスは敵より味方を増やすことができたと述べている。また、公の場でこの一件について語るときはいつも力を込めてこう訴える。気まぐれに理想を掲げたばかりに痛手を負ったという見方が多かったが、理想を貫くことこそがビジネスで成功するための最良の道である。
1966年秋、ゼロックス社はゼログラフィ・コピー機を発売してから初めて逆境に見舞われた。当時、事務用コピー機を販売する企業は40社以上あったが、多くはゼロックスからライセンスを受け、ゼログラフィ技術を使った製品を製造していた(ゼロックスは、普通紙印刷を可能にするセレン・ドラムという重要な技術については使用を認めなかった。そのため、ライバル製品はどれもまだ加工紙が必要だった)。しばらくのあいだ、ゼロックスには新分野の開拓者として高価格設定ができるという強みがあった。だが、『バロンズ』誌が8月に指摘した言葉を借りれば、「かつては目覚ましい新発明だったこの製品も――あらゆる技術革新の宿命として――ありふれた存在になる日が近づいている」ように見えた。後発企業は低価格を売りにしてこぞってコピー機を発売した。ある企業は5月に送付した株主宛の手紙のなかで、コピー機はいずれ「おもちゃ」のように1台10ドルか20ドルで販売されるだろうと予測した(実際、68年には30ドルのコピー機が登場した)。また、かみそりが替え刃に主役の座を奪われて久しいように、コピー機も紙を売りさばくための手段に成り下がるだろうという声まで聞かれるようになった。
ゼロックスは心地よい独占状態は一時的なものだと自覚していたので、数年前から出版業界や教育業界など、異業種の企業を傘下に収めることで事業拡大を図ってきた。1例を挙げると、1962年には、未発表原稿や絶版本、博士論文、定期刊行物、新聞のマイクロフィルムなどを保管するユニバーシティ・オブ・マイクロフィルムズを買収している。また、65年には、小中学生向けの教育雑誌を発行する出版社として国内最大手のアメリカン・エデュケーション・パブリケーションズと、教育機器メーカーのベーシック・システムズを買収した。
しかし、これだけでは市場に安心感を与えることはできず、ゼロックスの株価は下落した。66年6月末に267と3/4ドルだった株価は10月初めには131と5/8ドルに落ち込み、ゼロックス社の市場価値は半分以下になった。10月3日から7日にかけての週は、たった5日間で42と1/2ドルの下落を記録した。とくに、6日にはかなり危機的な状況に陥った。およそ2500万ドル相当の株式の売り注文に対して買い手がつかず、ゼロックス株はニューヨーク証券取引所において5時間にわたって取引が中断したのだ。