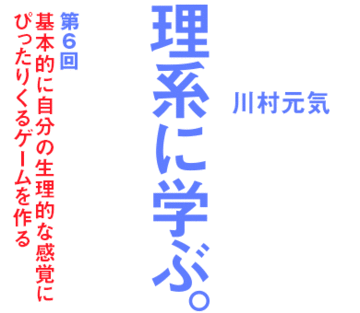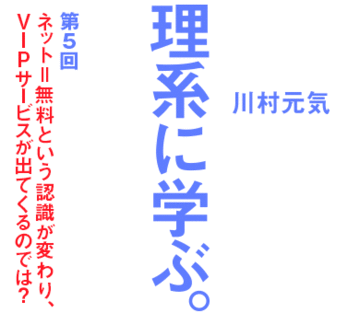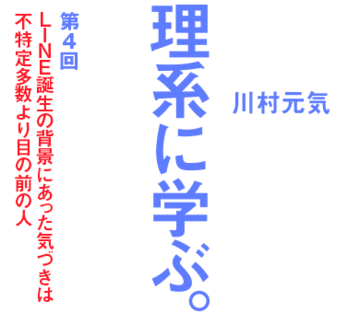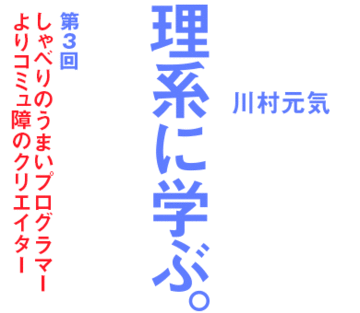『告白』『悪人』『モテキ』『バケモノの子』『バクマン。』などを手がけた映画プロデューサーで、初めて書いた小説『世界から猫が消えたなら』が120万部を突破し映画化。2016年も映画『怒り』『何者』など、次々と繰り出される企画が話題を集める川村元気。その背景にあるのは「“苦手を学ぶ”ことで、人間はぎりぎり成長できる」という一貫した姿勢だという。
そんな川村元気が、話題の新刊『理系に学ぶ。』では、「文系はこれから何をしたらいいのか?」をテーマに最先端の理系人15人と、サイエンスとテクノロジーがもたらす世界の変化と未来を語っている。
本連載ではその中から5人との対談をピックアップするが、第7回は、数々の傑作で世界を熱狂させてきたゲームプロデューサーの宮本 茂さんとの対談後半。
『スーパーマリオ』の背景を空色にした理由は?
川村 宮本さんに会ったら聞きたいと思っていたんですけど、それこそ『インベーダーゲーム』とか『ドンキーコング』とか、背景がずっと黒じゃないですか。なのに、『スーパーマリオ』のときにいきなり空色が入ってきたのは、どうしてなのかなと。
宮本 当時、使える色が60色くらいあって、そこに空色が入っているのはわかっていました。ただ、昔の解像度で背景に青をもってくるとキャラクターがぼけるから、ものすごくこだわって描いている絵でもあるし背景は黒でしっかり締めたかったのと、ゲームをして目が悪くなったと言われるのもいやで、ずっと拒んでいたんです。でも、『スーパーマリオ』はファミリーコンピュータにディスクシステムをくっつける前の、本体だけで動く最後のゲームとして出そうとしていて、「ある意味でお祭りでもあるし、派手にいきましょうか」ってことで、空色になりました。
川村 今までのゲームでは背景が黒だったのが、空色という比較対象ができたことで暗闇になったというか、「色を変えただけなのに、なんだろうこの感じ」っていう当時の驚きは、今でも覚えています。
宮本 僕も空色の世界から暗闇にした土管にスーパーマリオがぽとっと落ちたときに、急に寒さみたいなものを感じてぞくぞくっとしたのを覚えています。それで「この感じをもっと生かさないともったいない」ってことで演出が高じたのが『ゼルダの伝説』で、音で何か足せないかとか、いろいろやってみたりしましたね。
川村 確かに、ゼルダのジングルを初めて聴いたときは、震えましたね。
宮本 それまではファミコンのボードに直打ちで打って出る音しか使えなかったのが、ゼルダの頃はサンプリングに近いこともできるようになったので、そのへんの音をかなり使っていて、近藤浩治という任天堂のサウンドディレクターとべったりやりましたね。効果音は、作ってもらったサンプリングを一通り聴いて、「このシーンにはこの音」みたいなことをやったりして、すごく楽しかったです。音楽というのは素晴らしくて、それだけで人の気持ちを作ることができるんですよね。
川村 『告白』という映画を一緒に作った中島哲也監督も「人の感情を動かすのは、映像よりも音」とよく言っていました。
宮本 ただ、ゲームの音の付け方はちょっと特殊で、レースゲームでも「ブーン」というアクセルのリアルな音より、異質な音が入った方がいいんです。あり得ない音をどう奔放に混ぜるかっていう部分が、ゲームではけっこう楽しい。
川村 宮本さんがすごいのは理系に踏み込んだ上で技術の発明だけでなく、そこに文系のジャンルでもある色や音へのアート的なこだわりを加えたことだと思います。
宮本 あと、ネーミングもかなりやりましたね。
川村 そこはどんなセオリーを持たれていますか?
宮本 「まぁ、悪くないんじゃないですか」というのはほとんどだめで、最初は反対意見が多いものの方が実際に売れたりするものだと思います。普通じゃないというのが大事なんじゃないですかね。