「ハードウエア+コンテンツサービスのプラットフォーム」は、ソニーが1990年代後半から模索し続けたビジネスモデルだった。なぜ、アップルに先を越されてしまったのか。
iPhoneの斬新な日本語入力ユーザーインターフェース(UI)は、ある日本人エンジニアによって実現した。富士通、シャープ、ソニー、産業総合研究所を渡り歩き、2006年にアップルに引き抜かれた増井俊之氏である。
ソニー時代には、ソニーコンピュータサイエンス研究所(CSL)に所属、PDAや携帯電話向けに、学習機能を持つ予測変換ソフト「POBox」を開発したことで知られている。タッチパネルを初めて採用した携帯音楽プレーヤーの「iPod Touch」以降、アップルのUI開発に欠かせない存在となっている。
CSLは、かねて斬新なUI開発に力を注いできた。だが、「マウスやキーボードなどの操作性向上が中心命題であり、POBoxのようなソフトウエアがソニー製品に採用され、日の目を見たケースは多いとは言いがたい」(元CSL研究員)。対するアップルには、パソコン(PC)で築いた「マッキントッシュ」ソフトウエア資産がある。しかも、iPodでは、従来の凹凸のボタンに代わって、平面のクリックホールに指を滑らせて操作する斬新なUIが、市場に認知されることを実証した。このソニーとアップルの彼我の差――。それは、「UIに対する経営者の感度の違い」と、先の元研究員は付け加えた。
「プレーヤー+配信」で
先頭を走っていたソニー
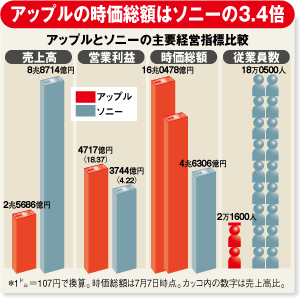 iPhoneの誕生に地団太を踏んだのは、ほかならぬソニーだろう。
iPhoneの誕生に地団太を踏んだのは、ほかならぬソニーだろう。
アップルが「iPod+iTunes」で確立した携帯音楽プレーヤー+ダウンロードサービスのビジネスモデルは、1990年代後半の出井伸之社長時代に、「ウォークマン」とソニー・ミュージックエンタテインメントを中心とする主要レーベルを巻き込み実現しようとしていた、まさに成長戦略そのものだった。
しかもソニーは、契約権の管理や金融決済を行なうデジタルライツマネジメント(DRM)やデータの圧縮・伸長技術のソフトウエアを独自に開発し、コンテンツサービスのプラットフォームとすべく、デファクトスタンダードを狙った。この新しいビジネスモデルにかかわる戦略組織には、2002年当時、3000人近い精鋭たちが集まっていた。創業以来脈々と続くパイオニア精神が、そこには確かにあった。







