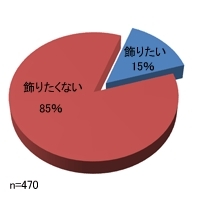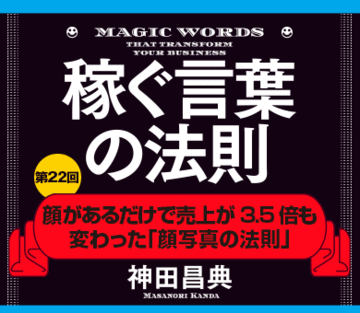先日、中国の通信機器メーカーHuawei(ファーウェイ)に関するニュース(出典:iPhoneMania)が報じられた。なんでも、同社のスマートフォン「P9」のカメラで撮影したと言ってGoogle+に投稿した超美麗な写真が、実はトータル45万円の一眼レフカメラで撮影したものだったというのだ(お粗末にも、画像のメタデータにカメラとレンズの情報が残っていたという)。
アップルの「iPhoneで撮影」キャンペーンのように、スマートフォンのカメラの性能を専門用語(◯◯メガピクセル)やブランド名で表現するのではなく、ユーザー目線で一番わかりやすい「写真のよさ」を語って共感を得る「つもり」だったのだろう。「ウソ」をついてしまった(少なくともユーザーからはそう見える)Huaweiの戦略は不用意すぎるが、そもそもなぜ、「質」をアピールするのに、ユーザーの写真が効くようになったのだろうか。
『ウソはバレる』から、一昔前のある「極端な事例」を引用しつつ、その謎を解いてみたい。
コダックのお粗末な新製品と、
「◯◯製だから安心」時代の終わり
かつてブランドがあれほど絶大な力を持っていた主な理由は、ブランドが質のシグナルになっていたからだ。高品質で知られる製品ラインが1つでもあれば、企業は容易にそのブランドを利用して新製品を発売したり、製品ラインを拡張したりできた。強力なブランドは平凡な製品の救世主になることもあった──少なくとも当面のあいだは。
こんな例がある。1980年代初頭、エマニュエルはイスラエルでコダック担当のコピーライターとして働いていた(編集部注:『ウソはバレる』の著者の1人でクチコミの提唱者)。ある朝、現地の販売業者が緊急会議を開いた。その数週間前、ニューヨーク州ロチェスターにあるイーストマン・コダック本社から、密封された荷物が届いていた。指定の日が来るまで絶対に開封してはいけない、という指示だった。
指定の日がやってくると、彼らは荷物を開封した。入っていたのは薄型でスタイリッシュな新型カメラだった。販促資料によると、写真業界に革命を巻き起こすカメラだという。そこで、販売業者は極秘のもと、カメラを広告代理店の人々に披露しようとしていた。その名も「コダック・ディスク」。カメラには従来のロール・フィルムの代わりに、15枚撮りの平らなディスクが装填されていた。驚くほど使いやすかった。撮るたびにフィルムを送る必要もない。ディスクが自動で回転するからだ。
広告業界の人間は興奮しやすい質たちだが、そのときも例外ではなかった。人々のため息が部屋じゅうを満たす。おしゃれなカメラだった。しかし、カメラに熱中するあまり、誰も肝心の写真の質には注目しなかった。問題なく写ってはいたが、少し粗かった。
その会議から少しして、カメラは世界じゅうで、鳴り物入りで発売された。使いやすい……撮影ミスが少ない……楽しい……おまけにコダック・ブランドだから安心……。広告にはそんな言葉が並んだ。結果は?売上は好調だった(イスラエルでもほかの国々でも)。1年目、コダックは全世界で800万台以上のディスク・カメラを出荷した。競合企業が市場に続々と参入し、前途洋々に見えた。
ところが数年後、製品は販売中止になった。ネックは例の粗い画質だった。結局のところ、ほとんどの消費者にとっては許容範囲を下回っていたのだ。コダック・ブランドは高品質をウリにしていたので、人々はそれを信じてカメラを購入した。しかし、コダックというブランドの役目はそこまでだった。やがて、多くの人が友人から粗い画質について聞きつけたり、家族写真を見せられたときに気づいたりしたのだ。
今日の環境なら、このカメラはこれほど長く生き残るだろうか?どうだろう。サイトはユーザーのこんな製品レビューですぐにあふれかえるはずだ。
「カメラは最高、でも写真は最悪!」
「なんでこんなに粗いのか謎……」
ちなみに、粗い写真をすぐさま逆手に取ったのがデパートの販売員だった。相対戦術の名人である販売員たちは、35ミリ・カメラを売り込むため、コダック・ディスクと35ミリ・カメラで撮影した写真をカウンターに並べた。「35ミリ・カメラの高品質な写真を買い物客に見せると、たいていは少し奮発して35ミリ・カメラのほうを買ってくれるんですよ」とある販売員は説明した。(『ウソはバレる』97-99ページより)
30年前の、それもコダックというすでに退場してしまった企業の話だといってバカにすることはできまい。それは、アップルが、カメラの「質」を語るのに、「ユーザーの写真」を使いはじめたことからもわかるだろう。アップルやiPhoneであろうと、もはやそのブランド名だけでは、ユーザーを興奮させることはできなくなってきているのだ。iPhoneの質が高く、「本物」であることを示すために、わざわざユーザーの声を借りなければならなかった、とも言えるかもしれない。
「質」はユーザーに語らせろ――この戦略が、もし現代の有効手だとしても、そこには1つ大きな前提がある。それは、「本物」しか生き残れない、ということ。安易にトレンドに乗っかろうとして、製品やサービスの本当の価値より少しでも「盛って」しまうと、Huaweiのようにすぐにバレてしまう。結局は「質」を高めて、それに見合ったコミュニケーションができる企業だけが、ユーザーの共感を得られるのだ。(構成:編集部 廣畑達也)