
市兵衛の死後、養子の古河潤吉(陸奥宗光の次子)が2代目当主となるも、2年後に潤吉が急逝し、1905年に市兵衛の実子である古河虎之助が3代目当主となる。虎之助の代から、古河鉱業は鉱業から工業への多角経営に移った。とりわけ、14年に勃発した第1次世界大戦による軍事特需で、事業規模を急速に広げた。ところが、20年からの戦後の反動恐慌と、大豆への投機で大損失を被ったのを機に古河商事が閉鎖され、その後古河銀行も第一銀行(現みずほフィナンシャルグループ、創設者は渋沢栄一)に吸収された。
こうした危機の中、古河財閥は加工業部門を柱にグループ事業の再構築を開始するのだが、そのリーダーとなったのが中川末吉(1874年11月6日~1959年4月9日)だった。中川の妻は市兵衛の養女だったが、中川は創業者の親戚という立場を特に表に出すことなく、財閥の当主を支える事業運営の総大将として活躍した。
米国留学経験を生かし、海外企業との合弁を進める。横浜電線製造(現古河電気工業)内にあったゴム事業を、米グッドリッチと合弁で横浜ゴムに発展させたり、独シーメンスと古河鉱業の合弁による富士電機製造の設立にも携わった。ちなみに富士電機のフジは、古河のフと、ドイツ語読みのジーメンスのジを組み合わせた社名である。富士電機はさらに通信機事業に進出し、富士通信機製造(現富士通)を生んだ。「銅山王」と称された創業者の向こうを張って、“白い銅”と呼ばれるアルミニウムの製造に乗り出し、日本軽金属を創業したのも中川だった。
1954年10月5日号の「ダイヤモンド」で、中川はダイヤモンド社創業者の石山賢吉と対談し、こうした事業創造の裏話や、市兵衛翁の昔話を語り合っている。市兵衛が説いた成功の3条件に「運・鈍・根」(運が良いこと、粘り強いこと、根気があること)という言葉があるが、対談の冒頭から中川が持ち出したのが「運」の話。近江(滋賀県)の庄屋の五男として生まれ、村役場の雑用係をしていた中川が、養子に出された先で足尾銅山の仕事に関わったのが縁で、古河の本店で働くことになり、市兵衛の目に留まり留学までさせてもらう。絵に描いたような立身出世譚を本人自ら披露している。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
古河生活65年
運のいい人間だった
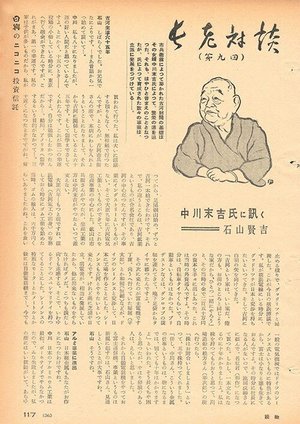 1954年10月5日号より
1954年10月5日号より
――しばらくでした。お元気で何よりです。まあ昔話から一つ始めていただいて。
私も80になりましたが、運のいい人間だと思っているんですよ。とにかく、15のとき、役場の小僧をしている時分に、東京へ行く機会ができたんですが、これがまあ、第一の幸運です。私の家は子どもが多いものだから、私がもらわれていった。
私は大いに活躍するつもりもなく、無神経で行ったんですが、ところが、古河市兵衛さんのところで、本店にわしを入れようということになりまして、それから古河に関係していること65年です。
そして留学までさせてくれたんです。これが第二の幸運ですよ。自分は勉強したかったんだから。結局、米国へ留学するという目的がかなって……。30近くになったときですがね。
帰ってから、足尾銅山はじめ、ずっと古河一本やりできたわけです。それで、私の違うところは、古河鉱業というものが合名会社であり、古河の中心だったんですが、その事業にインダストリーというものがない。そこで大正9年に古河電気工業というものができて、これを生産事業の中心にした。鉱山は市兵衛さんがやったが、生産工業の方は中川末吉がやったといって差し支えない。









