深澤 献
いま私たちが当たり前だと思っている日本の企業の姿や、働き方、組織の常識は、最初にそれを形作った設計者や実装者がいる。今回は、日本的経営の基礎となった「家族主義」を創ったカネボウの社長、武藤山治に焦点を当てる。武藤が掲げた「家族主義」「温情主義」とは、単なる“優しさ”ではなく、徹頭徹尾、リアリズムに基づくものだった。
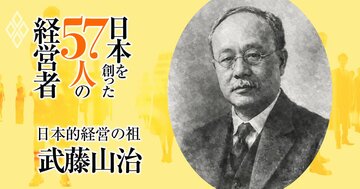
「週刊ダイヤモンド」1967年10月1日臨時増刊号に掲載された、「サラリーマンの実力時代来たる」と題された座談会。東京電力、日本通運、富士製鉄といった重厚長大産業の経営陣と、流通革命の旗手だった西武百貨店の堤清二の4人が、「実力主義」をどう日本企業に根付かせるかを率直に語り合っている。

ノリタケ、TOTO、日本ガイシ、日本特殊陶業などを擁するセラミックス企業集団、森村グループを創業した6代目森村市左衛門。その次男に当たる森村組(現・森村商事)社長の7代目森村市左衛門が、創業ストーリーについて語っている。
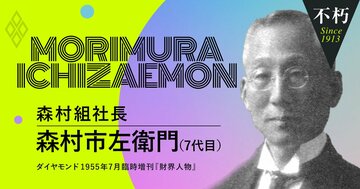
敗戦という未曾有の国難において、日本史上唯一の「皇族出身の首相」として政権を担った東久邇宮稔彦の極めて貴重な証言である。
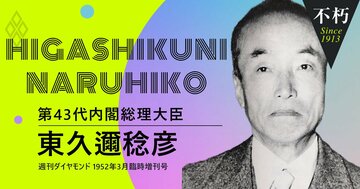
昭和の幕開け、焼け跡からの再出発、高度成長を経た成熟社会の入り口――。企業は生まれた時代の空気を色濃く映す存在だ。2026年に創業100年、80年、50年という節目を迎える上場企業を抽出した(原則として法人登記年。事業開始年など、当該企業が掲げる年と異なる場合がある)。

雇用における性別による差別を禁止する「男女雇用機会均等法」。1986年の施行から2026年は40年になる。40年前の時代の“空気”はどんなものだったのか、当時の「週刊ダイヤモンド」誌面から振り返る。
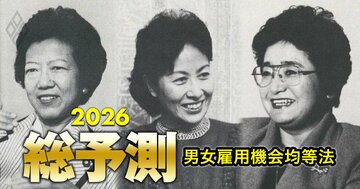
2026年の干支は「丙午(ひのえうま)」。江戸時代から、丙午生まれの女性を差別する迷信があり、この年に女児を産むのを避ける傾向があった。おかげで明治も昭和も、この年だけ人口が極端に少ない。360年にわたる丙午の迷信の実態と、60年ぶりに訪れる令和の丙午の行方を占う。

1980年代の情報通信業界を象徴する用語に、VAN(Value Added Network)とEDI(Electronic Data Interchange)がある。「週刊ダイヤモンド」85年4月6日号で、NECの関本忠弘社長が大規模VAN事業への強い意欲を語り、「日本電気は大規模VANで一番上手になれる」と自信を示している。
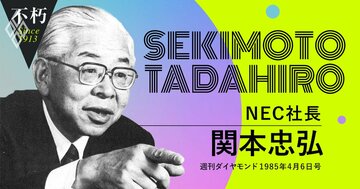
上智大学教授の渡部昇一が「週刊ダイヤモンド」1980年1月1日号に「歴史的楽観主義のすすめ」と題した論考を寄せている。80年代に入った新年最初の号ということで、未来予測的な側面もあり、興味深い内容だ。あえて“答え合わせ”をしてみよう。

#15
「大事は軽く、小事は重く」…“ヤマ師” 山下太郎が火災、資金難、世論の逆風下で見せた胆力【アラビア石油を創った男】
ペルシャ湾沖の掘削現場で大規模火災が発生する。「日の丸原油、炎上!」と世間が騒然とする中、太郎は逆境を前向きに捉え、努めて明るく振る舞った。追加出資や銀行融資を求めて奔走する太郎の姿勢は、単なる強がりではなく未来への確信と責任感の表れだった。

#14
“ヤマ師”太郎に見る戦後日本の情熱の原点…現代の経営者たちも持ち得る「共通の軸」とは?【アラビア石油を創った男】
太郎は、戦中の苦難を知る技術者・山内肇と共に石油開発に挑み、失われた命への責任感を胸に未来を切り拓いた。その戦争の記憶に基づく情熱は、日本の高度経済成長を支えた世代に共通するものだろう。現代においても経営者や起業家の原動力とは、「次世代のために何を残すか」という使命感であるべきではないか。

「ダイヤモンド」1935年4月11日号に掲載された郷誠之助の「人物雑談」と題されたインタビュー。当時の政治家や財界人について生々しく語っている。遠慮して言葉を選ぶことなく、驚くほど率直に語られていて、当時の空気感や上下関係、財界人の性格が手触り感をもって伝わってくる。
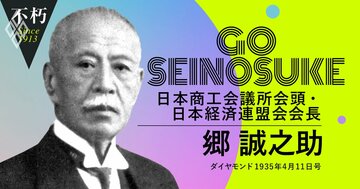
#13
「ラクダの絵葉書」が日本を動かした!“ヤマ師”太郎が灼熱の中東から届けた誠意と本気【アラビア石油を創った男】
アラビアでの石油開発計画を「無謀」と大蔵大臣から公然と批判され、状況が不利に傾く中、太郎は現地から日本の支援者に直筆の絵葉書を送り続け、情熱と誠意を伝えることで周囲の心を動かしていく。その姿は、リーダーの本気こそが人を動かす原動力であることを証明した。

セガ・エンタープライゼス社長の中山隼雄は、1980年代後半から90年代にかけてのゲーム業界の成長期にセガを急拡大させた「中興の祖」だ。飛ぶ鳥を落とす勢いにあった93年の「週刊ダイヤモンド」に掲載された中山のインタビューを紹介する。
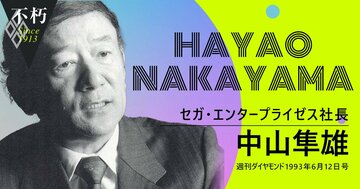
#12
日本とサウジの未来を懸けた石油交渉の美学、“ヤマ師”太郎の譲歩と視座【アラビア石油を創った男】
日本のエネルギー自立を懸けたサウジアラビアとの石油利権交渉で、太郎率いる交渉団は厳しい条件を突きつけられる。重い負担を受け入れつつも、太郎は「日本法人であること」だけは譲らず、未来を見据えた大局的な視点で交渉を主導。目先の利益にとらわれず、国家の自立と新たな国際関係構築を目指した。
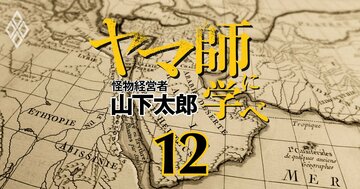
#11
国を滅ぼした石油で、国を再び興す!70歳を前に “ヤマ師”太郎がたどり着いた「でっかいこと」【アラビア石油を創った男】
戦後の事業で堅実に成功を収めながらも、「もっとでっかいことを」と模索し続けた太郎が、70歳を前にたどり着いたのは、戦争の根本原因と見定めた「石油」による国の自立だった。「石油報国」という新たな使命に、太郎は残る人生を賭けることを決意する。

1951年、日本がサンフランシスコ講和条約を目前に控え、占領から独立へと向かう節目に当たって、国際決済銀行副会長などを務めた銀行家で国際人でもあった加納久朗が、敗戦で富を失った日本が再び世界の一員となるための「精神の再建」を説いている。
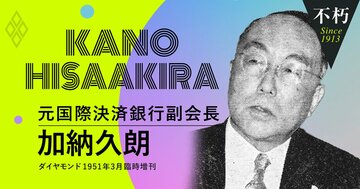
#10
終戦で消えた6兆円、個人資産を未来に託した“ヤマ師”太郎、ゼロからの再出発【アラビア石油を創った男】
終戦直前、太郎は満州で得た7億5000万円(現代の6兆円超)もの巨額資産を「国家と未来のために使う」と決意。軍事支援や科学技術振興に私財を投じようとしたが、敗戦と政府の方針転換で全てが水泡に帰してしまう。だが、時代の激変の中でも「自分のすべきこと」を貫いた太郎の姿勢は、現代のリーダーにも自分の資産や力の使い方という問いを投げかけている。
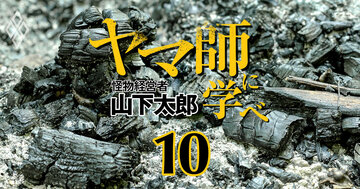
#9
一切の妥協を許さない!“ヤマ師”太郎が満州で「カネの成る木」を手に入れた信頼の力【アラビア石油を創った男】
満鉄社員向け社宅建設という大仕事に、太郎は一流の技師・市田菊治郎と共に「質」に徹した家づくりで応えた。細部まで妥協を許さず、快適性と耐久性を追求した社宅は高い評価を受け、以後の発注を独占。継続的な成功へとつながる。チャンスは手を抜かず全力を尽くす者にこそ味方する。

「週刊ダイヤモンド」1981年5月2・9日合併号に掲載された、元日清紡績社長で「財界四天王」の一人、櫻田武と、石川島播磨重工業(現IHI)社長から日本電信電話公社(現NTT)総裁に就任したばかりの真藤恒の対談。テーマは、電電公社の運営、公社民営論、日米経済摩擦、そして経営の本質にまで及んでいる。
