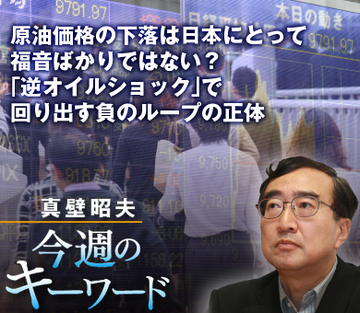真壁昭夫
第375回
GEとソニーの経営戦略は好対照を成している。GEは脱金融・製造業回帰へ舵を切るが、ソニーは金融や不動産など本業以外への依存度を高め、新規事業にも積極参入の方針だ。果たしてどちらが正解なのか。
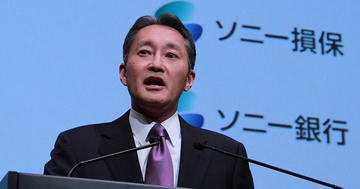
第374回
金融市場関係者の間で、ギリシャのデフォルトへの懸念が強まっている。このままでは同国の資金は5月にも枯渇する。デフォルトが現実化すれば、金融市場、さらにわが国を含む世界の実体経済への影響は必至だ。

第373回
足元の株高には、円安による企業業績の回復、異次元金融緩和策による“金余り”、GPIFや日銀などによる下支えがあり、当面は底堅い展開となりそうだ。しかし“金融相場”“官製相場”は意外と脆い。

第372回
2014年の国際特許出願件数で、中国のファーウェイが世界1位、国別でも同国が3位となった。その伸びは驚異的であり、過小評価できない。対して2位のわが国は前年比マイナス3%で、後退傾向が否めない。

第371回
シャープの苦境が続いている。液晶分野で一時は世界を席巻する勢いだった同社は、どこで誤ったのか。同社のみならず、日本の電機メーカーは世界戦略に欠けると指摘されてきた。各社が生き残る道は何か。

第370回
中国のAIIB創設は、世界の金融市場における米国の牙城を崩す目論見があった。そこに英国が、経済的な実利を狙って参加を表明。欧州主要国も雪崩を打って後を追い、米国陣営は一気に総崩れの様相となった。

第369回
“米国一人勝ち”の世界経済の中で、ドル独歩高が続いている。米国政府も、表面的にはこれを容認するスタンスを取ってきた。だが経済に陰りが見えれば、その姿勢は一変する。このまま現状が続くとは考えにくい。
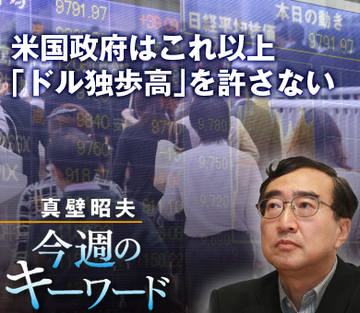
第368回
中国経済の減速が鮮明化している。今年の成長率は7%程度になると予想されるが、実態は3~4%との見方もある。経済の急減速は、社会を不安定化させ、共産党一党独裁というレジームを揺るがす可能性が高い。

第367回
大塚家具を筆頭として、最近同族経営の“お家騒動”が目立つ。肉親同士の反目を企業経営に持ち込むなど言語道断である。だが同社の問題は、ビジネスモデルの対立でも、また同族経営という形態にあるのでもない。

第366回
ギリシャの支援継続協議はとりあえず合意に至ったが、これは時間稼ぎにすぎない。問題の根底には、ユーロ圏が抱える本源的な矛盾がある。ではユーロ圏は将来、どうなるのか。考えられる道は三つある。

第365回
世界の主要国で、低インフレあるいはデフレの傾向が鮮明になっている。各国は金融緩和でその脱却を図るが、今のところ期待されたほど効果は上がっていない。金融緩和策の有効性を真剣に検証する必要がある。
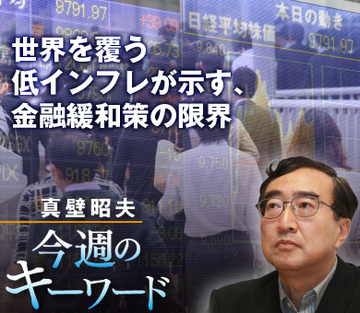
第364回
JA全中は安倍政権の改革案を受け入れ、事実上の解体が決まった。農業改革の第一歩として評価できる。だが、これだけでわが国の農業を活性化できるかといえば疑問だ。本当の農業改革にはまだまだ遠い。
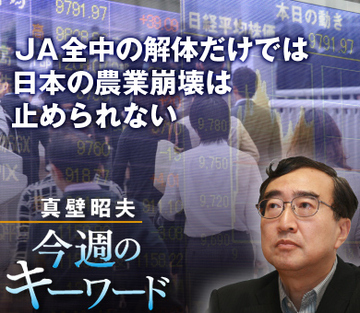
第363回
トヨタ自動車は今期、過去最高益を達成する見込みだ。好業績の基礎にあるのは同社に染み込んだ企業文化だが、その維持・継承に、創業家である豊田家が果たしている役割は大きい。

第362回
アップルは2015年度第1四半期決算で、過去最高の売上高と純利益を達成した。世界最大の需要地である中国で、スマホが堅調に売れた影響が大きい。同社の絶好調決算は、世界のスマホ市場で大きな地殻変動が起きつつあることを暗示している。
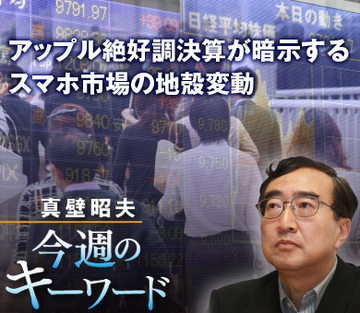
第361回
スイス中央銀行は、1ユーロ=1.2スイスフランの為替上限レートを撤廃すると発表した。その結果、ユーロ売り・スイスフラン買いの注文が殺到し、スイスフランが急騰した。スイス中銀の敗北により、「日銀限界説」が浮かび上がるかもしれない。
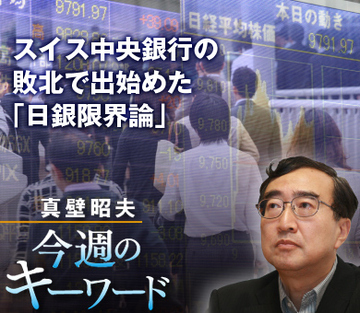
第360回
為替市場では、原油価格の下落に伴い、資源国通貨のみならず米国のドル高傾向にも一服感が出ている。米国景気に見え始めた天井の原因は、原油安ばかりではない。ドルのポジション調整を狙う投資家たちが、真に感じているリスクとは何か。
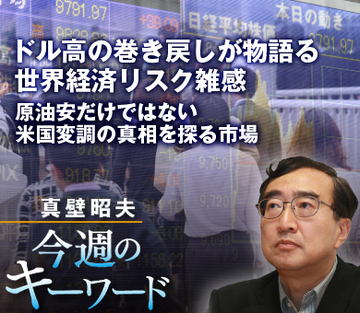
第359回
1980年代の“逆オイルショック”の再来とも言える今回の原油価格急落によって、ロシアをはじめとする資源国の経済も、大きな影響を被り始めている。いったい、原油はどこまで下がるのか。金融市場の投資家たちは、リスクをどう見据えて動くのか。
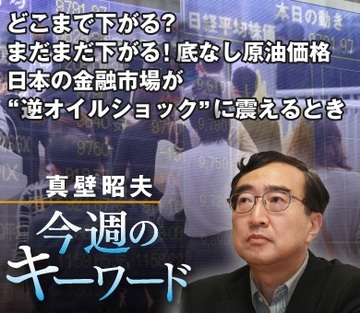
第358回
2014年の日本経済を振り返ると、円安・原油安・アベノミクスの3つのキーワードで総括することができる。今後、それらの行方いかんによって、マーケットの暴力的な是正が行われる可能性もある。2015年の日本経済をどう読み解くべきか。
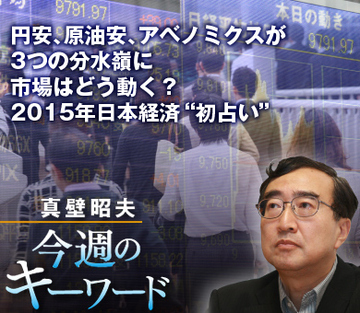
第357回
先の衆院選で与党が大勝し、アベノミクスによる安定した経済運営が続くこととなった。しかし、円安・株高の官制相場は長くは続かない。投資家は、足もとで起き始めた世界的なマネーフローの変化を読み解き、中長期的な運用方針を持つべきだ。
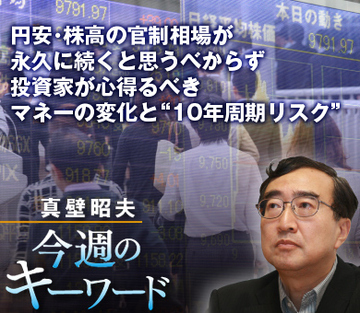
第356回
足もとで原油価格が急落している。背景には世界の需給バランスの問題がある。原油価格の下落は日本にとってまさに「福音」だが、そうとばかりも言っていられない。世界経済の悪化や円安の巻き返しなど、「負のループ」が起きる可能性もある。