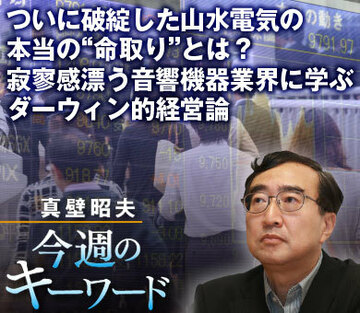真壁昭夫
第355回
約7年ぶりに、円が対ドルで120円の壁を突破した。アベノミクス以降の顕著な円安傾向は、どこまで続くのか。為替市場を左右するヘッジファンドや、ドル高を黙認してきた米国政府が虎視眈々と狙ているであろう“潮目”の決断を考察する。
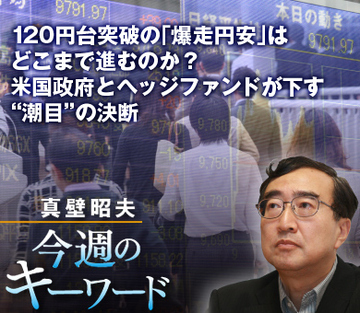
第354回
政策当局が経済対策を打ち続けても、経済活動の低迷が長期化する“日本病”が、欧米にも広まりつつある。ただ、日本の場合は他国と比べて、この病から抜け出すことが難しい。アベノミクスは、本当に日本病の処方箋となり得るのか。
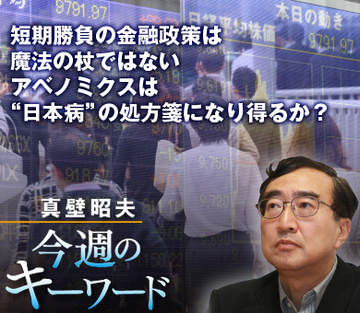
第353回
安倍首相の衆院解散・総選挙の判断は、はっきり言ってよくわからない。与党が決めた消費税率の再引き上げ延期について、事実上国民の合意は形成されている。またアベノミクスも、筆者に言わせればまだ前哨戦の段階だ。では、何が争点なのか。
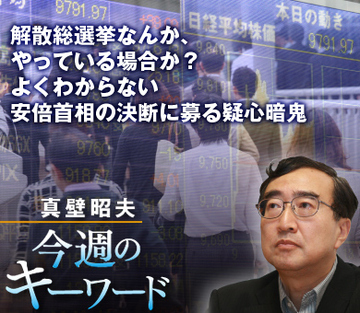
第352回
北京で開催されたAPECにおいて、ようやく日中首脳会談が実現した。安倍首相と対面した際の習近平国家主席の態度を、「ふてぶてしい」と評する声は少なくない。しかし目くじらを立てる必要はない。アジアのパワーバランスは変化し始めている。
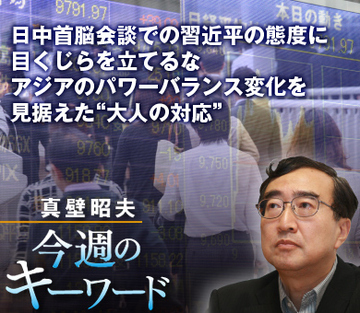
第351回
10月末、日銀の黒田総裁は思い切った追加金融緩和策(バズーカ砲第二弾)を唐突に発表した。人々を驚かせる黒田総裁のセンスは抜群だが、果たして金融緩和策にこれ以上の景気回復を望めるのか。その実効性をそろそろ真剣に議論しよう。
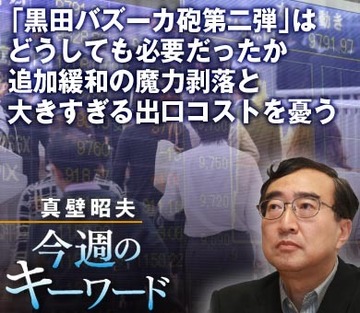
第350回
米国のFRBは、今月で超金融緩和策を打ち止めにすることを決定した。リーマンショック発生後、景気の下支えとして実施されてきた緩和策の終焉により、今後世界経済はどう動くのか。注視されているのが“金余り相場”へのインパクトだ。
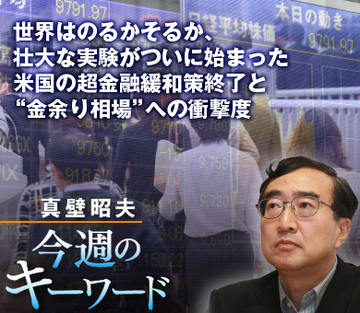
第349回
最近、投資家や経済専門家と話していると、彼らのアベノミクスに対する関心が低下していることがわかる。株価の不安定化や相次ぐ閣僚の辞任などの影響もあるだろうが、最近安倍首相の“空手形”が増えて来たと感じるのは、筆者だけだろうか。
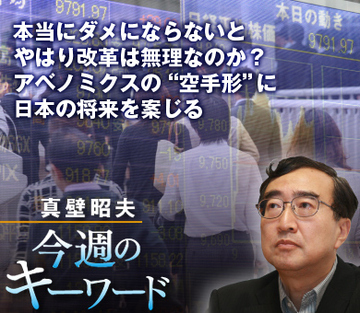
第348回
「IoT」(モノのインターネット)という言葉が、にわかに注目を浴び始めた。そもそもこの「IoT」とは、どんなイノベーションなのか。これまで“モノづくり重視型”のカルチャーが強かった日本企業は、新しい価値観への大転換を迫られそうだ。
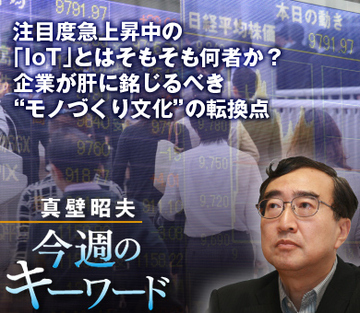
第347回
今年のノーベル物理学賞を日本人研究者3人が獲得したことは、画期的なニュースだった。しかし、その快挙に酔ってばかりでいいのか。「技術で勝ってもビジネスで負けている」と言われる日本の研究開発力について、いま一度問題提起すべきだろう。
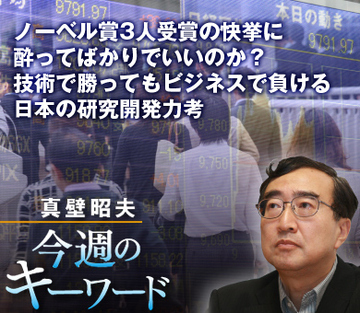
第346回
総合商社のドル箱だった資源ビジネスが、変調をきたしている。足もとでは住友商事が、シェールオイルを中心とする新型原油開発の失敗などで巨額の損失を計上した。背景には様々な環境変化も見える。資源ビジネスは、これからも本当においしいのか。
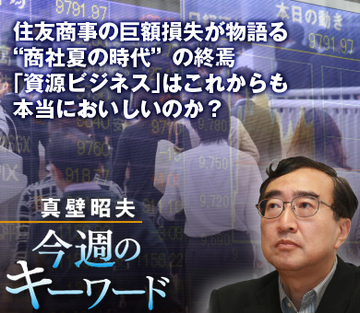
第345回
スコットランドの独立を決める住民投票は、同国の英国残留という結果に終わった。振り返ってみると、彼らの独立への見通しにはいくぶん荒唐無稽な部分があったし、今回の独立騒動がグローバリズムの進む世界へ投げかけた波紋は小さくない。
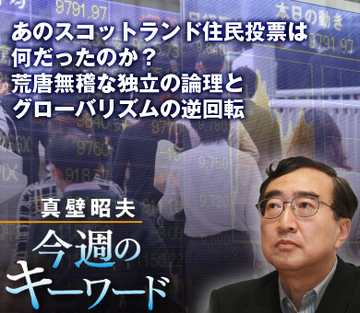
第344回
先頃ソニーは、今期決算において最終赤字額が2300億円に拡大する見通しを発表。スマホなどのモバイル端末事業を大リストラする。なぜ、ソニーの1人負けは続くのか。コアコンピタンスを失ったソニーが「ソニーでなくなる日」を考える。
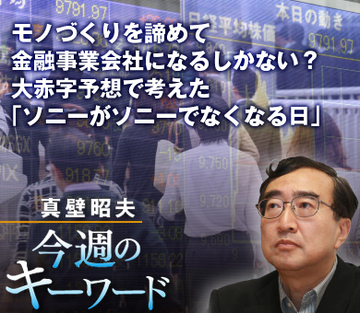
第343回
錦織圭選手の全米オープンでの活躍は、日本のみならず欧米諸国でも注目を浴びている。才能があっても壁を乗り越えられない若者が多いなか、錦織選手はなぜここまで頑張れたのか。人生一度のチャンスを生かせる指導者との付き合い方を探る。
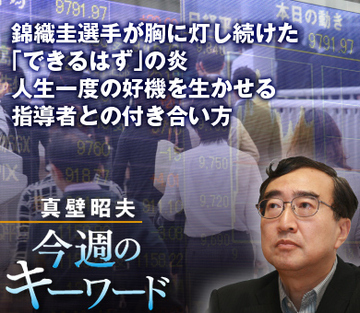
第342回
米国の金利上昇見通しに伴い、足もとの為替市場では円安・ドル高が加速している。アベノミクス以降の円安で、日本の輸出企業は復活したと言われるが、それだけで日本経済は底堅いものになっているのか。円安の中長期リスクを改めて検証する。
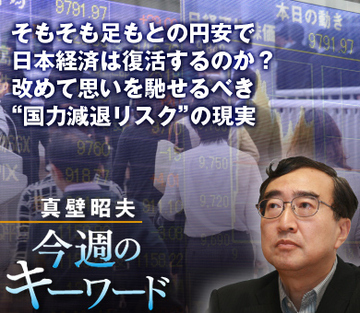
第341回
足もとでわが国の長期金利は、0.5%を下回る水準まで低下している。これだけ金利が低くなると、むしろお金の流れは阻害され、各国が政策を総動員しても景気はなかなか回復しない。こうした状況には、資本主義そのものの限界も垣間見える。

第340回
政務費の不透明な支出を追及されて号泣した野々村竜太郎・元兵庫県議に続き、山本景・大阪府議がLINEで中学生とトラブルを起こして問題となっている。政治信念なき彼らの言動は言語道断だ。地方議員たちが自覚すべき役割期待とは。
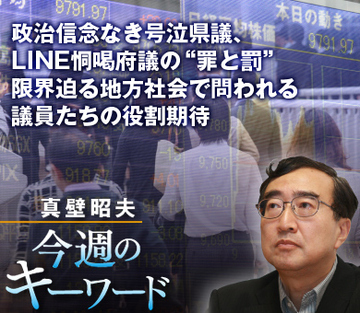
第339回
7月下旬に明るみに出た中国の期限切れ食肉問題で、日本企業は大きなダメージを受けた。中国は日本にとって依然として重要な市場だが、先行きには不安要因も多い。経営者は、そろそろ中国ビジネスのリターンとリスクを冷静に見極めるべきだ。
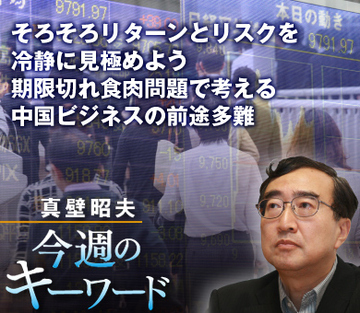
第338回
人類史上初の総力戦となった第一次世界大戦の開戦から、この7月で100年の時が経つ。足もとの世界情勢を見ると、当時の世相に通じるリスクも見られる。世界的なナショナリズムの台頭や多極化によって、今後世界はどこへ向かって行くのか。
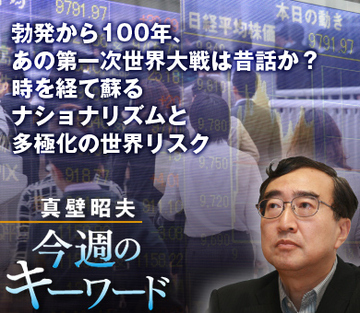
第337回
マレーシアの旅客機がウクライナ上空で撃墜されてから、数週間が過ぎた。親ロシア派の仕業と見られた事件は、ロシアの立場を危うくし、国際情勢に予想以上の影響をもたらしそうだ。日本もこの動きを睨み“ナイスガイ”から脱皮すべきだろう。
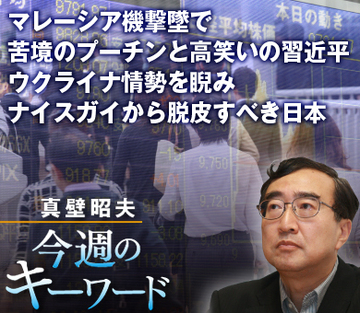
第336回
高級音響機器メーカーとして一世を風靡した山水電気が、ついに破綻した。全盛期の同社を知る人たちにとっては、寂寥感を感じる向きも多いだろう。かつての競合たちのように、どうして山水は生き残れなかったのか。筆者なりに分析したい。