篠原拓也
第6回
著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、同書の中から、「統計思考」の身につけ方を具体的なケースに基づいて教授する。最終回の今回は、マーケティングや統計調査でよく使われる「回帰分析」の正しい利用法について。使い方を誤ると、間違った推論へと導くことになりかねないので注意したい。

第5回
著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、同書の中から、「統計思考」の身につけ方を具体的なケースに基づいて教授する。今回は、がん検診の診断精度を上げることの難しさについて、精度のパーセンテージの面から考えていく。
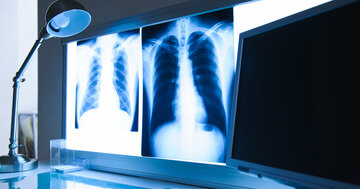
第4回
著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、同書の中から、「統計思考」の身につけ方を具体的なケースに基づいて教授する。今回のテーマは、「全会一致」によって不合理な意思決定を生まれる、「集団思考の罠」について。

第3回
著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、同書の中から、「統計思考」の身につけ方を具体的なケースに基づいて教授する。今回のテーマは、「お金の使い方」と「お金をどう稼いだか」の相関関係についての考察。

第2回
著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、同書の中から、「統計思考」の身につけ方を具体的なケースに基づいて教授する。今回のテーマは、断片的な情報から、全体の数を推測する方法について。仕事の実務でも、なにかと知っておくと便利なスキルだ。

第1回
このたび著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、情報を客観的に分析して適切な判断を行うための合理的な考え方「統計思考」の身につけ方を教授する。今回のテーマは「店の混み具合」。人は意外に確率的に行動するため、どの店の混み具合もある一定の割合に収れんしていくという現象について。
