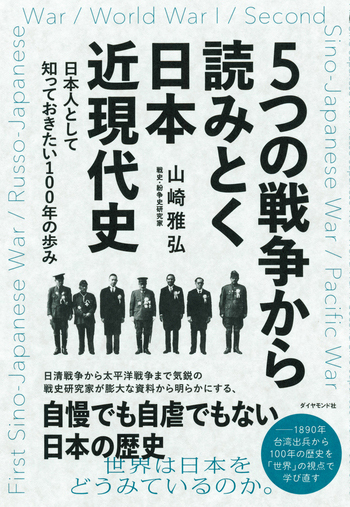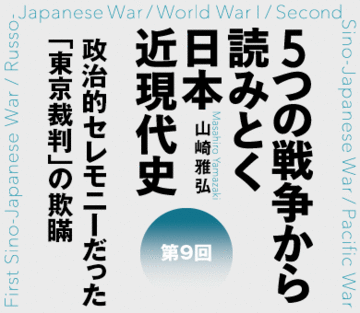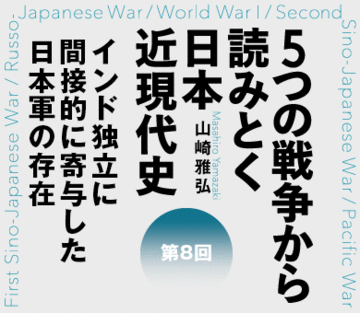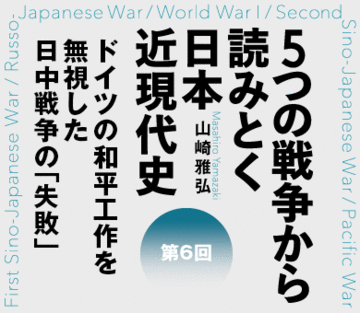近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売半月でたちまち3刷・5万5000部突破の気鋭の戦史・紛争史研究の山崎雅弘による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第10回は日本国憲法の成立過程、そして戦後の教科書に書かれた「民主主義」の内容を解説します。

日本国憲法は米国からの“押しつけ憲法”だったのか
マッカーサーとGHQは、日本の占領統治を開始した直後から、戦後の日本を民主化するためには憲法の改正が不可欠だと考えていました。明治以来の日本の憲法である「大日本帝国憲法」は、封建的な要素が多すぎる上、民主主義の根幹である「人権」や「自由」を国民に保障しない内容になっていたからです。
マッカーサーは最初、元首相で敗戦後も国務大臣という地位にあった近衛文麿に、新憲法の準備を示唆(要請)しました。ところが、「日中戦争を始めた時の首相として戦犯に訴追される可能性が高い近衛に、新憲法を作らせるのか」という声がアメリカ政府内で上がり、1945年10月9日に発足した幣原喜重郎内閣がその作業を引き継ぎました。
幣原内閣は、商法学者の松本烝治国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」を立ち上げ、憲法草案の作成を命じました。松本は、マッカーサーとGHQが求める「自由主義」や「民主主義」を一部で取り入れつつも、天皇主権の基本原則はそのまま残すなど、全体としては「大日本帝国憲法の焼き直し」のような「草案」を作成しました。
そこで、マッカーサーは極東委員会の活動がスタートする前に、GHQで新たな「憲法草案」を作る方策に切り替え、民政局長コートニー・ホイットニー准将をリーダーとする25人のスタッフが、1946年2月4日から憲法文案の作成に取りかかりました。
しかし、彼らの中には憲法学の専門家が一人もいなかったため、民間の日本人が既に作成していた憲法草案や欧米諸国の憲法などを参考にして、試案がまとめられました。
それらの参考資料の中で、特に大きな意味を持っていたとされるのが、1945年12月26日に民間の憲法研究団体「憲法研究会」が発表した「憲法草案要綱」でした。社会統計学者の高野岩三郎などが中心となって作られた、この憲法草案要綱には、後の「日本国憲法」の骨格となる「国民主権」「天皇は国民の総意の下で国家的儀礼を司る存在に留める」「男女平等」「基本的人権と言論・表現の自由の保障」などが盛り込まれており、発表から5日後の12月31日には、GHQは早くもこの草案の英訳版を作成して、内容の研究を開始していました。
以上のような経緯が示す通り、日本国憲法は単純な「GHQの押し付け」でも「事情を知らないアメリカ人が数日で適当に作った代物」でもなく、マッカーサーとアメリカ政府の意向を色濃く反映しつつも、多くの日本人の意見や要望を内容に反映させた上、帝国議会(国会)での正統な審議を経て作成された「日米合作の新憲法」でした。
敗戦3年後に刊行された
「民主主義」の教科書には何が書かれていたのか
日本国憲法の施行から1年5ヵ月後の1948年10月、文部省は中学・高校生向けの教科書『民主主義』(上巻)を刊行し、全国の学校に配布しました。この教科書は、法学者の尾高朝雄が中心となって編集された上下2巻の構成で、内容は戦後の日本国民が、戦前戦中の「国体」に代わる国の基本的な枠組みとして、どのように「民主主義」を実践すべきかについて、平易な文章で説明するものでした。
例えば、第1章「民主主義の本質」では、民主主義を単に「政治形態」として形式的に捉えるのではなく、まずはその根本精神を理解することから始めるのが重要だと説いていました。人間が人間として自分自身を尊重し、互いに他人を尊重しあうということは、政治上の問題や議員の候補者について賛成や反対の投票をするよりも、はるかに大切な民主主義の心構えである、というのが、この教科書の教える「民主主義の本質」でした。
こうした考え方は、戦前戦中の国家神道体制下の日本において、一人一人の国民が人間として「尊重されていなかった」という深い反省に基づくものでした。本文の中には、次のような文章が記されていましたが、戦前から戦中、そして敗戦という激動の時代を生きた当時の日本人にとって、その説明は非常にリアルに感じられるものでした。
「これまでの日本では、どれだけ多くの人々が自分自身を卑しめ、ただ権力に屈従して暮らすことに甘んじて来たことであろうか、正しいと信ずることをも主張しえず、『無理が通れば道理引っこむ』と言い、『長いものには巻かれろ』と言って、泣き寝入りを続けて来たことであろうか」
「それは、自分自身を尊重しないというよりも、むしろ、自分自身を奴隷にしてはばからない態度である。人類を大きな不幸におとしいれる専制主義や独裁主義は、こういう民衆の態度をよいことにして、その上にのさばりかえるのである。だから、民主主義を体得するためにまず学ばなければならないのは、各人が自分自身の人格を尊重し、自らが正しいと考えるところの信念に忠実であるという精神なのである」
また、文部省は「日本国憲法」の第21条に記された「言論の自由」についても、それがどのような価値を持つものなのかを、この教科書でわかりやすく解説しました。
「民主主義が重んずる自由の中でも、とりわけ重要な意味を持つものは、言論の自由である。事実に基づかない判断ほど危険なものはないということは、日本人が最近の不幸な戦争中いやというほど経験したところである。ゆえに、新聞は事実を書き、ラジオは事実を伝える責任がある。国民は、これらの事実に基づいて、各自に良心的な判断を下し、その意見を自由に交換する」
以上のように、日本の敗戦から3年後に文部省が出版した『民主主義』の教科書は、一人一人の国民が、思考や価値判断を自分の所属する「集団」に委ねず、個人として主張や判断、行動を行うことこそが「民主主義」であると、子どもたちに教えていました。そして、事実に基づいて自由に議論することが、国民の正しい政治にとってどれほど重要なのかについても、この教科書は強調していました。
けれども、この教科書によって、戦後の日本が西欧のような「成熟した民主主義国」を目指す道をまっすぐに進んだかといえば、そうはなりませんでした。例えば、戦前戦中に比べると、個人の尊重という面でかなりましになったとはいえ、自分の所属する会社などの「集団」に思考や価値判断を委ねることを、さほど「悪い」とは思わず、むしろ自分からその道を選ぶ人が、戦後の日本でも数多く存在したのです。
では、なぜ戦後の日本社会において、社会制度としての民主主義の発達が中途半端な状況になってしまったのか。その理由はいろいろ考えられますが、第2次大戦後の国際社会を二分した「東西冷戦」の東アジアでの激化という日本の周辺環境も、日本の民主化にブレーキをかけた要素の一つでした。