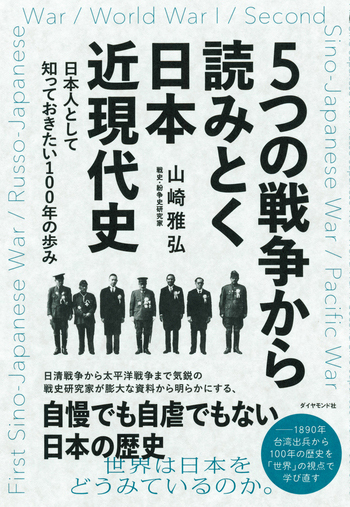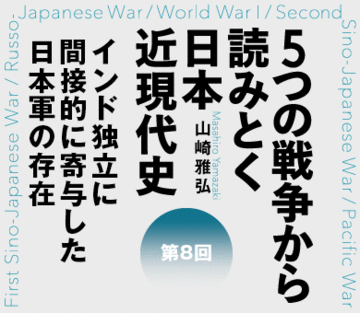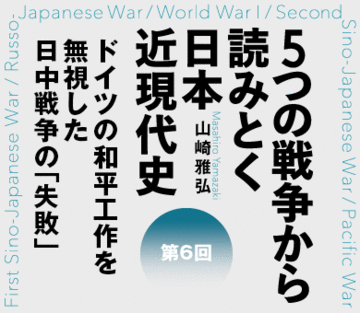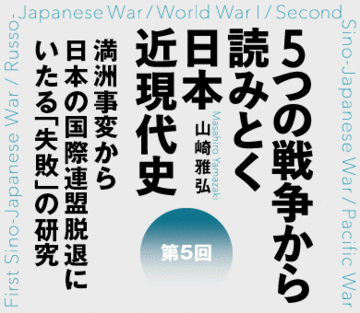近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売4日でたちまち重版・4万5000部突破の気鋭の戦史・紛争史研究の山崎雅弘による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第9回は政治的セレモニーだった「東京裁判」の実相を解説します。

戦勝国が敗戦国を裁く政治的セレモニー
天皇の人間宣言から5ヵ月後の1946年5月3日、東京の市ヶ谷にある旧陸軍士官学校の講堂で「極東国際軍事裁判」と呼ばれる、歴史的な出来事の幕が開かれました。この「裁判」の基本的な構図は、日本が第二次大戦中に犯した「戦争犯罪」を、戦勝国であるアメリカ、ソ連、イギリス、中国、フランスなどの計11ヵ国の「連合国」代表が裁くというものでした。
しかし、実際に裁判が始まってみると、そこで日本の「罪状」とされた条項の中には、当時の国際法ではきちんと定義されていない「平和に対する罪(戦争を始めた罪)」や「人道に対する罪」などの新しい概念が含まれていたため、被告となった日本の戦争指導者の弁護人はもとより、連合国の側にいる人間からも「この裁判はおかしいのではないか」という疑問の声があがっていました。
東京で開かれた極東国際軍事裁判(以下「東京裁判」と略)は、この前年の1945年11月20日にドイツのニュルンベルクで開始された、ナチスドイツの戦争指導者に対する同様の国際法廷「ニュルンベルク裁判」と対になるもので、第二次大戦は「日本とドイツという二大侵略国」によって引き起こされた戦争だと、国際社会で強く印象づけることが、その主な目的でした。つまり、この二つの裁判は、第二次大戦の勝者である連合国が「善」、敗者であるドイツと日本が「悪」であるとのわかりやすい図式を、国際法廷という権威づけの形式をとって歴史に記録する、いわば戦勝国主導の「政治的セレモニー(儀式)」でした。
これらの裁判の発端は、玉音放送から一週間前の1945年8月8日に、米英仏ソの四ヵ国代表者がロンドンで調印した「国際軍事裁判所憲章」で、まずドイツの戦争指導者を対象とするニュルンベルク裁判の準備が進められました。この憲章の第六条において、戦争犯罪の定義を「平和に対する罪」「(通例の)戦争犯罪」「人道に対する罪」の三種類に区分することが決定され、これがニュルンベルク裁判と東京裁判における罪状判断の基準とされました。ここで言う「平和に対する罪」とは、侵略戦争の計画・準備・実行、既存の国際条約に違反する形での戦争の計画・準備・実行などを指し、「人道に対する罪」とは、殺人や虐殺、奴隷化、国外追放、その他の非人道的行為を指すものと規定されていました。
また、被告となった日本の戦争指導者も、この三種類の区分に分けられ、「平和に対する罪」の被告がA級戦犯、「(通例の)戦争犯罪」の被告がB級戦犯、「人道に対する罪」の被告がC級戦犯と呼ばれました。つまり、A級・B級・C級という戦犯の区分は、罪状の軽重ではなく、その内容によって規定されたものでした。A級戦犯として訴追された日本の戦争指導者は、計28人で、東條英機元首相をはじめ、板垣征四郎(満洲事変当時の中心人物)、松井石根(南京攻略時の中支那方面軍司令官)、松岡洋右(日独伊三国同盟締結時の外相)などでしたが、日中戦争開始時の首相だった近衛文麿は、A級戦犯として訴追されると知らされた後、裁判が始まる前の1945年12月16日に服毒自殺しました。
また、戦前戦中の日本で最高決裁者とされていた昭和天皇は、裁判の始まりから終わりまで、一度も訴追の対象にはなりませんでした。東京裁判に代表を送った連合国の中で、オーストラリアと中国は天皇の訴追を強く求めましたが、当時大きな権限を握っていたマッカーサーは、前記したような「日本統治の方針」に基づき、占領政策の円滑な遂行には協力が不可欠だと考えていた天皇が戦犯として訴追されないよう、取り計らいました。
こじつけ、人違い、事後法……
「東京裁判」の欺瞞の正体
東京裁判で、日本の戦争指導者や日本軍人に対する訴因として挙げられた55項目の中には、事実関係から見て明らかに「おかしいもの」も含まれていました。例えば、1938年の張鼓峰事件と1939年のノモンハン事件は、どちらも満洲国とソ連およびモンゴルの国境認識の相違が原因で生じた「国境紛争」であり、共に戦闘終結後の外交交渉で決着がつけられた問題でした。人がほとんど住んでいない場所が戦場だったため、一般市民の死者も全くいなかったはずでした。
しかし、東京裁判では、張鼓峰事件とノモンハン事件は共に「平和に対する罪」の「侵略戦争の遂行」と、「殺人とその共同謀議」の「ソ連・モンゴル軍人およびソ連の一般人の殺害」の両方で、罪状として挙げられていました。これを罪状に含めたのは、紛争の相手国だったソ連でしたが、国境紛争という性質上当然のことながら、張鼓峰事件とノモンハン事件の戦場において「ソ連兵に殺された日本兵」も大勢いました。
また、訴因の中の「侵略戦争の計画準備」「戦争の開始」「侵略戦争の遂行」「宣戦布告前の攻撃による殺人」の4項目において、太平洋戦争の開始時にはまだ独立していなかった米領フィリピンや、太平洋戦争の最初から最後まで日本の同盟国であったタイについても、あたかも独立国あるいは連合国の一つであるかのように扱われていました(タイに対する「侵略戦争」については、後に証拠不十分として訴因から除外される)。
裁判が進むにつれて、こうした連合国側主張への疑問点が法廷でも議論の的となり、アメリカ人の弁護士の一人は法廷で「ではアメリカ軍が行った広島と長崎への原爆投下はどうなのだ、人道に対する罪には当たらないのか」と、戦勝国(連合国)が行った非人道的行為については一切触れない態度に疑問を呈する意見を述べていました。また、連合国側の判事として裁判に参加した、インド人の法律家ラダビノド・パルは、裁判自体の欺瞞性を鋭く指摘する意見書を提出し、「戦勝国であっても、事後に戦争犯罪を裁く法を作って公布する権限は持たない。よって、この裁判自体が有効かどうか、疑いを差し挟む余地がある」との理由で、被告全員の無罪を主張しました。
この東京裁判と並行して、シンガポールやフィリピンのマニラなどの計四九の法廷で、BC級戦犯の裁判が行われ、ここでも大勢の日本軍人が死刑判決を受けていました。訴因の多くは、現地住民の虐殺や、連合軍捕虜の虐待であり、1942年にフィリピンで起きた「バターン死の行進」(捕虜となったアメリカ兵とフィリピン兵が、病人も含めて炎天下の中で長距離を歩かされ、アメリカ兵約1200人とフィリピン人約1万人が死亡)や、タイとビルマを結ぶ泰緬(たいめん)鉄道建設(連合軍捕虜とアジア各地から徴用された労務者が一九四二年以降、苛酷な環境で鉄道建設に従事させられ、連合軍捕虜約1万3000人とアジア人労務者四万人以上が死亡)を含め、さまざまな出来事に基づく裁判が、5700人近くの被告に対して行われました。
捕虜虐待で告訴された日本軍人や朝鮮・台湾出身の軍属は、捕虜の処遇に関する国際条約(ジュネーブ条約)を上官から全く教えられておらず、多くの兵士は自分がなぜ裁かれているのか理解できませんでした。戦争中の日本軍で常識とされた「敵の捕虜となるのは屈辱」という考え方も、日本軍人による捕虜虐待をエスカレートさせた原因でした。
また、審理時間がわずかである場合も多く、ある試算によれば被告全体の四分の一ほどは「人違い」で告訴されたという不運に遭っていました。このBC級裁判によって、最終的に約1000人の日本軍人・軍属が死刑判決を受け、日本に帰国できないまま、アジア各地の刑務所で処刑されました。
以上のように、東京裁判は当時の国際法に基づく公正な「国際法廷」とは言えず、戦後の早い段階から「一方的で不当な勝者の裁き」ではないのか、という声が海外でも国内でも湧き起こりました。しかし、戦勝国の「人道に対する罪」が裁かれていないから「当時の日本に罪はない」という論理が成立するはずもなく、仮に不公平な裁判であったとしても、日本の戦争指導部が戦前・戦中に行った行動の責任が消えるわけではありませんでした。