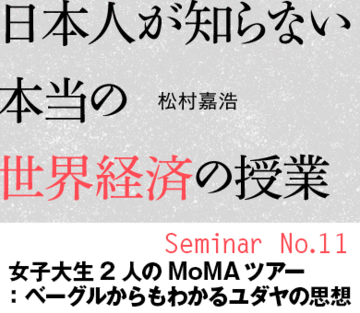世界の哲学者はいま何を考えているのか――21世紀において進行するIT革命、バイオテクノロジーの進展、宗教への回帰などに現代の哲学者がいかに応答しているのかを解説する、哲学者・岡本裕一朗氏による新連載です。9/9発売からたちまち重版出来(累計3万部突破)の新刊『いま世界の哲学者が考えていること』よりそのエッセンスを紹介していきます。第15回はヨーロッパにおけるイスラム教徒とキリスト教徒の共存について概観します。

なぜ私たちは宗教へと回帰しているのか
21世紀になって、宗教の問題を考えるには、グローバリゼーションの流れと切り離すことができません。というのも、グローバリゼーションは、一方で諸地域の緊密な結びつきを形成するとともに、他方で宗教的な対立を掻き立てているからです。今日、宗教運動は衰退するどころか、むしろホットな現象になっています。
この事実を直視したうえで、それがどこへ向かうのか、考える必要があります。そのために、ここではアメリカの政治学者サミュエル・ハンチントンが1996年に出版した『文明の衝突』を取り上げたいと思います。
この著作は、彼が1993年に『フォーリン・アフェアーズ』誌に掲載した論文「文明の衝突?」を、疑問符抜きで新たに詳述したものです。その中でハンチントンは、冷戦終結後の世界を理解するため、宗教を中心とした文明に注目したのです。そのさい、彼はフランシス・フクヤマのような一極的な世界秩序(自由民主主義の勝利)といったモデルをしりぞけ、七つあるいは八つを数える世界の主要文明へと分断されると考えました。
ハンチントンが「文明の衝突」論を展開するとき、決定的な要因になっているのは宗教です。たとえば、次のような記述を見れば、宗教の影響力がいかに大きいのか、分かると思います。
イスラム教徒と東方正教会や西欧のキリスト教徒との関係はしばしば激しいものだった。それぞれが相手にとって対立するものとなってきた。20世紀の自由民主主義とマルクス・レーニン主義の闘争は、イスラム世界とキリスト教世界とのたえざる激しい抗争とくらべれば、一時的で表面的な歴史的現象だった。
こうした「文明の衝突」論を読むと、宗教が異なれば、もはや紛争か対立、さらには戦争しか残されていないように見えます。はたして、それ以外の理解は不可能なのでしょうか。そこで、次に「文明の衝突」に対してどう対応するか、考えてみたいと思います。
そのために、フランスの宗教社会学者で現代のアラブ世界にも造詣が深いジル・ケペルの議論を見ておきたいと思います。ケペルは2008年に、「『文明の衝突』をこえて」というサブタイトルをもつ『テロと殉教』を出版していますが、その中でイスラムの原理主義運動を三段階に分類したうえで、ヨーロッパに数多く生活しているイスラム系の人々と、どう共生していくかを構想しています。
『テロと殉教』において、ケペルが取り上げるのは、2001年の9・11同時多発テロ以後、アメリカによって繰り返し発言された「《対テロ戦争》」と、「イスラム主義過激派」による「《殉教作戦》」です。それらを彼は、「二つの《大きな物語》」であると規定したうえで、その二つがともに破綻していると考えます。
ケペルによると、「中東が、ひいては世界全体がこの二つの《物語》のために政治的にのみならず、文化的にも、経済的にも、社会的にも行きづまっている」のです。
ここで注目したいのは、「ヨーロッパに根づいているイスラム系住民」に対して、ケペルがどのような議論を展開するか、という点です。「本書でわたしはヨーロッパのそうした現状を考慮に入れ、ヨーロッパが《テロ》と《殉教》のイデオロギーをのりこえ、イスラム系住民との関係をとおしてどんな風に新しい社会関係の厚みを構築していくことができるのか、という問題をさぐろうと思う」。
そこで問題となるのは、イスラム系住民とよりよい社会関係を構築するにはどうすればよいか、ということです。