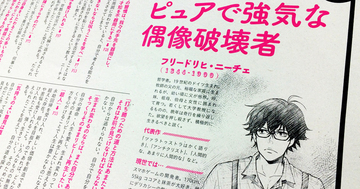17歳の女子高生・児嶋アリサはアルバイトの帰り道、「哲学の道」で哲学者・ニーチェと出会って、哲学のことを考え始めます。
そしてゴールデンウィークの最終日、ニーチェは「お前を超人にするため」と言い出し、キルケゴールを紹介してくれます。
そのキルケゴールは、「憂愁とは何か」、アリサに教えてくれるのでした。
ニーチェ、キルケゴール、サルトル、ショーペンハウアー、ハイデガー、ヤスパースなど、哲学の偉人たちがぞくぞくと現代的風貌となって京都に現れ、アリサに、“哲学する“とは何か、を教えていく感動の哲学エンタメ小説『ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』。今回は、先読み版の第22回めです。
えっ、なんでわかるんですか。たしかに黄昏れていました……
自分の人生ではなく、他人の人生を妬むことに時間を費やしてしまっている。情熱をもって生きないと、自分の人生は妬みに支配されてしまう――。
いままで自分の人生のために、時間をフル活用して生きてきた、とは胸を張って言えない自分がいることに、私は気づいた。人生の時間はいくらでもあるように思えていたが、刻一刻と、時間は過ぎていっているのだ。
私にとって、情熱を燃やせる生き方とは何か?を持たないまま、ただ時は残酷に減っていくばかりである。
「キルケゴールさん、なんかいろいろ教えてくれてありがとうございます」
「いえいえ、ところで、いまアリサさん“人生って思っているよりも短いんだな”と黄昏れていませんでした?」
「えっ、なんでわかるんですか。たしかに黄昏れていました……」
「フフッ。それが憂愁ですよ。僕はそういう切ない気持ちに浸ることが好きなんです。『青年は希望に幻影を持ち、老人は思い出に幻影を持つ』。何歳になっても人は黄昏れてしまうのかもしれません」
なるほど、これが憂愁か。たしかに憂愁に浸ると、世界が、いま生きているこの瞬間が、美しいもののように思えてくるのも、納得だ。
「あ、そろそろ時間だ。僕次の予定があるから、もう行かなきゃ。すいませーん、お会計お願いします!」
「あ、すいません、いくらでしたか?」
「ああ、大丈夫だよ。ここは僕が支払います」
「えっ、でも……」
財布を出しかけたところでニーチェが、
「問題はない。キルケゴール君は、お坊ちゃんなのだ」
そう言って深く頷いたので、私は「ごちそうさまです」と何度かお辞儀をして店を出た。
店の外に出ると、蒸し暑さはまだ残るものの、昼間の熱気は薄れていた。
キルケゴールは「Farvel、ニーチェ、アリサ!」と言ってまた繁華街の方に去っていった。