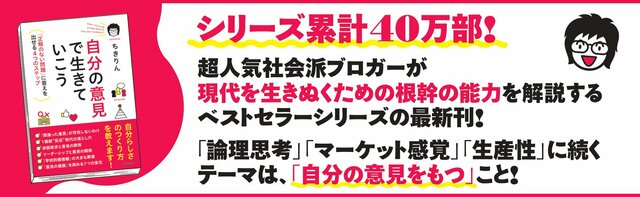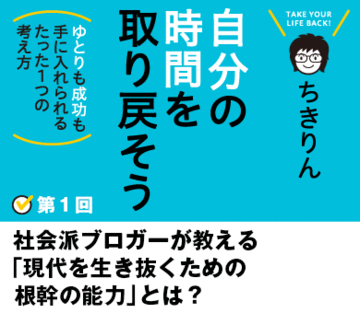私たちを取り巻く「忙しさの本質」とは?日本で働く人の最大の問題とは?
そして今、世界中で進みつつある「大きな変化」とは?
超人気ブロガー・ちきりんさんが、2つの視点から明らかになる1つの重要な概念と方法論を解説した『自分の時間を取り戻そう』が、発売直後から大きな話題となっています。
今回より同書の序章をベースに、「世の中にたくさんいる忙しすぎる人達」の生活を具体的な事例で見てみます。まずは「大手PR会社で働き、同期に先駆けて昇格した正樹」の物語です。
昇格後、正樹はますます忙しくなり残業時間も大幅に延びています。彼の働き方の問題はなにか?なにが解決の鍵なのか?ぜひ考えてみてください。
デキる男 正樹
正樹は33歳。今年の初め、同期に先駆けてグループマネージャーに昇格した。平均より数年は早い昇格だ。仕事は広告関係の企画営業で、商品プロモーションの企画案を立てて顧客に提案し、受注すればテーマ設定からメディア選定、細かいイベントの準備まですべての指揮を執る。
早期昇格が実現したのは顧客からの強い支持があったからだ。入社当初は仕事の要領もつかめず低空飛行が続いたが、ここ数年は顧客からの評価がぐっと高まり、自信もついた。
社内でも正樹の昇格は注目され、「実力さえあれば若くても責任あるポジションにつける実例」として新卒採用サイトにも掲載されている。昇格を機に交際数年になる美保とも婚約し、公私ともに順風満帆だ。
なのに昇格から1年、正樹は悩んでいた。以前は自分のプロジェクトだけに集中していればよかったが、昇格後は数人の部下がそれぞれ担当する合計20社近い顧客のプロジェクトすべてに目を配る必要がある。
なによりつらいのはスケジュールの自己管理ができなくなったことだ。これまではプロジェクトのピークが重ならないよう、提案時期を細かく調整していた。
ところが最近は、自分のプロジェクトがヤマ場を迎えている最中に部下のプロジェクトの締め切りが突然に設定される。「そういうことはもっと早めに……」と指導しているさなかに、他の部下からは「ちょっと困ったことが」とメールが飛び込む。
もっとも危険なのはなにも言ってこない部下だ。黙々と働いているから安心していたら、締め切りギリギリに持ってきた企画書があまりにお粗末で驚かされた。「先週からずっとやっててこれなのか?」――正樹は言葉を失った。
その日の夜、正樹はひとりでパソコンに向かっていた。手元にあるのは先ほどの部下の企画書だが、実質的にはほぼゼロから作り直さざるをえない。あと1週間の余裕があれば本人にやり直させる。だが顧客とのミーティングは明日だ。自分も同行することになっている。こんな企画書を見せるなんてありえない。「まったくいい根性をしてるよ」――パソコンの画面に向かって思わず愚痴が飛び出す。

今週末、美保からは新居に置く家具を見に行こうと誘われていた。しかしそれもちょっと難しい。週末には今日やるはずだった、自分のプロジェクトの進行表を完成させる必要がある。美保も正樹の立場については理解してくれており、不満を言われることはない。しかし昇格してから同じようなことが続いているのでちょっと心苦しい。
先のことを考えるとさらに不安が募る。美保は早めに子どもを産みたいという。それには正樹も賛成だ。だがこんな生活のまま父親になったらどうなるのか?
美保が専業主婦になる予定はない。正樹だって子育てには協力したいと思っている。しかし先日そう言って、こっぴどく叱られた。「協力する」とはどういうことだと。子育ては美保の仕事だが、自分も協力すると言っているのか?大袈裟な呆れ顔で見つめられ、正樹は言葉を失った。
両親の体調も不安のタネだ。昨年、父が高血圧で倒れ、ごく短期だが入院した。幸い大事には至らなかったが、この先なにがあるかわからない。母親も膝が痛い、腰が痛いとこぼしている。正樹には妹がいるが、今はキャリアアップを目指し留学中だ。
「今、オヤジが倒れたらどうなるんだ?」夜中に実家から電話があると、いつもぎょっとする。以前、父親が倒れたと電話がかかってきたときの衝撃が忘れられない。いつもはしっかりしている母親がパニックに陥り、ひとりではなにもできなかった。
それだけじゃない。そもそもグループマネージャーなんて自分にとってゴールでもなんでもない。さらに大きな仕事を手がけるには、課長、部長、本部長とステップアップしていく必要がある。
しかしそれは、部下の数が20人、30人と増えていくことを意味している。どんな働き方をすればそんなことが可能になるのか。今の正樹にはとても想像できない。
それにしてもプロとして最低限守るべきレベルを部下に理解させるのが、こんなに難しいとは。昇格前には想像もできなかった。
ようやく資料の修正が終わると、すでに日付も変わっている。正樹は資料をコピーしてファイルに詰めた。昼間ならスタッフに頼めるが、今は自分でやるしかない。
「ハラが減った」――ようやくほっとして、会社の前にあるラーメン屋に直行した。こんな時間にこんなものを食ってていいのか。豚骨のこってりしたスープを飲み干しながら、正樹は自分で自分に回答した。
「いいのだっ!」