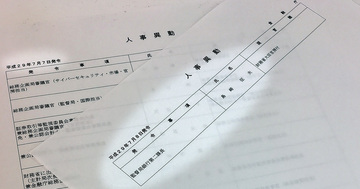金融庁の森信親長官の任期が異例の3年目に入った。斬新な改革を掲げて金融行政に変革をもたらし、特に地域金融機関に経営力強化を訴え続けてきた森長官にとって、政策の集大成となる「仕上げの年」になるのは間違いない。銀行は真に顧客本位のサービスを提供できる存在になれるのか。これまでの金融行政の経緯と、最近の地域金融機関の動きをまとめた『ドキュメント 金融庁vs. 地銀 生き残る銀行はどこか』(光文社新書)の取材チームの一人、中村宏之・読売新聞メディア局編集部次長が解説する。

かつて経済部の現場時代に筆者も取材した経験があるが、金融庁は当時から取材の難易度が高い役所の一つだった。個別金融機関の機密情報を扱っている上に、政策対応次第では金融市場への影響も大きい。
このため、もとより金融庁からの積極的な情報提供はほとんどない。さらに幹部も日々、忙しく動き回っており、正面から取材のアポイントが入るわけでもない。結局、局長室の前の廊下などで立って待ち、たまにトイレなどに出てくる時や退庁時のぶらさがり、夜討ち朝駆けをするのがせいぜいだった。なかなか進まない取材の中、「地検特捜部の取材のようだ」などと同僚と自嘲気味に言い合っていたのを思い出す。
ただ、それも無理もないことだった、と今になれば思う。1997年以降の未曽有の金融危機を経て、銀行に苛烈な不良債権処理を迫り、検査を強化して、経営体力が低下した銀行には破綻処理や公的資金注入による資本増強を行う時代だった。処理を一つ間違えば、日本経済全体にも悪影響を与えかねないプレッシャーの中で、金融庁も英知を絞って対応している様子が、取材を積み重ねる中で見てとれた。
りそな銀行や足利銀行など、政府が金融危機対応会議を開いて公的資金の注入や破綻処理に奔走していた時代から今や10年以上もの時を経た。銀行の不良債権処理にメドがついてからも久しい。近年の金融行政は、表面的には「平時」モードである。