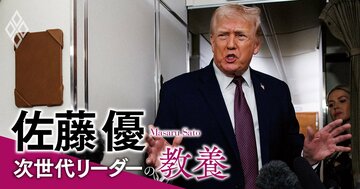外資系トップの多くはMBAを取得し、その知識をビジネスの現場で積極的に実践することで、企業を活性化している。外資系を渡り歩きキャリアを積んできた、日本コカ・コーラ会長 魚谷雅彦氏に独自の問題発見・解決法を学ぶ。
 |
| 魚谷雅彦 日本コカ・コーラ会長 |
ライオン(在職中にコロンビア大学でMBA取得)、シティバンクなどを経て、1994年に、日本コカ・コーラに入社した魚谷雅彦会長(当時は副社長)は、じつはヘッドハンティングの誘いを断っていた。
というのも、国内飲料市場の3割のシェアを握る日本コカ・コーラは、「全世界で事業展開をしており、ビジネススクールの教科書に出てくるような会社。自分ができる仕事などないと思った」(魚谷会長)からだ。
それでも、当時の社長だったマイク・ホール氏の説得に押し切られるかたちで入社。
すると、「完璧な会社」に見えたコカ・コーラにも大きな問題が内在していることに気づく。
日本におけるコカ・コーラのビジネスは、マーケティング戦略を立てる日本コカ・コーラと、飲料を製造するボトラー12社からなる複雑な事業形態を取っている。
組織が大規模化、複雑化すればするほど、現場の情報がトップへ伝わりにくくなるのは、どんな会社でも同じこと。伝言ゲームのように問題の本質が曲げられていくという現実を目の当たりにした魚谷会長は、直接、現場の情報収集に踏み切る。
じつは、いまや伝説となった「爽健美茶」のヒットは、魚谷会長の問題発見から生まれたものだ。
「広告宣伝をしているウーロン茶と、広告宣伝をしていない爽健美茶の自動販売機での販売数量が同じなんです」。