論文発表当時、アメリカでは政府機関や教育機関に人材が流れ、企業は優秀な若者の関心を引き、確保することが難しい状況にあった。その原因をドラッカーは、企業が彼らの期待を満たしていないためだとした。彼らが企業に求めるのは、やりがいと機会、知的かつ金銭的な見返りそして社会的かつ倫理的リーダーシップだというのだ。当時とは背景は異なるものの、優秀な人材が確保できないという状況たとえば「ウォー・フォー・タレント」は、この数年よく話題に上る。優秀な人材にアピールするための「企業の魅力」を考えるうえで現代にも示唆を与える論考といえる。
魅力に欠ける企業でのキャリア
大学や大学院に在籍している高学歴の若者たちは、10年、いや15年前に比べると、企業でのキャリアにあまり魅力を感じていないようだ。これは少なくとも、企業の新卒採用担当者や大学の就職部長、学生との関わりが深い教員の間でも一致した見解である。
この現象は予想どおり、「企業への敵意」などといった月並みな表現を呼び起こし、「社会主義者」が大学教員の間で幅を利かせるといった状況を連想させる。しかし、若者は企業にけっして敵対的ではない。あまり興味を抱いていないだけなのだ。
企業でのキャリアが大学生にとって最も魅力的だったのは、「ネオ・リベラル派」が大学のキャンパスで影響力を振るっていた1940年代後半から50年代初めにかけてだった。
若者は、企業でのキャリアに幻滅している。その幻滅の背景にある本当の理由は、一般に思われているよりはるかに重大で深刻だ。給与の面でも、そして何より機会の面でも、若者の就職先としての企業の優位性は大きく失墜している。
また、企業は知的な期待や知的な主義主張に応えられていない。事実がどうあれ、教養ある若者の目にはそのように映っている。つまるところ、高学歴の若者は、企業の基本的価値観をきわめて物足りないと考えているのだ。
競争力の低下
第二次世界大戦後10~15年くらいの間、企業、特に大企業の初任給以上の給与を大卒者に支給できる他の雇用主は存在しなかった。
企業以外の就職先、特に政府や高等教育機関における給与水準は、底打ち状態からようやく上向き始めたばかりだった。一方、企業の給与はというと、とりわけ新入社員の給与は、組合賃金と密接に連動していたとはいえ、急激に上昇していた。
同時に、企業における雇用機会は、他分野をはるかにしのいでいた。アメリカ企業がおしなべて肉体労働から知識労働へと大いなる転換を遂げたのは、この戦後時代のことである。マーケティングや経理、R&D、人事など、あらゆる分野で、大規模な人員増強が図られた。どの部門も、教育水準の高い人員を大量に求めていたのだ。
また、企業に就職すれば、他のどの分野より恵まれた昇進機会が用意されていた。30年代から40年代初頭までは、企業での就職口がほとんどなかったため、政府や高等教育機関が就職先として人気を集めていた。
その結果、第二次世界大戦直後の数年間は政府や高等教育機関では、35年前後に大学を卒業した職員が多く、人手には不自由していなかった。しかも彼らはまだ若く、キャリア形成の途上にあった。
対照的に企業では、戦後初期には高年齢化が進んでいた。50年前後におけるアメリカの典型的な「若手経営幹部」とは、若くても50歳を超えており、大恐慌時代以前のはるか昔から働いている者たちだった。
したがって、40年代後半から50年代にかけて、企業に職を得た野心的な若者たちには速いテンポの昇進が期待できたのである。
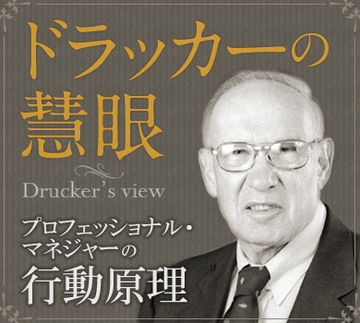
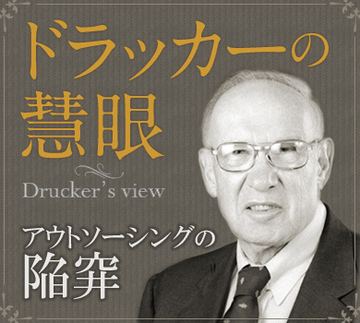
![【1981年マッキンゼー賞受賞論文】[新訳]「日本株式会社論」を論破する日本の成功の背後にあるもの](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/0/0/360wm/img_00443c7f84bf9434aca449d8bdb0154789893.jpg)
![【1971年マッキンゼー賞受賞論文】[新訳]欧米企業が抱える問題を解決する日本の経営から学ぶもの](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/3/360wm/img_4329cc16e10b4dfa5044183069c6183388331.jpg)



