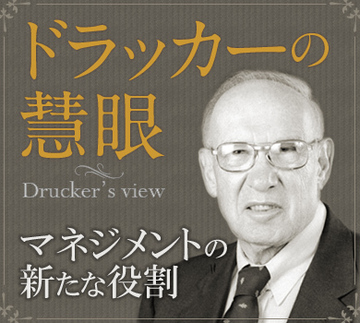政府と産業界の密接な結びつき、円満な労使関係などは、そもそも誤解であり、また、日本の経済的成功の背後に日本株式会社があったわけではないと、ドラッカーはいわゆる「日本株式会社論」を論破する。日本人はみな、職業と仕事において一番になることを熱望しており、そこにこそ、日本のこれまでの発展、そしてこれから遂げるであろう発展の秘密が隠されていると言う。なお、当論文の日本語版における初出は1981年6月号である。再掲載に当たり、新たに翻訳を行っている。
「日本株式会社」は一枚岩ではない
「私は、ロシア人よりも日本人のほうが恐ろしい」
ある若い弁護士が、私にこう言った。
「たしかに、ロシア人は世界を征服しようとしている。だが、彼らの一体性は上から押しつけられたものであり、難局を乗り切れるとは思えない。一方、日本人も世界を征服しようとしているが、彼らの一体性は内部から来ている。彼らは、1つのスーパーコングロマリットとして行動する」
西欧人は、そのコングロマリットをしばしば「日本株式会社」と評する。しかし日本人にとって「日本株式会社」は、ジョークにすぎない。それも、あまりできのよくないジョークだ。
日本人の目に映るのは亀裂であり、外国人の目に映るような一枚岩ではない。また、日常生活のなかで日本人が感じているのは、緊張や圧力、対立であり、一体性ではない。彼らは、大銀行や巨大企業グループの間で繰り広げられる、食うか食われるかとまではいかないにしても、熾烈な競争を目にしている。
そしてみずからも、日本の組織の特徴である内部の派閥争いに日々関わっている。各省庁は他の省庁を相手に飽きることなくゲリラ戦を仕掛け、派閥の内輪もめが政党や内閣、大学、民間企業を動かす。
なかでも特に注意すべきことは、外国人からは日本政府と日本企業が密接に協力しているように見える場合でも、日本人の目には政府が余計な干渉をして指図しようとしているとしか映らないことだろう。ある大会社のCEOはかつて、「我々は同じ綱を引いている。だが、互いに反対方向に引っ張り合っている」と語ったものだ。
日本政府は、国益のために産業界の一致した協力を引き出すことに、常に成功しているわけではない。たとえば、全権力を掌握しているといわれる通商産業省が、20年にわたって圧力をかけ続けたにもかかわらず、どうしても大手コンピュータ・メーカー各社を連携させることができずにいる。これは、ドイツやフランス、イギリスにおいては、政府がうまくやりおおせたことである。
外国人はこぞって、円満な日本の労使関係をほめそやす。ところが、日本の庶民は、国有鉄道がたびたび起こす不法ストに不平たらたらだ。労使関係が円満なのは、労働組合がことのほか非力な領域、すなわち民間部門だけである。
日本の労働組合の指導者がいささか辛辣に指摘するように、西欧の企業でも労働組合を持たないところ(たとえばIBM)では、日本企業と同じように落ち着いた労使関係が見られる。しかし、第二次世界大戦後のアメリカによる占領の名残りで労働組合の力が強い公的部門では、世界に名高い円満な労使関係など、どこにも見当たらないのである。
とはいえ、日本人の間では、世界経済に効果的に参入するためのコンセンサスは出来上がっている。「日本株式会社の奇跡」という一般通念とは相反するが、日本の産業が競争力を持つ理由は、考え方や行動が一枚岩だからではない。
それよりもはるかに興味深い要因、すなわち、日本人の国民性の特徴を利用することで効果的な経済行動を生み出すという、政治的慣行の結果なのである。
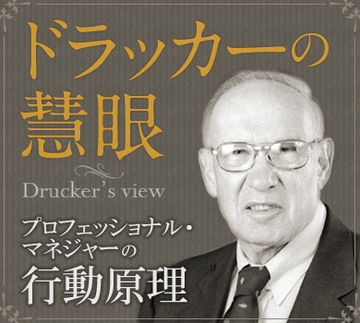
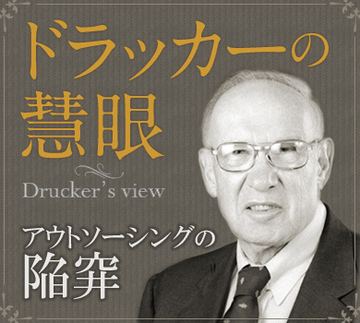
![【1971年マッキンゼー賞受賞論文】[新訳]欧米企業が抱える問題を解決する日本の経営から学ぶもの](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/3/360wm/img_4329cc16e10b4dfa5044183069c6183388331.jpg)