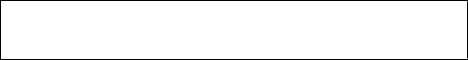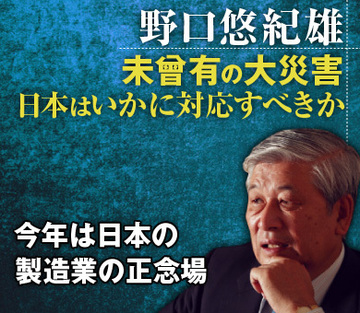かつて、“日立”と言えば、東日本では日立製作所を指し、西日本では日立造船を指した。日立造船は、最も早く海外輸出を加速させた名門造船メーカーだが、独立系ゆえに造船比率が高く、「いつ倒産しても不思議はない」と言われ続けてきた。後に、産業界でも類例のない“本業の切り離し”に踏み込んだ同社は、造船時代とは異なる環境ビジネスで再び飛躍を遂げつつある。(「週刊ダイヤモンド」編集部 池冨 仁)
雪は降っていなかったが、非常に寒い日の午後だった。
2011年2月15日、スイスのチューリッヒに飛んだ日立造船の古川実会長兼社長とスタッフは、イノバ社を訪れた。同社は、技術開発力とオペレーティング能力に定評があり、欧州で「ゴミ焼却発電施設」(都市ゴミを燃料にした発電システム)のシェアで約40%を握る最大の老舗メーカーである。
イノバ社の前身のフォンロール社と日立造船は、古くは1960年にライセンス契約を締結して、日本に欧州式のゴミ焼却発電施設の技術を導入した。過去50年間、日立造船はフォンロール社のライセンシー(技術供与を許可された提携関係)という立場にあった。
それが一転、イノバ社の親会社が倒産して連鎖倒産の危機に直面し、急に資金が回らなくなった。そこで、ライセンシーだった日立造船が救済に乗り出したのだ。
辻勝久Vプロジェクト室長は、「今回の買収は、最初にイノバ社の不穏情報をキャッチし、水面下で接触を開始してから、12月20日に買収合意に至るまで、わずか1ヵ月という極秘のプロジェクトだった」と、振り返る。Vプロジェクトとは、フォンロール社の頭文字と英語のビクトリー(勝利)をかけたコードネームだった。
 イノバ社の買収により、日立造船は欧州市場を確保するとともに、全世界の市場を視野に入れた事業展開が可能になった。両社が培ってきた技術力は高い相乗効果が見込まれている
イノバ社の買収により、日立造船は欧州市場を確保するとともに、全世界の市場を視野に入れた事業展開が可能になった。両社が培ってきた技術力は高い相乗効果が見込まれている
その約2ヵ月後、初めてイノバ社を訪れるに当たり、古川社長は、300人の全社員を講堂に集めてもらった。自分たちが年末年始をゆっくり過ごせたのは、日立造船が約50億円の資金を出してくれたおかげということもあり、社員たちは期待と不安を抱えて古川社長を出迎えた。
英文の台本はあらかじめ用意されていたが、途中まで読んだところで、古川社長は台本に落としていた視線を上げ、社員に向かって自分の言葉で話し始めた。「ヘタな英語ですが、私の思いを話したい」と断って、「(1)雇用は守る、(2)研究・開発費は削らない、(3)一緒に、ダントツの世界一を目指そう」と強く訴えたのである。