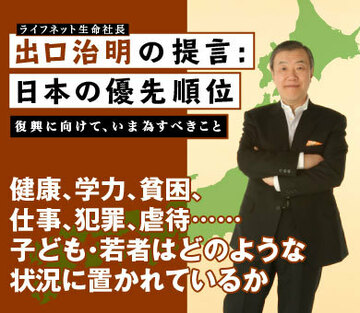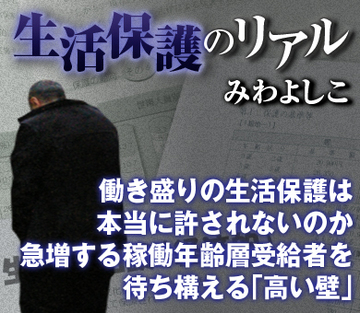格差が拡大する一方の日本社会
「一億総中流社会」はもはや崩壊
1990年代初頭、大規模な資産バブル崩壊の後、わが国経済は低迷が続き、過去20年間に名目ベースのGDPはほとんど増加していない。そうした状況下、我々の身近で着実に「貧富の差=経済的格差」が拡大している。
生活保護の受給者は史上最高水準に達している。有体に言えば、所得水準が下落して、厳しい生活を強いられている人が増えているのである。そうした「貧困」と呼ばれる経済状態について様々な見方がある。そもそも貧困に関する定義に関しても、それぞれ国や機関によって異なっている。
一般的に、貧困について使われる定義には代表的な2つがある。1つは「絶対的貧困」だ。この定義は、1970年代に世界銀行が使い始めた。
2000年代以降、この定義では、年収370ドル(約2万9000円)以下、あるいは1日1ドル(約78円)以下という絶対的な水準を設定し、その水準以下で生活している人を「貧困」と定義する。幸運にして、わが国にはこの定義に当てはまる人々の数は多くはない。
もう1つは、「相対貧困」というコンセプトだ。これは、国民の所得分布の中で、その人がどこに位置するかによって経済状態を判断し、貧困の状態を定義する。
具体的には、国民の所得から税金や社会保障費などを差し引いた可処分所得の分布をつくり、その中間値の半分に満たない人たちを貧困と定義する。
厚生労働省が発表した「平成22年国民生活基礎調査の概況」によると、平成21年の国民1人あたりの名目ベースの年収は250万円となっている。それを例にとると、わが国では年収が125万円に満たない人が相対的な貧困ということになる。
最近、わが国では、その相対貧困率が急速に高まっている。かつての“一億総中流社会”の面影はない。間違いなく、貧富の差が広がる現象が起きている。
今から二十余年前まで、わが国の国民の多くが“中流意識”を持っていた。それだけ経済的な状況に多くの格差がなかったということだ。その背景には、戦後の高度成長とそれに続く大規模なバブルの発生があった。