
真壁昭夫
中国勢に負ける?トヨタがたった3年で社長交代した“焦り”の正体
トヨタ社長が異例の3年交代となった背景には、中国勢の電動車シフトとAI急成長のインパクトが想像以上に大きいことが挙げられる。トヨタとて全方位戦略で世界トップを維持するのも容易ではない。中国勢に負けず劣らず、研究開発と設備投資を推し進めるには、他社との連携が重要だ。目下、レアアースの中国依存も引き下げなければならない。これまで以上に、トヨタの事業戦略が日本経済の回復を左右するはずだ。

見えた!日本経済の勝ち筋、「アンソロピック・ショック」で米中印の株価が下落しても日本は上昇したワケ
米アンソロピックが最新AIモデルを発表したことで、「AIが従来のSaaSを時代遅れにするのではないか」という懸念が株式市場に広がった。マイクロソフトやセールスフォース、アドビといった大手や、関連投資を行う資産運用会社にも波及し、世界的な売り圧力に。米国だけでもソフトウエア株の時価総額が1週間で1兆ドル(約150兆円)消失したと報じられた。AIに代替される「SaaSの死」は本当か。
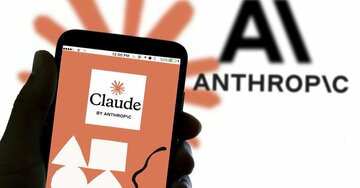
「円安ホクホク」と浮かれる日本と大違い!中国とロシアが進める「ドル高是正リスク」への“賢い対策”
高市首相が衆院選の遊説で「円安は輸出産業にとっては大チャンス」「外為特会の運用がホクホク状態」などと発言し物議を醸している。その後のSNS投稿で、「為替変動にも強い経済構造をつくりたいという趣旨だった」と説明したものの、「円安を容認しているのでは」との指摘は多い。一方、トランプ米大統領は「ドル高を是正したい」狙いがある。それはなぜか。外国為替市場の最新事情と、金(ゴールド)保有が世界で高まる背景を解説する。

「消費税ゼロ」に世界が失望…政治家の人気取りで日本人が背負わされる“大きすぎる代償”
食料品の消費税をゼロにするには、何を財源にするかが明確でなければ財政が悪化する。日本の国債の流通市場では財政悪化への懸念から「金利が急上昇」している。世界の投資家は、衆院選後を見通し、財政破綻リスクの上昇を警戒しているのだ。選挙の結果次第では、先行き不透明感の高まりから株安、通貨安、国債安(金利上昇)のトリプル安が起きる可能性は否定できない。日本経済を強くするために「本当に必要な政策」とは何か。

残念ですが高市トレードは切り札になりません…日本経済が復活できない“身もフタもない理由”
高市政権下で、最も注目すべきは円安が加速したことだ。現在の日本経済の課題は、円安・物価上昇・金利上昇の「負の連鎖」を止められないことだ。高市トレードと政策の矛盾、弊害を抑えるにはどうしたらいいのか。また、解散総選挙の行方によっては、今までの逆、株価の下落と円高への転換、長期金利の下げ止まりの方向に動くことも考えられる。

米トランプ「ドンロー主義」に対して日本が今すぐやるべきこと、「防衛力の強化」ともう1つは?
トランプ米大統領がベネズエラ攻撃に続いてグリーンランド領有に意欲的だ。中国やロシアへの抑止力に加えて、ベネズエラで石油を抑え、グリーンランドでレアアースを確保したい意向があるようだ。トランプ氏は、習近平国家主席やプーチン大統領と同様、武力による覇権拡大に手を付け始めた。世界平和や秩序は崩壊の危機に直面している。わが国がすべきことは何か。

孫正義が「6兆円出資」を回収する“驚きの方法”…カギを握る日本のモノづくり企業とは?
ソフトバンクグループを率いる孫正義氏が、史上最大の賭けに出た。ChatGPTを開発した米オープンAIに総額6兆円超の大型出資を実行しているのだ。AIが人間の知性を超える時代を、夢物語ではなく現実のものにするために、孫氏は勝負を掛けた。その裏には、米国のソフトウェアと日本のハードウェアの新結合も秘められていそうだ。
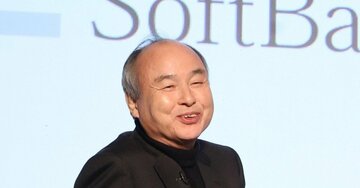
エヌビディア「一強時代」がついに終焉?割って入った「最強ライバル」の名前
半導体ビジネスで独走状態の米エヌビディア。株価も絶好調で米株式市場が最高値を更新する際のけん引役でもあった。一体、いつまで独り勝ちが続くのか? 実は少しずつ、勢力図に変化の兆しが表れている。エヌビディアの最大のライバルは、関連部材を主に韓国企業から調達している。この変化に追いつけないと、日本企業の競争力は低下してしまうだろう。

日銀の利上げで「トクする人」と「ソンする人」の決定的な違い
日銀が政策金利を30年ぶりの水準に引き上げた。経済全体で見ると、住宅ローンを抱える30~50代の現役世代は、負担が増える可能性が高い。それに対して、預金などの金融資産の蓄積の大きい60代以降の世代は負担が減ることも考えられる。他方で気がかりなのは物価高と円安だ。高市政権下、国債費は初の30兆円になる見通し。財政の一段の悪化、円安がさらに進行する懸念もある。

TSMC熊本第1工場は“失敗”だったのか?第2建設「中断」報道に見る困惑と期待
半導体の台湾TSMC熊本第2工場の工事が「中断している」と指摘され始めた。第1工場が期待されたほどの成果を上げていないこともあり、地元では不安や困惑が広がっている。一方、「悪い話ではない」という声も。当初計画よりも「先端品」を製造するための“良い”見直しであれば、期待は一気に高まるだろう。公式発表が待たれる中、TSMC熊本の重要性、その成否が北海道に工場建設中の日の丸半導体・ラピダスをも左右する事情を探る。

ChatGPT「非常事態宣言」でサム・アルトマンが焦るGoogleだけじゃない〈敵〉の正体
「ChatGPT」を開発した米オープンAIのサム・アルトマンCEOが、社内に「非常事態」宣言を出した。AI分野で競合の追い上げに、大きな危機感を抱いているのだ。最大のライバルはグーグルだが、敵はそれだけではない。中国のアリババやディープシークが、政府から手厚いサポートを受けて急速に台頭している。オープンAIの独走はいつ崩れるのか?世界的な再編に発展すれば、AIに完全に出遅れた日本勢にもチャンスが訪れそうだ。

エヌビディア株も道連れ?ビットコイン急落が示す「米国経済の変調」と日本への飛び火
ビットコインなどの暗号資産、仮想通貨市場が非常に不透明になっている。「リセッション(景気後退)が目前に迫っているかのような動き」と報じるメディアもある一方で、「2026年前半に急騰するだろう」という専門家もいて先行きが見通せない。ビットコインの行方を正しく予測するには、何が欠かせないのか。

中国が21兆円ファンド!グーグル・テスラものめり込む「AIの次」、2026年の主役とは?
2025年もあと1カ月と少し。そこで今回は、26年の世界経済の「主役」を大胆に予測しよう。スマホではなく、AI(人工知能)だけでもない。中国政府が約21兆円規模で支援する分野であり、米国ではオープンAIやグーグル、メタ、テスラなどのビッグテックが開発を急いでいる。日本では孫正義氏率いるソフトバンクグループが投資に熱心だ。世界のIT大手がのめり込む「AIの次」の事業とは?
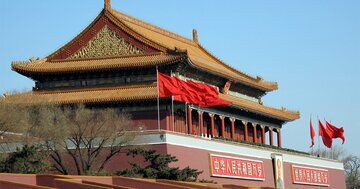
「鬼滅の刃」と“リストラ”で最終利益は1兆円超!絶好調のソニーが次に変革する2事業とは?
ソニーグループが映画『鬼滅の刃』のヒットや円安もあって業績好調だ。2012年以降3人のトップがリストラを断行し、新しいビジネスモデルにリソースを再配置したことが奏功している。次にソニーが改革の焦点にしそうな分野は何か。ずばり、2つあるだろう。自己変革の手を緩めてはならない。
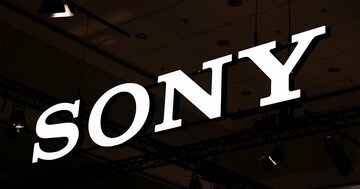
トヨタも恐れる「半導体ネクスペリア問題」…その裏で中国が着実に進めていた“国家戦略”とは?
トランプ関税に続いて「半導体ネクスペリア問題」が日本を直撃している。ホンダは米国とメキシコ、カナダで減産に追い込まれた。経営再建中の日産は、国内の追浜工場と九州工場で減産。26年3月期の売上高を下方修正した際、同問題の影響を織り込んだという。トヨタは決算会見で「リスクはある。代替品がどういうものが使えるのか、影響を注視している」とコメント。スズキも同問題を受けて通期の業績予想を据え置いた。ただし、悪影響は自動車業界にとどまらない。回り回って物価高となり私たちの生活にも直撃するリスクがある。

エヌビディアもファーウェイもソフトバンクも…世界のIT大手がのめり込む「AIの次」の事業とは
日経平均株価が最高値を更新し初の5万2000円台に突入した。米IT大手アップルの決算が好調で、ハイテク企業への注目が背景にある。世界のIT大手が今、開発を競うのが「ロボット」だ。AI分野は、推論モデルから「フィジカルAI」開発にシフトし始めた。ヒト型ロボットの実装化は、私たちの労働や生活にどんな影響をもたらすのか。映画『ターミネーター』のように人類滅亡の危機はないのか。期待とリスクが交錯するロボット開発競争の行方とは。
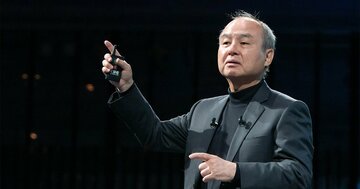
減税→経済成長→財政健全化?世界の潮流に逆行する高市内閣が目をそらす「社会保障改革の核心」
高市早苗首相の経済政策「サナエノミクス」がフォーカスされる一方、年金や医療、介護保険などの社会保障制度を見直す「国民会議」にも注目すべきだ。現行制度は、基本的に人口増加を前提に設計し運営している。この前提が狂い始めているため、可能な限り公平に、持続可能な制度へ変革しなければいけない。痛みを伴う改革でカギを握るのが、消費税率の引き上げだ。

アサヒもアスクルも無印良品も…なぜサイバー攻撃が増えたのか、IT効率化の「大きな弊害」とは
「スーパードライ」が出荷できなくなったアサヒビールに続いて、通販大手「アスクル」や「ロハコ」もサイバー攻撃を受けた。この影響で人気ブランド「無印良品」のネットストアも一時停止中だ。なぜ世界でサイバー攻撃が増えているのか。ITによる効率化の「大きな弊害」を探る。ネットの寸断が生活に深刻な影響をもたらす今、アサヒの事例は決して他の企業にとって他人事ではない。

身勝手すぎないか?トランプ大統領がTikTok規制法を覆した「まさかの理由」
「ノーベル平和賞を受賞したい」旨をSNSでも発信し続けているトランプ米大統領。彼にとってSNSは欠かせないツールだ。アカウントのフォロワー数が300万人超の「TikTok」も例外ではない。中国への情報漏えいリスクから、バイデン前政権はTikTok規制法を成立させたが、トランプ氏は覆してしまった。オラクル中心の米企業連合がTikTokの米国事業を約2兆円規模で買収する見込みだが、米中対立の火種は依然として残ったままだ。

残念ですが、移民なしで日本経済は回りません…「自国にプラスになる外国人」を受け入れて人口を増やした国とは?
「日本人ファースト」に端を発して議論が過熱している外国人労働者の受け入れ問題。日本が海外の移民政策から学ぶことは多い。ドイツは移民の誘致と同時に、解雇に関する規制緩和など一大改革を行い、経済成長率を高めた。スウェーデンは2024年、約500万円を支払う代わりに社会になじめなかった外国人に帰国を求めた。シンガポールは、「自国にプラスになる外国人」の受け入れを明示。社会に順応できる移民を選別し、慎重に管理する方針だ。日本は外国人をどのように受け入れ、社会と経済の活力向上につなげればいいのか。
