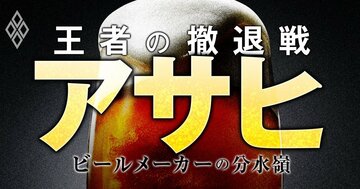インフレ連動債の利回りが急低下し、ここ数日に金価格が過去最高値を更新する一因となる中、投資家は再び実質金利を意識している。だが、大幅なマイナスの実質金利の影響は、貴金属だけにとどまらない。実質金利は通常、予想物価上昇率を差し引いた安全資産の国債のリターンと定義される。金融史学者のエルロイ・ディムソン氏は、実質金利と株価リターンに関連性があると指摘している。マイナスの実質金利は20世紀の大部分、さらに18、19世紀でも現実に見られた。株式投資家にとって、こうした指摘は良からぬ知らせだ。実質金利がとりわけ低い期間の後には、株式市場の平均パフォーマンスが目立って悪い時期が続いた。ディムソン氏によると、歴史に照らせば、保有資産の60%が株式、40%が債券となっている投資家は、向こう数年の実質リターンが2%程度になるかもしれない。実質金利が低迷、もしくはマイナス圏にあった特筆すべき例は1910年代だが、第1次世界大戦の期間中のみならず、開戦前からそうだった。また、1970年代も典型例だ。
超低金利の歴史、投資家に何を語るのか
有料会員限定
記事をクリップ
URLをコピー
記事を印刷
Xでシェア
Facebookでシェア
はてなブックマークでシェア
LINEでシェア
noteでシェア
関連記事
あなたにおすすめ