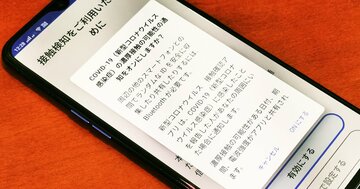9月に入り新規感染者の数が落ち着いてきた様子だ。コロナ感染のピークが過ぎたというのは、本当だろうか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
9月に入り新規感染者の数が落ち着いてきた様子だ。コロナ感染のピークが過ぎたというのは、本当だろうか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
落ち着きつつある新規感染者数
「ピークは過ぎた」は本当か?
7月から8月にかけて広がった新型コロナの第2波ですが、9月に入り新規感染者の数が落ち着いてきた様子です。「東京では2カ月ぶりに低い水準となった」というテレビのニュースを目にするたびに、一般市民として気になることは、「本当にピークが過ぎたのか?」ということです。
私は経営戦略コンサルタントであって、医学の専門家ではありません。しかし、実は私の専門分野で使われている問題解決スキルは、新型コロナ問題とは結構相性がいいのです。私以外の戦略コンサルタントがコロナに関していろいろ発言しているのも、同様の理由です。
今回はそのスキルの話を通じて、新型コロナのピークが過ぎたのは本当なのかについて考えてみたいと思います。
この先しばらくの間、新型コロナではなくコンサルのスキルに関する話になります。結論を急ぐ方のために先に申し上げておけば、コンサル流の推論から導かれる結論は、「第2波のピークは過ぎたが、11月頃までに次の第3波が来るだろう」というものです。あくまで論理的推論に基づいた予言ではありますが――。
さて、本筋の話を始めます。経営コンサルティングという仕事には、大きく分けて2つの種類があって、1つはわかっている経営理論に沿って経営指導をする仕事、そしてもう1つが、よくわかっていない新しい現象を解明して経営指南をする仕事です。ざっくりいえば、国内資本や銀行系のコンサルティング会社は前者、外資の戦略コンサルティング会社は後者を得意としています。
私は後者で育った人種なので、どちらかといえば、まだよくわらかない社会現象を解明する仕事のほうが得意です。その際、私たちが使うスキルは「仮説推論」という手法です。仮説推論というのは演繹法、帰納法と並ぶ3番目の論理的推論法で、主に新しい現象を解明する際の武器になります。新型コロナを例にとって、これらの3つの論理推論法について説明しましょう。