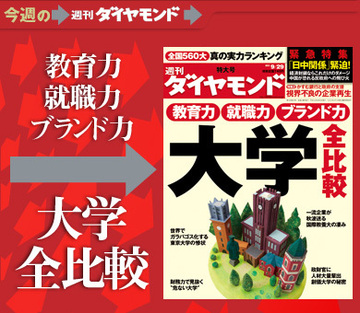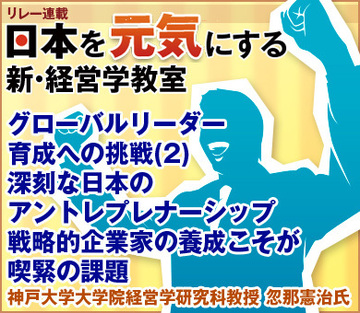新事業創造において、大学とはどのような存在なのだろうか。大学はコミュニティそのものであり、さらに特別な存在である。シリコンバレーでも大学、とりわけスタンフォード大学とカリフォルニア大学バークレー校は、何ものにも代え難い大きな存在だという点に異論をはさむ人は皆無だろう。
シリコンバレー発祥の地はヒューレット・パッカードが産まれたガレージ(史跡認定もされている)だ。このガレージにまつわるヒューレット・パッカード誕生の歴史も、スタンフォード大学のフレデリック・ターマン教授抜きには語れない。
起業家や起業を目指す者にとって大学は、研究室での研究開発や普段の講義を通して応援してくれる教授や同級生、卒業生などがいて、他にもさまざまな要素が組み合わさっており、それは他にはないスゴイ場所なのだ。
しかし、勝手に大学が何かしてくれるかというと、そういうわけではない。大学に入れば何とかなる、大学が色々とやってくれる、と思うのは間違いだ。
一方、結果的に大学をずいぶん活かしている例がある。いわば、自らインキュベートする、あるいは互いにインキュベートし合うために、大学に自然に溶け込み、活動している人たちだ。
今回は、そんな例を通して、大学にいるとき、卒業してから、大学とはどのような存在で、どういう意味を持つのか考えてみよう。
60歳の学生起業家は
大学を楽しみフル活用
 やぎゅう・よしひこ/小豆島ヘルシーランド株式会社・代表取締役会長。NPO法人オリーヴ生活文化研究所 理事長、社会福祉法人聖愛財団 監事、NPO法人アートビオトープ 理事。
やぎゅう・よしひこ/小豆島ヘルシーランド株式会社・代表取締役会長。NPO法人オリーヴ生活文化研究所 理事長、社会福祉法人聖愛財団 監事、NPO法人アートビオトープ 理事。
筆者は多摩大学大学院経営情報学研究科で客員教授を務めている。具体的には、品川駅そばの社会人向けMBAプログラム(夜学)で「実践アントレプレナーシップ」を担当している。卒業生には実際に起業した人や大企業で社内新事業を提案した人もいる。
実学を志向した内容であり、多様な受講者が集まっている。その中から、オモロイ方を紹介したい。香川県小豆郡の小豆島ヘルシーランド株式会社の代表取締役会長で60歳を数える柳生好彦氏だ。