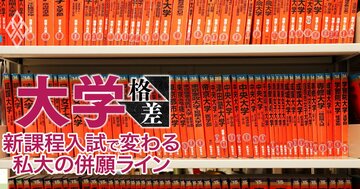Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
関西で中堅大学が受験者を集めている「年内学力入試」は、一般選抜の入試偏差値と比べてどれほどの難易度なのか。連載『教育・受験 最前線』では、連載内特集『大学入試2026』を10回以上にわたってお届けする。第8回は関西の私立22大学の44年間の偏差値推移データを一挙掲載するとともに、年内学力入試の難易度について実態を探る。(ダイヤモンド編集部副編集長 臼井真粧美)
首都圏の「年内学力入試」騒動
関西に飛び火して「大変」
「関西が飛び火をくらって、もう大変」。進学塾の阪神進学アカデミーで代表を務める松田元気氏によると、2026年度大学入試は昨年までとは勝手が異なる。11月に入った今、関西で「公募推薦(公募制の学校推薦型選抜)」と呼ばれる、年内に基礎学力テストを行う「年内学力入試」が出願と試験のヤマ場を迎えているところだ。
この公募推薦、関西では長年実施されてきたものだ。ところが昨年に首都圏で東洋大学が導入すると、文部科学省が「学力試験の入試は2月以降」というルールに違反していると指摘。首都圏の高校にはなじみのない方式であり、反発が出たのだ(『東洋大が2年目の「年内学力入試」で新配点を導入…「基礎学力テスト200点、小論文10点」の落とし穴【首都圏39私大44年間の偏差値推移】』参照)。
結局、面接や小論文などを組み合わせて評価することを条件に、年内に学力試験を行うことが容認された。これを受けて、関西の大学も事前提出の小論文などを新たに課すようになり、小論文のお題である志望理由を用意しなければいけなくなり、受験生も添削などでサポートする塾や高校の教員も負担が増えたというわけだ。
関西の難関私立大学群「関関同立」(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)で学力試験といえば、年明けの一般選抜に限られる。対して、中堅私立大学群である「産近甲龍」(京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学)や「摂神追桃」(摂南大学、神戸学院大学、追手門学院大学、桃山学院大学)、その下位にあたる大学は、年内学力入試を導入している。
年明けの一般選抜で国公立大学や関関同立を目指す受験生は滑り止めを確保するため、中堅以下の私立大学を目指す学生は試験内容が基礎学力の範囲であることに加えて年内に合否の決着をつけられるため、年内学力入試を受験。幅広い層にリーチできる産近甲龍などは受験者数も増えている。
この学力入試、関関同立に合格できるレベルの受験生でも、不合格になることが珍しくない。一般選抜の入試偏差値と比べてどれほどの難易度なのか。次ページでは、関関同立や産近甲龍、摂神追桃など関西の私立22大学の44年間の偏差値推移データ(一般選抜)を一挙掲載するとともに、年内学力入試の難易度について実態を探る。