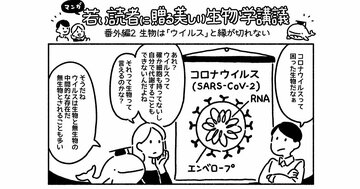ノーベル生理学・医学賞を受賞した生物学者ポール・ナースの初の著書『WHAT IS LIFE? (ホワット・イズ・ライフ?)生命とは何か』が世界各国で話題沸騰となっており、いよいよ3月9日に日本でも発刊される。
ポール・ナースが、生物学について真剣に考え始めたきっかけは一羽の蝶だった。12歳か13歳のある春の日、ひらひらと庭の垣根を飛び越えた黄色い蝶の、複雑で、完璧に作られた姿を見て、著者は思った。生きているっていったいどういうことだろう? 生命って、なんなのだろう?
著者は旺盛な好奇心から生物の世界にのめり込み、生物学分野の最前線に立った。本書ではその経験をもとに、生物学の5つの重要な考え方をとりあげながら、生命の仕組みについての、はっきりとした見通しを、語りかけるようなやさしい文章で提示する。
養老孟司氏「生命とは何か。この疑問はだれでも一度は感じたことがあろう。本書は現代生物学の知見を十分に踏まえたうえで、その疑問に答えようとする。現代生物学の入門書、教科書としても使えると思う。」、池谷裕二氏「著名なノーベル賞学者が初めて著した本。それだけで瞠目すべきだが、初心者から専門家まで読者の間口が広く、期待をはるかに超える充実度だ。誠実にして大胆な生物学譚は、この歴史の中核を担った当事者にしか書けまい。」、更科功氏「近代科学四百年の集大成、時代の向こう側まで色褪せない新しい生命論だ。」、さらには、ブライアン・コックス(素粒子物理学者 マンチェスター大学教授)、シッダールタ・ムカジー(医師、がん研究者 コロンビア大学准教授)、アリス・ロバーツ(人類学者 バーミンガム大学教授)など、世界の第一人者から絶賛されている。
本書の発刊を記念して、ベストセラーサイエンス作家であり、本書の訳者である竹内薫氏の「訳者あとがき」を特別に公開する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ノーベル賞学者の少年時代
ポール・ナースは生物学の世界における巨人である。二〇〇一年にノーベル生理学・医学賞も受賞している。でも、日本の一般読者には、もしかしたら馴染みが薄い人かもしれない。
ノーベル賞の公式サイトに英文でご本人が短い伝記を載せているので、その内容に沿って、ポール・ナースの人となりをご紹介しておこう。
本書の内容とも一部かぶるが、イギリスの片田舎ノーフォークで、ポール少年は伸び伸びと育った。小学校が家から遠く、長時間の通学の途中で寄り道をしながら、生き物(主に昆虫)に親しんだのだという。
父親は便利屋(家の修理などを請け負う仕事)と運転手をしていた。母親は料理人だった。階級制度が根強く残るイギリスではあるが、両親ともにポール少年をかわいがり、勉学の環境を整えてくれた。
一九三〇年代の大不況で一家はロンドン近郊に引っ越し、父親は缶詰工場で機械工として働き、母親は家事をしながらパートの清掃員をしていた。このころ、公園の樹木を観察していて、日向よりも日陰の葉っぱの方が大きいことに気づいたり、旧ソ連が打ち上げた人工衛星スプートニク二号(犬のライカが乗っていた)に驚いたりしたことが、小学校時代の想い出だそうだ。うーん、さすが、栴檀(せんだん)は双葉より芳(かんば)しといった幼少時代ですね。
中学高校は、テストが多く、裕福な家庭の子弟が多かったことで、あまり居心地がよくなかったらしいが、生物学のよい先生に巡り会い、山歩きや飛行機の操縦法を学び、生涯の趣味になったようだ。クラシック飛行機を自在に操って空を駆ける科学者って、なんだか素敵ですよね。
本書にもエピソードが登場するが、このころ、ポール・ナースは信心深いバプテスト派のキリスト教徒であることをやめてしまう。学校で進化論を学び、聖書の解釈に悩み、牧師に相談したけれど一蹴されたのだという。日本のような八百万の神=アニミズム、そこに仏教などが混在した多様な宗教風土と異なり、一神教の国では、科学を志す人間は、宗教を乗り越えて科学を「選ぶ」ことを迫られる。
その後、フランス語の試験で落第を繰り返したために、大学に入学できず、醸造所のラボで技官として働いた経験なども、ふりかえってみれば、建設的な道草であり、少年時代の通学路のようなものだったのだろう。