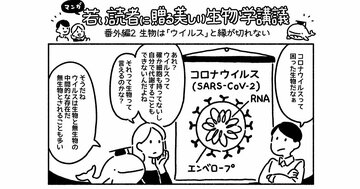転職を繰り返す
その後の人生については、とにかく「転職」が多いことがあげられる。もともと、一つの大学や研究機関にずっと居続けることは、欧米ではきわめて珍しい。あえて、居心地のよかったエジンバラ大学を去り、サセックス大学、さらには王立がん研究所、オックスフォード大学、ふたたび王立がん研究所といった具合だ。
繰り返しになるが、ポール・ナースは、典型的なイギリスの知識階級出身ではない。いわゆるオックスブリッジ型の裕福だったり貴族階級に属したりする人間ではないのだ。だから、オックスフォード時代について、ご本人は、控えめではあるが、大所帯の運営や資金の問題ばかりに時間を取られ、研究に集中できなくなったとぼやいている。
そのせいか、あっさりとオックスフォード大学を去り、古巣の王立がん研究所に戻っている。学生生活と研究生活の大半をオックスブリッジ以外の場所で過ごしたという意味でも、彼がイギリスの科学サークル内で異端の存在であることがうかがえる。
妻アニーとの結婚生活は円満で、二人の娘がいて、それぞれ、テレビのプロデューサーと素粒子物理学者として活躍している。妻とは大学時代に知り合ったそうだが、妻の影響で、かつての科学少年・昆虫少年は、音楽、絵画といった芸術方面にも興味の範囲を広げていった。
さて、ここら辺でポール・ナースの半生から、肝心の科学業績に話題を切り替えよう。
本書のいたるところで語られているように、彼は「生殖」と細胞レベルの「分裂」を生命の本質と捉えており、そのメカニズムの解明に生涯をかけた。彼がcdc2と名づけた遺伝子の情報(=コード)がタンパク質キナーゼという酵素を作る。この酵素は、サイクリンというタンパク質と一緒になって、細胞周期を進行させるのだ。
こうやって教科書風にまとめてしまうと味気ないが、分裂酵母という、ビールを作ってくれるちっちゃな生き物の細胞周期の仕組みが、人間も含めた「生き物」すべてに共通しているというのは、ほとんどありえないことのように思われる。
逆に、生き物が増える仕組みが、あらゆる生き物で同じだということから、本書の二四五ページでポール・ナースが述べているように、現在の地球上の生き物の誕生は、三五億年の歴史の中でたった一回だけ起きた奇跡であり、すべての生き物は、われわれと親戚関係にあることになる。
これほど壮大な物語はないだろう。
私はよく思うのだが、教科書風のまとめなんぞ、どうでもいい。大切なのは、こういった驚くべき発見をした本人による「生の物語」を読んだり聴いたりすることだ。そこにこそ、科学という営みの本質が隠れている。
この壮大な物語こそが、若きポール少年が葛藤の末に捨てた聖書に代わるものであり、現時点における人類の知の到達点なのだ。ただし、ポール・ナースの立場は神の存在は証明できず、知ることが不可能だという不可知論であり、単純に神を否定しているわけではない(きわめて科学的な態度だと感じる)。
本書を翻訳していて感じたことを書きたいと思う。
驚いたのは、この本がポール・ナースにとって初めての「本」の出版だということ。これだけ科学的な実績があり、二〇〇一年にノーベル賞を受賞しているのだから、何冊も本を書いていても不思議ではないが、ロックフェラー大学学長、王立協会(ロイヤル・ソサエティ)会長といった要職で忙しく、一般向けの本を書く暇がなかったのかもしれない。
では、なぜ今、このような一般向け科学書を彼は書いたのか。
この本の随所で、彼は、現代社会の危機に言及している。新型コロナ禍において、おそらく母国イギリスと超大国アメリカの指導者が、科学を軽んじてしまったこともやんわりと揶揄している(名指しで批判しないところがイギリス紳士らしい)。
ワクチンの問題にしても、副反応があることは事実だが、人口の六割から七割が接種しない限り、新型コロナ禍は収束しない。それも数学的かつ医学的な事実だ。
私は文系だから科学なんぞ知らなくていい。私は経済人だから、私は政治家だから科学はいらない。そう考える人が多ければ、人類は、ウイルスとの戦いで劣勢に立たされてしまう。
新型コロナだけではない。人種やジェンダーで人を差別したり、地球温暖化を否定したり、科学を学ばないことによる弊害はきわめて大きい。
これは私の推論にすぎないが、ポール・ナースは、次の世代のため、人類が悲惨な状態に陥らないために、生涯で一冊の一般向け科学書を書いたのではないか。この本はまさに、細胞周期の司会進行役を務めるタンパク質キナーゼと同様、新たな世代への橋渡しの役割を担っている。
私は数々の科学書を翻訳してきたが、これだけ心を打たれた本は、初めてだ。それほど、ポール・ナースという科学者の家族、友人、先輩、同僚、部下、人類、そして生き物への愛情を感じた。