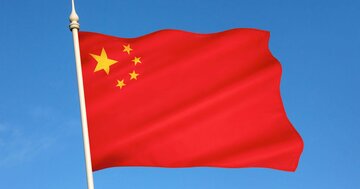近くて遠い、国後島を望む Photo:PIXTA
近くて遠い、国後島を望む Photo:PIXTA
今、世界は対立や紛争にあふれている。米中の覇権争い、中東での内戦や衝突、ミャンマーにアフガニスタン、そして友好とは言い難い近隣国に囲まれた日本の緊張など、キナ臭さは高まる一方だ。この緊迫した世界情勢を解説した新刊書『世界の紛争地図 すごい読み方』からの一部抜粋で、世界各地の対立と紛争の背景をわかりやすくコンパクトに伝えていく。今回は、日本が抱える北の国境問題、北方領土返還への遠い道のりについて解説する。
ソ連は「日ソ共同宣言」で
二島返還に同意したものの…
日本が周辺国との間に抱えている領土問題は、尖閣諸島、竹島に加えてもうひとつある。北方領土問題だ。
北方領土とは、北海道根室半島沖に位置する歯舞諸島・色丹島・国後島・択捉島の四島を指す。第二次世界大戦前には四島に1万7000人あまりの日本人が住んでいたが、終戦間際のどさくさにまぎれて侵攻してきたソ連軍に占領されてしまった。日本人は1949年頃までに追い出され、ソ連が実効支配を固めた。それ以来、四島はソ連の支配下に置かれ続け、現在はロシアが支配を継続している。
日本は四島の返還を求めているが、ロシアは聞く耳をもたず、解決への道はいまだ定まっていない。長年にわたり日本とロシアの間に立ちはだかってきたこの問題を「北方領土問題」というのである。