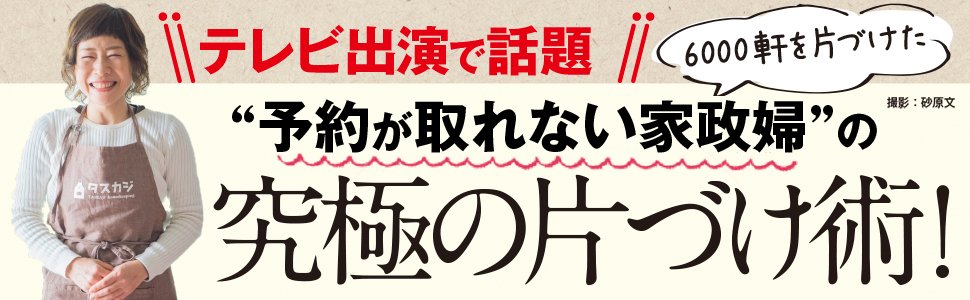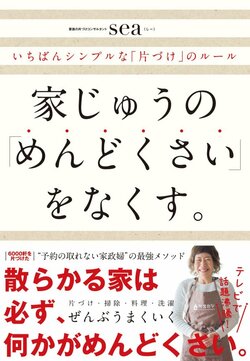20年以上にわたり、のべ6000軒以上の家を片づけてきた「片づけのプロ」、seaさん。家事代行マッチングサービス「タスカジ」では口コミで人気に火がつき、「予約の取れない家政婦」と呼ばれている。テレビ「セブンルール」にも出演するなど、話題に事欠かない。
そんなseaさんの片づけ術の集大成が、新刊『家じゅうの「めんどくさい」をなくす。ーーいちばんシンプルな「片づけ」のルール』だ。この連載では、本書より一部を特別に抜粋・編集して公開する。
じつは1月から3月は、片づけの依頼が多いシーズンなのだという。「大掃除で片づけたのに、あっという間に散らかってしまった」「このままでは新年度を迎えられない!」という人からの依頼が増えるためだ。
本記事では、片づけられない人が見落としている「あること」を明らかにし、本書の片づけ術の一部を公開する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
片づけられない人は「自分のモノ」を把握できていない
片づけの最中、引き出しの奥から存在を忘れ去っていた服や化粧品が出てきたり、あちこちから電池や付箋が発掘されたりしたことはありませんか? 私の経験では、9割の家で「ここにあったのか!」というモノが発見されます。自分が持っているモノって、想像以上に把握できていないものです。
残念なことに、把握できていないモノがたくさんある場所は、片づきません。そういう使わないモノに収納が占領されていると、肝心の「使うモノ」の場所が圧迫され、使い終わったモノが戻せなくなるからです。
そのため、片づけにおいては何より自分の持っているモノを把握する必要があります。片づける場所のモノをいったんすべて出し、「分類」するのです。片づけでは、この「分ける」作業がとても重要です。
片づけは「使うモノ」を選ぶことから始まる
「分ける」作業の最重要ミッションは、大量のモノのなかから「使うモノ」を選ぶことです。いざ片づけを開始すると、モノの量に圧倒されてしまうかもしれません。
でも、ここで混乱して作業に時間がかかってしまうと、疲れて片づけを完走できなくなってしまいます。『家じゅうの「めんどくさい」をなくす。』では、負担を最小限に抑えつつ、最速で大量のモノを分ける技術をまとめました。
分ける作業の進め方
① 収納からすべてのモノを出す
まずは、「片づける」と決めたエリアのモノを全部出します。
このとき、必ず広いスペースを確保してからモノを出し始めてください。スペースに気を遣っていると、思う存分作業ができなくて効率が落ちます。床やベッドの上を大きく空けましょう。
収納の中に入っているモノも、すべて出してください。「ここに入れたモノはわかってるから大丈夫」という聖域をつくってはダメですよ。
収納された状態で判断しようとすると、モノの状態がよくわかりませんし、収納のすみに埋もれているモノを見落としがちです。収納から出すと、ひとつひとつのモノの状態とトータルの量がありありと見てとれます。
洋服なら「あ、これ変色してる」「こっちは傷んでいるな」と気づいたり、タイツや靴下なら「毛玉だらけだ」「左右そろってないものがこんなにあったのか」とそこで初めて気づきます。収納の下のほうに埋もれていたタイツやストッキングの買い置きが出てくる、なんてこともよくあります。
② 「粗い山」をつくる
収納から出したモノは、出したその手でカテゴリ別の粗い山に分けます。
「出しながら分ける」と言うと身構えてしまうかもしれませんが、難しいことはありません。洋服ならトップスの山/ボトムスの山/アウターの山くらいの粗さでまとめるだけ。もともと収納には同じカテゴリのモノが固まっていることが多いので、そのまとまりを崩さずに出すのが基本です。
同じカテゴリのモノが数箇所に散っている場合は、「集合!」と号令をかけるつもりで、1箇所に集めます。Tシャツやジャケットが寝室や物置部屋にもあるのなら、それらも集合させてください。
モノを出して床が埋まってくると、量の多さに圧倒されて「ああ、大変なことを始めてしまった……」と不安になる方もいるでしょう。でも大丈夫、モノはちゃんと収まります。
③ 使う/手放す/迷うに分ける
さて、ここからがいよいよ「分ける」作業の本番です。粗い山に分けたモノを、さらに、使う/手放す/迷う、の3つに分類していきます。
分ける基準はいたってシンプル。「使う」か「使わない」かです。
【使うモノ】
これからの生活で使うモノ・使う予定があるモノはすべて「使うモノ」に分けてください。片づけでいちばん大事なのが、この「使うモノ」です。これらを優先してよい場所にしまっていけば、使い終わったモノがサッと戻せる「めんどくさくない家」になります。
「使うモノ」を選んでもらうとき、私は依頼者さまに「ないと困るモノはどれですか?」と聞くことが多いです。そうすると「使えなくはない」とか「いつか使うかも」といった使用の目途がたたないモノが除外され、「使うモノ」だけを選ぶことができます。
ここでネックになるのが「思い出の品」です。
思い出の品だけは、使う/使わないの基準で判断できません。もう役目は終えているけれど、「取っておくこと」自体に意味があるからです。ただ、古いモノすべてが思い出の品ではないはずです。この作業では「これは取っておきたい」と保管する価値を感じるモノだけを残しましょう。
たとえば、いろんな家で意外と出てくるのが「古い給与明細」。使うかどうかでいうと「使わないモノ」ですが、もし「仕事を頑張っていたときの大切な思い出」と感じるなら、残していいのです。
「思い出の品」はほかのすべてのモノと扱いが違うので、最後にしまいます。まとめて別の場所に置いておいてください。
【使わない→手放すモノ】
「使わないモノ」のなかで、明らかに不要だと判断できるモノは、この段階でゴミ袋に入れて手放しましょう。売ったり人にゆずったりして捨てる以外の手段で手放せそうなモノも、ここに分類します。
ここで無理をして、手放すモノを増やす必要はありません。それでも、同じジャンルのモノが一堂に会すると、明らかに汚れた服や、役目を終えた書類、インク切れのボールペンなど、限りなくゴミに近いモノ(あるいはゴミ)が続々と現れます。そういう「手放しても絶対後悔しないモノ」は、迷いなく捨てられるはずです。
また、「1箇所に集めてみたら大量にあった!」というモノもあるでしょう。タイツやストッキング、ホチキス、消しゴム、シャープペンの替え芯などなど……。細かいモノほど量が増えがちです。
この時点で「こんなにいっぱいあるなら、少し手放してもいいや」と思えたら、「手放すモノ」に分けましょう。
【使わない→迷うモノ】
「これは使わないけど、うーん、もったいないかな……」などと手放すのに抵抗を感じるなら、それ以上悩まず、「迷うモノ」に分類してください。
「いつか使いたいけど、具体的な予定はない」モノも、ここに分けます。大量にある同じような文具、着られるけどイマイチしっくりこない服などを見て、分ける手が一瞬でも止まったら「迷うモノ」に分けてOKです。
使わないモノだからといって、即捨てなくてもいいのが私のメソッドのポイントです。あえて曖昧な選択肢を用意することで、分ける作業の痛みを減らし、判断のスピードを早めています。
④ 最後に「迷うモノ」を見直す
「使う」「手放す」「迷う」の分類が終わったら、自分をほめてあげましょう。片づけが苦手な人ほど自分に厳しく、完璧じゃないかも……とくよくよしがち。分ける前の写真を残しておくと、見比べて自分の進歩を実感しやすいのでおすすめです。
さて、分け切った時点では、「迷うモノ」が大量にあるはずです。
でも、ここで「使うモノ」にもう一度目を向けてください。そこには、これからの自分の生活に必要なモノだけがまとまっていて「これだけあれば生活は回るな」という安心感がきっとあるはずです。
その頭でもう一度「迷うモノ」を見ていただきたいのです。「迷うモノ」だけを冷静に見ると、そのなかに優劣があることがわかってきます。たとえば「白いトップスが何枚もあるけど、これは古いし、こっちはデザインが若すぎる」というふうに。そう思うと、惜しまず手放せるモノもあるはずです。
おもしろいことに、「迷うモノ」は集めると手放しやすくなります。
着られるけど似合わない服や、使いにくい調理器具など、「イマイチなモノ」が塊になると、全体にどんよりした雰囲気が漂い、「手放したい」という気持ちが芽生えるからです。そう思えたら、この見直しの1ステップで、苦もなくモノの量を減らすことができます。
分類を終えたあとの「しまい方」については、『家じゅうの「めんどくさい」をなくす。』で詳しく説明しています。
考える時間は「5秒」まで
「分ける」作業は、とにかく手を止めないことを優先し、一気にリズムよく分けていくのがコツです。まずは「分け終わること」を直近のゴールにしてくださいね。
手を止めないためのルールとして、どこに分けるか考える時間は「5秒」までにしてください。
人の集中力はもって2時間くらい。短い人は30分でへとへとになってしまうこともあります。人間のエネルギーは有限で思っている以上に少ないので、「答えを出さないと先に進めない」と思っていると仕分けの段階でエネルギーを使い果たしてしまいます。
5秒考えて答えが出ないモノは、すべて「迷うモノ」です。あえて思考を停止させていいんです。捨てる・捨てない以外の、第3の選択肢を持つこと。これがとても重要です。
「考えるのは5秒まで」。このルールは絶対に守ってくださいね。