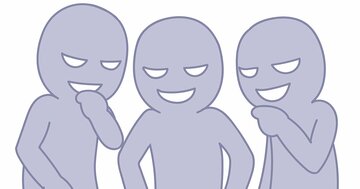母が遠くへ行ってしまうような焦燥感
合格発表日をきっかけに、母はどんどん変わっていきました。それまで感情の起伏が激しかったのが、他人にひどいことをされてもたいていのことでは怒らなくなり、毎日笑顔で幸せそうに過ごすようになり、きつめだった顔だちまで優しい磊落な印象に変わりました。
お母さんなんか変わったね、と私が言うと、母はこう言いました。
紗生が合格して、私、なんだか達観したみたい。紗生が本当に限界まで努力して、奇跡みたいに目標を達成して、もうこれ以上の幸せはない、って思った。本当に心から、神様と紗生に感謝しようと思った。ようやく自分に自信を持てるようになったの。ああ、生きててよかったなあ、と思った。それだけで十分。何も望まないよ。
もう人生に悔いはないかもしれない、なんて言う母にやめてよ、と冗談で言いながら私は、母に自信を持たせるという目標が叶ったのだと知りました。
けれど私は、母をこんなに喜ばせることができてよかった、ととても嬉しく思うのと同時に、どこか、母が遠くに行ってしまったような焦燥感に襲われていました。
ずっと一緒に同じ方向を向いてきた母が、私の教育が一段落したことで、新しく自分を見つめ直し、自分自身のための人生を生きようとしているような気が、なんとなくしていました。
そして、そういう直感というのはだいたい当たるものです。私が大学に入ってサークルやクラスの付き合いが増えて家にいる時間が少なくなったということもあり、毎日のようにおしゃべりしていた私と母のふたりの時間も、徐々になくなっていきました。それでもたまの母の休みにはふたりで飲みに行ったり、深夜におしゃべりしたりすることもありましたけれど。
母が第二の人生を歩もうとしているのは寂しくはありましたが、母と仲が良く、価値観も合い、話していてとても面白いことには変わりなかったので、このままの感じで私も大人になるのかな、と思っていました。
第二の転機は、私がアメリカに留学したことでした。
はじめて母と離れて暮らしました。遊ぶところも気晴らしをするところもないような、森と住宅地に囲まれた、本当に小さなキャンパスでした。授業に行き、課題をし、英語の勉強をするだけの生活が続きました。
そんな逃げ場のない環境で、私ははじめて挫折を味わいました。これまで抱いていた自分へのイメージや自信がもろくも崩れ去った瞬間でした。
私は思い上がっていたのです。川代紗生という人間は素晴らしい人間であり、自分こそが正義なのだと思い込んでいたのです。私は唯一無二の価値ある人間なのだと信じ切って、周囲の人間を見下していました。他人に対して失礼なことばかり考えていました。
けれどそんな素晴らしいはずの私は、母がいなければけっして成り立たないのだと、一人で暮らしてみてはじめて気がついたのです。母がいつも私を支えてくれ、私を認めてくれたからこそ、私は自信を持って日々生きていられたのだと。母がいなければ、私はちゃんと立つことすらできない。英語の勉強も頑張れないし、自信を持って国際交流することも、自分の意見をきちんと言うこともできないんだとようやく気がつきました。
自立しなければ、と思いました。
ひとりで生きられるようにならなければ、と。
小さな田舎町の寮の地下の部屋で、私は一人考えました。
そして、自伝を書くことにしました。私の人生に起こったことを、事細かに、すべて書き記しておこうと思いました。
どうしてわざわざ留学中に、なんて言われもしましたが、最後のチャンスだと思ったのです。今きちんと、自分を振り返ってみなければ、一生逃げ続けることになるだろうと思いました。嫌いな部分を直視し、認め、受け入れなければ、一生このままコンプレックスから目をそむけ、偽りの「川代紗生」のイメージだけを信じ続けるだろうと。忙しい日常に流されることのない今だからこそ、やらなければ、と思いました。
3ヶ月かかって、私はようやく、80ページにも及ぶ自伝を書き終えました。最後の言葉を書きつけたのは、帰国する飛行機の中、成田に着く一時間程前のことでした。苦しみ、悩み、私自身を殺したくなりながらも、私は本当の自分をようやく少しはわかったような気がしました。いいところも悪いところも、これでちょっとずつ受け入れられるようになる、と思いました。
それは母の支えなしで、やっと自分の力で勝ち取った、自信でした。
そして、私はひとつのとても重要な事実に気がつきました。
母は、絶対ではない、ということ。
私は母に愛されて育てられてきました。いつも母と一緒でした。母と同じ価値観を持ち、趣味を持ち、時間を持ちました。作家も、映画も、アーティストも、全部母と共有していました。母と一心同体でした。
それがよかったのです。母と一緒がよかったのです。自分に似ていて、自分を理解してくれる人がいつもそばにいてくれて、自分を大切にしてくれるというのは、本当に居心地がいいことです。それが幸せだと思っていました。母とずっと一緒がいい、一緒じゃなきゃだめだ、と思っていたのです。
自分の人生を振り返ってみて、そして、アメリカから日本に着き、久しぶりに母と話してみて、違和感を覚えました。はじめのうちは、帰国して少ししか時間が経っていないから、変な感じがするだけかもしれないと思いました。けれど、その直感は次第に、確信へと変わっていきました。
お母さんが言うことが必ずしも正しいとは限らないんだ。
留学する前は、母が言うことは全部正しいんだと思っていました。母の言うことは絶対なんだと思いました。母と自分の意見が異なるのはおかしいとすら思っていました。なぜなら、楽だったからです。頑張らなくてもよかったからです。母が頑張っているのを見ていれば、私は自分も頑張ったような気分に浸れました。母が苦労した経験から得た価値観を、そのまま受け売りして自分が思いついたことのように語っていました。
けれど、何度考えても、母の言うことに共感できないことも増えてきました。それまでは母の言うことなら無条件に信じていたのに、違和感を覚えるようになってきたのです。それは価値観だけでなく、趣味も同じことでした。音楽、本、映画の好みも共有していた私たちですが、だんだんと母が好きと言うものが必ずしも好きではなくなっていきました。
母が、このアーティストすごくいいの、感動するよ、と言っても、それまでは素直に聞いていたのが、なんだか共感できなくなってきました。
私は別に好きじゃない。
私はそれはおかしいと思う。
そうかな? そんなことないと思うけど。
母の言うことを否定することが増えました。
当然、母は不満そうでした。それまで同じ感覚で、なんでも共有できていたのが、否定されるようになったのですから、不機嫌になるのも無理はありません。母は、それならもういいよ、と言ったきりすすめてこなくなりましたが、それでも自分の好みや価値観を私に話してくることには変わりありませんでした。
私は次第に、母の言うことをはなから聞かなくなりました。母の言うことにはなんでも、「それは違うと思うけど」と言いたくなってきました。
あ、これが俗に言う反抗期というやつなのかと、私は22にもなってようやく知ったのです。
そのことに気がついたときはもちろん、動揺しました。どうしてここまで母に反抗したくなるのかわかりませんでしたが、とにかく母の言うことを聞きたくなくて、仕方なくなったのです。
母の話を聞くのが苦痛でした。何を聞いても、そんなことない、と言いたくなりました。私はお母さんのようには思わない、正しいのは私なの。そう主張したくなり、ろくに考えもせずに母を否定し、傷つけました。そんな自分ははじめてだったので、ネットで情報を集め、自分はいわゆる「第三次反抗期」という、成人したあとに親に反抗したくなる状況なのだと、どこか冷静に分析していました。ああ、ややこしいことになった、と思いました。
私がネットで記事を書き続け、小説家になることを夢見ていることを母は知っていました。私の記事もほぼ毎回読んでいます。けれど、母は私が文章を書くことに対し、はじめは応援してくれていたものの、私が小説を書き始めた頃から、だんだんあまりいい顔をしなくなりました。
母が私を心配しているのは明らかでした。私がこのまま会社員にならずに小説家を目指すと言いやしないか、心配しているのだろうと私は思いました。
母は自分が好きなことをやって失敗したから、私に同じような苦労をしてほしくないと思っているのだろうと思いました。だから、私が母の若い頃と同じように、夢を追いかけるのを見て、それを止めたくなったんだろうと。ちゃんと堅実な道を選んでほしいんじゃないか、と。
母が心配しているのをひしひしと感じ、それが苦痛で仕方ありませんでした。誰にも干渉してほしくありませんでした。縛られたくありませんでした。お願いだから好きなようにやらせてくれ、と思いました。
だから思い切って母に、私、社会人になったら、一人暮らしするから、と告げました。もう決めたこと、決定事項として。
しばらくの沈黙のあと、ずいぶんと思いやりが無いんだね、と母は言いました。母は怒っていました。
相談してくれるならまだしも、自分勝手だよね、と。
びっくりしました。まさかそんなに冷たく突き放されるとは思っていませんでした。
だって、私、自立したいんだもん、と母に訴えました。
一人暮らししないと自立できないの? 本当に自立しようと思ったら、今からだって、家にいたってできるんじゃないの? そういうのってさ、他力本願だよね。環境に任せて自立させてもらおうなんて、おかしいと思うけど。そんなの、本当の自立じゃないよね。ちゃんと自分の力で生きていけるようになりたいんだったら、せめて親である私をちゃんと安心させてからにしてよ。はっきり言って今の紗生見てて、一人で暮らしたからって自立できるようには到底思えないけど。それでも出て行きたいって言うなら、勝手に出てけば? 止めないから。
それほど厳しいことを言う母は、久しぶりでした。
母が、私がやりたいと言ったことに反対したのは、それがはじめてのことでした。
それからはますます、母に反抗する気持ちが強くなっていきました。母がよく思っていないのはわかっていましたが、それでも感情を抑えることができませんでした。
反抗期になるべきときに反抗しなかったんだから、別にこれくらいいいじゃん、反抗させてよ。
お母さんと違う道を選んで何が悪いの。
お母さんと違う意見を持って、何が悪いの。
お母さんと私は違う人間でしょ。
私とお母さんは、同じ人間じゃないの。
もう、ちゃんとべつべつの人間なんだよ。
ずっと同じ感覚でいる必要なんて、ないんだよ。
そう言いたい気持ちがぐつぐつと胸のなかで煮えたぎって、大きくなり、今にも爆発しそうでした。母と話すとひどいことを言ってしまいそうになったので、会わないように計算して帰ったりもしました。
そしてついに私は、一つの結論に至りました。
そうか、お母さんは、子育てがイコール自分のアイデンティティなんだ、と。
お母さんは、私が成功しないとだめなんだ。ちゃんとした道を選ばないとだめなんだ。自分の子育てが成功してないってことは、自分の人生がだめだって思っちゃうからだ。だから私に固執するんだ。
もう、縛られたくありませんでした。お願いだから私を解放して、と思いました。好きなようにやらせてくれ、と思いました。
第三次反抗期のことを書こう、と思ったのは、12月終わりのことでした。
口でうまく説明できない私は、文章にして母に伝えるしかないと思いました。
私はいつも、悩みは作文にして解決してきました。自伝のときだってそうです。書いている瞬間は苦しいけれど、すべてを書き終えてしまえば、私は違う視点でものごとを見られるようになっているからです。
この感情もぶつければ、すっきりするだろうと思いました。
けれど、何度パソコンに向かっても、進まない。
驚くくらい、書けませんでした。書いては消し、書いては消しをくりかえしました。
自分の想いを文章にして、母を説得したいと思いました。母を責めたかったのです。私がこうしてもやもやして自立できずにいるのは、母のせいだと思ってほしかった。申し訳ないと思ってほしかったんです。だから、作文を書いて、自分の想いをすべて書き連ねて、母に読んでもらおうと思っていました。
でもどんなに書こうと思っても書けません。
こんなにも感情があふれているのに、どうして書けないんだろうと思いました。
一文字も進まないまま年が明けました。