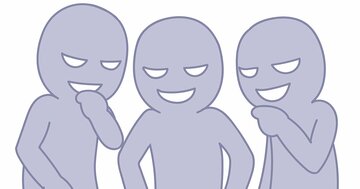SNSが誕生した時期に思春期を迎え、SNSの隆盛とともに青春時代を過ごし、そして就職して大人になった、いわゆる「ゆとり世代」。彼らにとって、ネット上で誰かから常に見られている、常に評価されているということは「常識」である。それ故、この世代にとって、「承認欲求」というのは極めて厄介な大問題であるという。それは日本だけの現象ではない。海外でもやはり、フェイスブックやインスタグラムで飾った自分を表現することに明け暮れ、そのプレッシャーから病んでしまっている若者が増殖しているという。初の著書である『私の居場所が見つからない。』(ダイヤモンド社)で承認欲求との8年に及ぶ闘いを描いた川代紗生さんもその一人だ。「承認欲求」とは果たして何なのか? 現代社会に蠢く新たな病について考察した当エッセイから、今回は、内容の一部を抜粋・編集して紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
やりたいことはなんでもやらせてくれた母
反抗期を経験したことは、ありますか?
私はありません。より正確に言えば、つい最近まで、ありませんでした。まったくと言っていいほど。中学二年の頃、ほとんどの友人が「親ウザイ」と言っていたときですら、私はうまく想像できませんでした。
というのは、私と母は昔からとても仲が良いのです。母は子育てにとても熱心な人で、私に並々ならぬ愛情を注いでくれました。私がやりたいと言ったことはなんでもやらせてくれました。借金をしてでも、休みなしで平日と土日、仕事を掛け持ちして働いてでも、母は私を優先してくれました。英会話、お絵かき教室、テニススクールなどの習い事にも通わせてくれましたし、私がほしがる本は全部買ってくれましたし、中学の頃、私が勉強を一切やらないで遊び呆けていたときも、勉強しろとは一切言わず、友達との時間を大切にしなさいと言いました。
「紗生がやりたいことを、全力でできるように」。母はいつもそう言っていました。だから私が何かをやりたいと言ったときには、反対することはありませんでした。私立の大学に行きたいと言ったときも、アメリカに留学したいと言ったときも。「お金が無いからだめ」などとは、一切言いませんでした。幼い頃からそうやってやりたいことは何でも挑戦させてもらえていた私は、それがどれだけお金のかかることなのかなんて、想像もしていなかったのです。母親という生き物は毎日朝から晩まで、家にはいないで働いているものだと思っていたし、祖母の家に預けられることや、自分で鍵を持ち歩いて一人で誰もいない家に帰ることは、至極当然のことだと思い込んでいたのです。
母がなぜそこまでして、私に「紗生はどうしたい?」「紗生が決めていいよ」と言ってくれたのかというと、母自身厳しい両親のもとで育てられた経験があり、子どものことを芯から理解してあげられる母親になりたい、という強い意志を持っていたからでした。母が幼い頃からしつけが厳しかった母の両親はもちろん、母のためを思ってやっていたことだったのですが、当人はむしろ、「親に自分のことを理解してほしい」というもやもやとした感情を長年くすぶらせることになってしまったのです。そのおかげで、わかってもらえないならいっそ、と自分の好きなことを追いかける道を選ぶようになりました。両親が好きだからこその、反発心でした。
結果として、母は両親の心配する視線も無視して、自分の夢を追いかけるようになりました。親がすすめようとする堅実な道ではなく、自分が大好きなことを全うする道を選んだのです。そして、母はその日その日を楽しく生きられればいいと思うようになりました。「今」その瞬間を、一瞬一瞬を楽しもう。それが自分の生き方だと信じていたのです。
けれど、そんな生活はそううまくはいきませんでした。
母は失敗しました。ちょうど結婚し、私が生まれようかという頃のことです。そのときそのときで何も考えずに感情にまかせ、やりたいことだけをやっていたせいで、母には人に認めてもらえるような知識や知恵や証明がなかったのです。母は路頭に迷うことになりました。幸せな生活から一転、なりふりかまわず、職を選ばず、とにかくがむしゃらに働かなくてはならなくなりました。好きな仕事じゃないからいや、なんて言ってはいられなくなったのです。そのときようやく母は、その場しのぎに自分の欲に従って生きるだけでは駄目なのだと気がつきました。母にとって、とても大きな挫折の瞬間でした。
なんとかして、生きていかなければならない。生きる。大切な、この子を守るために。
もしかすると、だから母は、私に紗生という名前をつけたのかもしれません。とにかくちゃんと生きてほしい、と思ったのかもしれません。
母は、私が生まれたとき、こう考えました。
この子には、自分のやりたいことをなんでもできるような環境を与えてあげたい。
今好きなことを精いっぱいやってほしいのはもちろんだけれど、もしいつか本当にやりたいことが見つかったとき、きちんとものごとを分別する力がなければ、私のように死に物ぐるいで働かなくてはならなくなる。
それならこの子の選択肢が増やせるように、ちゃんとした教育だけは、与えてあげたい。
いざというときに、自分の夢を、諦めなくてすむように。
そう思って、母はそれまで集中していた自分のやりたいことも何もかも捨て、私を育てることにだけ集中するようになりました。
私が将来、自分のような苦しみを味わわないために。
母は、教育書を何冊も読み漁り、様々な学者による教育論を調べつくし、何が最も私のためになるのかを考えて育てました。そして、私とじっくり話す時間を持つことを、ひとときも惜しみませんでした。どんなに仕事が忙しくても、疲れていても、母はマイナスな言葉は発しませんでした。もちろん人並みに落ち込んだり怒ったり、感情を高ぶらせることはありましたが、私と話すときは、いつも本当に面白がって私の話を聞いてくれました。私がもやもやした感情をくすぶらせているときは、すっきりするまでいつまでも待ちました。
寝る前にはいつも絵本を読み、シルバニアファミリーのドールハウスで一緒に遊び、そして裁縫が得意だった母は、何着も手作りのドレスを作ってくれました。どんなブランドの洋服よりも、母がパターンを引き、ユザワヤで布やボタンを選んで作ってくれたドレスがお気に入りでした。
私が高校生の頃に母の言っていたことが、今でもずっと心に強く残っていて、離れません。
紗生と話すのが、紗生と遊ぶのが、紗生を知っていくのが、楽しくて仕方なかった。子育てが本当に楽しかった。だって、私が紗生を育てている以上に、私も、紗生に成長させてもらってたんだよ。子育てって、本当にいろんな気付きがあって、面白いよ。だからいつも、紗生を尊敬して育ててた。親なのに子どもを尊敬するって、他人から見たらおかしいかもしれないけどさ。
いつも紗生と同じ年齢でいるようにしてたなあ。3歳のときは、私も3歳。12歳のときは、12歳。今、紗生は高校生だから、私も高校生。だから紗生が今好きな遊びもメイクもファッションも、面白いなあって思うよ。
紗生がこれから大学生になったら? うーん、どうだろうね? 私も大学生になるのかな。なりたいけど……きっとそのうち、私が追い付けないくらいに紗生は成長していくんだろうなあ。
そうしたら、もう紗生と一緒ではいられなくなるし、話も合わなくなっちゃうかもね。
どこか諦めたような目で言う母に、焦りを感じました。そんなことになるわけないよ、ずっと仲良し親子でしょ、とむきになって返したのを覚えています。
母の愛情をたっぷり浴びて育った私は、次第に母に恩返しをしたいと思うようになりました。
というのも、私が生まれた途端にひどく教育熱心になった母は、周囲から少し、醒めた目で見られているような気がしたのです。なんとなくですが、母のやり方は、世間からは認められないのかもしれないと思いました。だって、毎日暮らしていけるかもわからないときだってあったのに、自分の老後の蓄えや趣味なんかには投資せず、子どもの教育にお金をつぎこんでいたわけですから、他人から見れば、「見栄張っちゃって、そこまでして子どもをエリートにしたいなんて」と思われてもおかしくなかったのです。
私はなんとかして、母は素晴らしい人であると、みんなにわかってほしいと思うようになりました。母は人格者なのだと、証明したくなったのです。そして何より、母に喜んでほしいと思いました。母はそれだけ愛情にあふれているにもかかわらず、自分に自信がない人だったので、母に自信を持たせてあげたいと思いました。
そういうこともあって、私は難関の早稲田大学を受験することにしました。もちろん自分がその大学や学部にとても惹かれていたというのが一番の理由ですが、それと同じくらいに、母に恩返ししたいという気持ちが強かったのです。
学年でもビリをとるくらいにひどい成績だった私が、難関と呼ばれる大学に合格するような奇跡を起こせば、母は間違っていなかったのだと証明できるんじゃないか、と。
猛勉強の末、私は合格しました。
当然のことながら、母は喜びました。ふたりで抱き合って合格を祝いました。
それが転機でした。