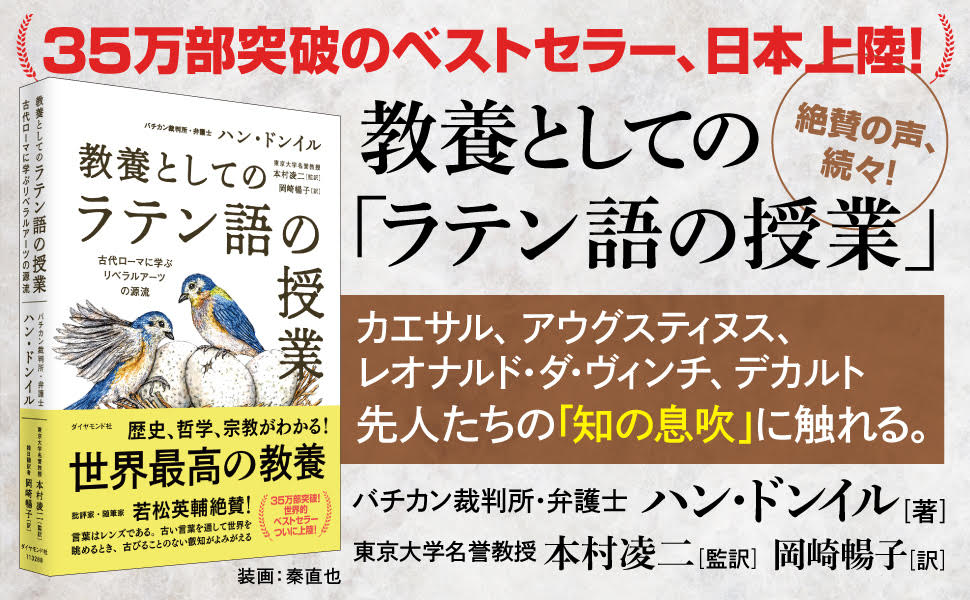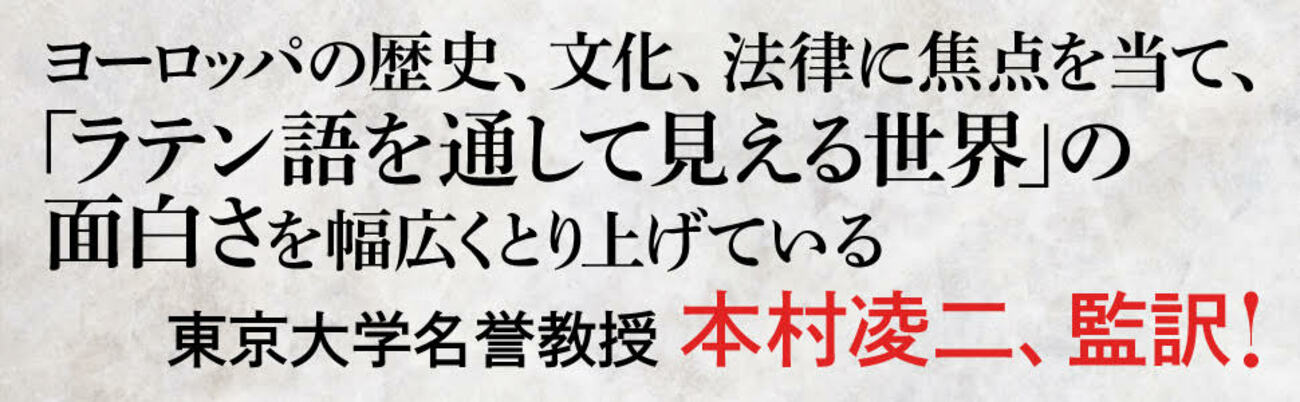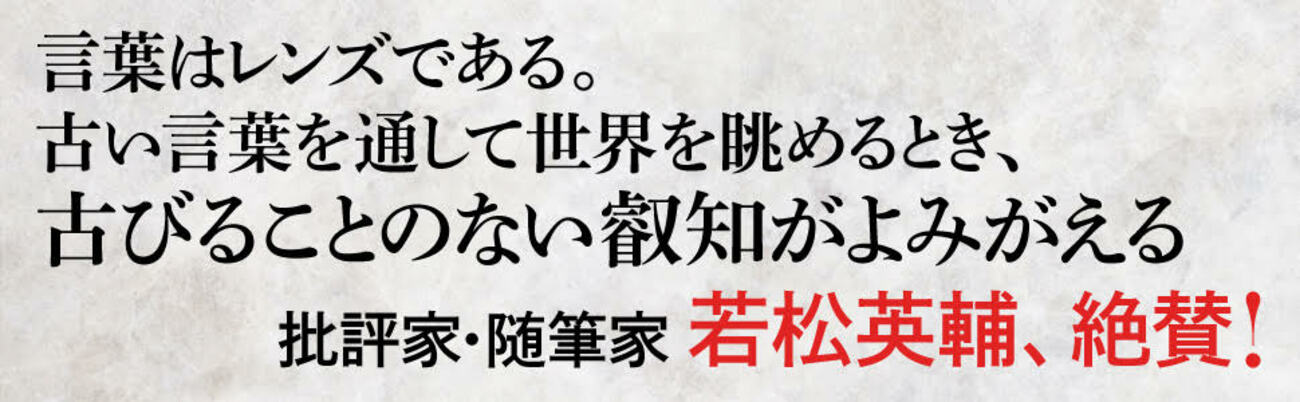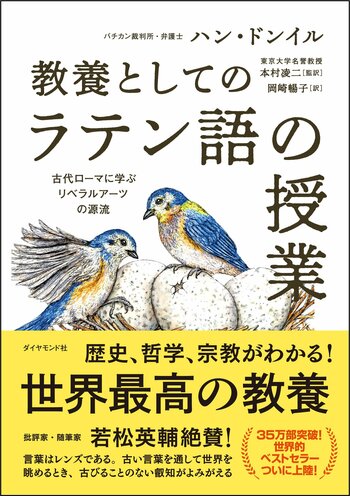ラテン語こそ世界最高の教養である――。東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏による「ラテン語の授業」が注目を集めている。同氏による世界的ベストセラー『教養としての「ラテン語の授業」――古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流』(ハン・ドンイル著、本村凌二監訳、岡崎暢子訳)は、ラテン語という古い言葉を通して、歴史、哲学、宗教、文化、芸術、経済のルーツを解き明かしている。韓国では100刷を超えるロングセラーとなっており、「世界を見る視野が広くなった」「思考がより深くなった」と絶賛の声が集まっている。本稿では、本書より内容の一部を特別に公開する。
ラテン語の名句に隠された意味とは?
Post coitum omne animal triste est.
ポスト・コイトゥム・オムネ・アニマル・トリステ・エスト
(すべての動物は性交後にゆううつになる)
※発音はローマ式発音(スコラ発音)を基準にしています。
この名句は、ギリシャ出身の医師・哲学者であるクラウディウス・ガレヌス(Claudius Galenus、129~199 ※201年や217年死亡説もあり)の言葉です。ガレヌスはローマ時代の剣闘士 gladiator の外傷治療専門医だったとも言われています。
そんな彼が残したこの一文は、法医学のみならず宗教学でも引用されるのですが、その意図は「大きく期待した瞬間が過ぎ去った後に、人は、自分の力ではどうにもできないもっと大きな何かを逃したような虚しさを感じるものだ」というものです。
これはつまり、たとえ愛する人がそばにいたとしても、個人的、社会的な自我が実現されていなければ、「人間は孤独で寂しく疎外された存在である」ということと、向き合わなければならないと解釈できます。
もっと言えば、人間は霊的な動物として、理性的人間 homo sapiens であると同時に宗教的人間 homo religiosus を目指すようになったということです。これは宗教的にこの名句を解釈したものです。
ある意味、人間は自らを人間と自覚して以来、神を崇拝し始めたのだと言えるでしょう。したがって、宗教とは、単に人間が強力な絶対者に従ったものではなく、その時代を支配していた冷酷な体制と不条理な価値観にあえぐ生活の中で、生きる意味と価値を再発見するための苦闘から始まったと言うこともできます。
すなわち、初期の人類は人生の価値と意味を、神的なものから“類推 analogia”しようとしていたのでしょう。神が人間を必要としたのではなく、人間が神を必要としたのです。ここで「作られた神」という概念が登場することになります。
Deus non indiget nostri, sed nos indigemus Dei.
デウス・ノン・インディチェット・ノストリ、セド・ノス・インディチェムス・デイ
(神が我々を必要としたのではなく、我々が神を必要とするのだ)
こうして始まった宗教は、王や皇帝が正しく神に由来するという支配階級の主張を正当化したのはもちろんのこと、民衆の日常のさまざまなことにも深く浸透していきました。
今日、この名句を私たちの日常に取り入れるなら「目標とした社会的地位や名声を追い求めた後に人間が感じる感情は、満足ではなくゆううつである」と解釈できます。
実際に、情熱的に望んだ瞬間が一気に過ぎ去ると、人間は虚無感を覚えるものです。ステージ上で喝采を浴びていた歌手が、帰宅して一人で家にいるときに感じる感情などまさにこれではないでしょうか。
私が法医学の授業を受けた際にも、この名句を引き合いに出しながら、芸能人が向精神薬に手を出してしまう環境について説明されたことがあります。
(本原稿は、ハン・ドンイル著『教養としての「ラテン語の授業」――古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流』を編集・抜粋したものです)
【編集部からのお知らせ】
『教養としての「ラテン語の授業」』とは?
本書は、東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士となったハン・ドンイル氏が行った「ラテン語の授業」を整理したものだ。
彼の授業は、単なる語学の授業ではなく、総合人文科学の授業に近い。西洋文明の源流ともいえるラテン語を通して、歴史、哲学、宗教、文化、芸術、経済など多くのことを学べる。
監訳を担当した東京大学名誉教授である本村凌二氏も「ヨーロッパ各国の歴史、文化、法律に焦点を当て、ラテン語を通して見える世界の面白さを幅広くとり上げている」とコメントしている。
読売新聞読書委員、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授などを歴任した若松英輔氏も「言葉はレンズである。古い言葉を通して世界を眺めるとき、古びることのない叡知がよみがえる」と絶賛している。
本書目次より
日本語版刊行に寄せて──叡知の貯蔵庫としてのラテン語
Lectio I 胸に秘めた偉大なる幼稚さ
――Magna puerilitas quae est in me
・ラテン語はなぜ難しいのか?
・レオナルド・ダ・ヴィンチがラテン語を猛勉強した理由
・「偉大なる幼稚さ」を大切に
Lectio II 最初の授業は休講します
――Prima schola alba est
・学問とは「人間と世界を見つめる枠組み」を作る作業
・ローマ人のシンプルな教育制度
・あなたの心の陽炎を見つめてください
Lectio III ラテン語の品格
――De Elegantiis Linguae Latinae
・「否定」の概念は“夜に流れる水”から生まれた
・ラテン語はインド・ヨーロッパ語族に属している
・古代の人々は「母」という概念をどう考えたか?
・ピタゴラスはインドの思想に影響を受けていた
Lectio IV 私たちは学校のためではなく、人生のために学ぶ
――Non scholae sed vitae discimus
・赤ちゃんに学ぶ「言語学習の本質」
・ラテン語の発音からヨーロッパ社会を学ぶ
・発音からすけて見える「ヨーロッパ人のプライド」
Lectio V 長所と短所
――Defectus et Meritum
・長所と短所の「語源」から見えてくるもの
・自分の短所と目をそらさずに向き合う
・ラテン語の名句に学ぶ「捨てる勇気」
Lectio VI ひとりひとりの“スムマ・クム・ラウデ”
――Summa cum laude pro se quisque
・奥深いラテン語の名詞
・真の教育とは、勉強したくなる動機を与えること
・ラファエロの絵画と神秘主義
Lectio VII 私は勉強する労働者です
――Ego sum operarius studens
・ラテン語「エゴego」の役割
・習慣の語源が教えてくれること
・「勉強する労働者」は挫折を楽しむ
Lectio VIII カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい
―― Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo
・イエスの使徒パウロとローマのかかわり
・キリスト教がここまで普及した理由
・キリスト教における「政治と宗教の分離」
Lectio IX たとえ神がいなくとも
――Etsi Deus non daretur
・法学者グローティウスの主張
・聖書は弟子たちによる“授業ノート”か
・人が哲学や倫理を求めた理由
Lectio X 与えよ、さらば与えられん
――Do ut des
・「あなたが私に施したから、私もあなたに与えよう」
・「相互主義」という国際ルールの起源
・人生は、他者を思いやることで完成する
Lectio XI 時間は最も優れた裁判官である
――Tempus est optimus iudex
・時間にまつわるさまざまな言葉
・長い時間をかけて辞典を作り、悟ったこと
・古代ローマ人は「幸せ」をどう考えたか?
Lectio XII すべての動物は性交後にゆううつになる
――Post coitum omne animal triste est
・絶望の日々をどう乗り越えたか
・ラテン語の名句を英単語と照らし合わせる
・「期待した瞬間」が過ぎさると、人間は絶望する
Lectio XIII あなたが元気なら、よかったです。私は元気です
――Si vales, bene est; ego valeo
・古代ローマ人のあいさつ
・郵便は軍事目的でも使用されていた
・「あなたが安らかであってこそ、私も安心できる」
Lectio XIV 今日は私へ、明日はあなたへ
――Hodie mihi, Cras tibi
・死をくぐり抜けた人間は、どんな香りを放つのか?
・古代ローマの葬儀
・人間は、他者に残された記憶によって香りを放つ
Lectio XV 今日を楽しみなさい
――Carpe diem
・名句Carpe diemは農業に由来する言葉
・今日を我慢し、節制するのは美徳なのか?
・ローマ人たちも「過去」に縛られていた
Lectio XVI ローマ人の悪口
――Improperia Romanorum
・ラテン語の「洗練された悪口」
・「神聖な」「呪われた」という2つの意味が混在する言葉
・「心の言葉」に耳を澄ませよう
Lectio XVII ローマ人の年齢
――Aetates Romanorum
・ヨーロッパ言語が「水平型言語」である理由
・イタリア人に受け継がれた「寛大な精神」
・学びとは、自分だけの歩き方を学ぶこと
Lectio XVIII ローマ人の食事
――Cibi Romanorum
・「私を上に引っ張り上げる」ティラミス
・古代ローマ人の一日の食事
・宴がわかれば、ローマの文化がわかる
・同性愛を禁止した合理的な理由
Lectio XIX ローマ人の遊び
――Ludi Romanorum
・ローマ時代のさまざまなゲーム
・セネカが軽蔑した「円形闘技場の熱狂」
・高度な技術力に支えられた公共浴場
Lectio XX 物事は、知っているものしか見えない
――Tantum videmus quantum scimus
・ムッソリーニが標榜した「偉大なイタリア」
・カエサルが暗殺された場所
・自分が知っているものしか目に入らない
Lectio XXI 私は欲望する。ゆえに存在する。
――Desidero ergo sum
・スピノザとデカルトの違い
・満足とは「十分に何かをする」こと
・人間が作り出した最高の仮想が、人間を苦しめている
Lectio XXII 韓国人ですか?
――Coreanus esne?
・「国」という概念はいつから生まれたか?
・「天才教授の怒り」忘れられないエピソード
・「私たちはみな同じ人間」という真実
Lectio XXIII しかし、今日も明日も、またその次の日も、私は進んで行かねばならない
――Verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare
・sex の由来は数字の「6」だった
・単語ひとつに思想が反映される
・勉強の由来は「心から望む何かに力を注ぐこと」
Lectio XXIV 真理に服従せよ
――Obedire Veritati!
・世界の問題を「世俗の学問」の力で解決する
・ボローニャ大学の果たした役割
・真理を解くカギは「宗教」にある
Lectio XXV みな傷つけられ、最後は殺される
――Vulnerant omnes, ultima necat
・古代ローマでどのように医学が発展していったか?
・心と体を傷つけるのは、他者ではなく、自分自身
Lectio XXVI 愛しなさい、そしてあなたが望むことを行いなさい
――Dilige et fac quod vis
・砂漠とは、神への信仰が深まる場所
・タクラマカン砂漠の洗礼
Lectio XXVII これもまた過ぎゆく
――Hoc quoque transibit
・今日できることは明日に延ばそう
・「朝、自分に微笑みかける」という課題の真意
・うれしいことをしっかり嚙みしめる
Lectio XXVIII 命ある限り、希望はある
――Dum vita est, spes est
・今の人生を送るか? 完璧な世界で新たな人生を送るか?
・希望の語源は「期待して望む」
・死と直面して悟ったこと
・感謝の言葉
・監訳者あとがき
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock