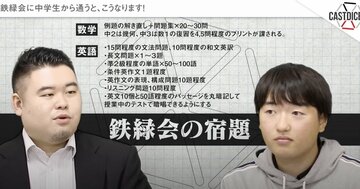「お手伝い」を通して
社会を見る目を養う
お手伝いと勉強、どちら優先?
× お手伝いよりも勉強の時間を優先させる
○ お手伝いは学びにつながるのでバランスよく取り入れる
日常のお手伝いから社会科への視点を養うことができます。たとえば、買い物に行くと、コンビニやスーパーでの食材の陳列の仕方がどこの店舗でも大体同じであることに気づきませんか?
スーパーだと、入口に野菜売り場があって、その奥に肉や魚が売っているコーナーがあり、真ん中の棚には、お菓子や保存食などが並んでいます。親子で「なんでこの配置なんだろうね?」と話しながら、店内を観察して陳列の謎に迫る仮説をつくってみるとおもしろいですよ。「もしかしたら、お客さんが買いやすいのかな?」などと気づきがあるはずです。これは社会科のなかでもとくに経済の分野の視点を養うことにつながります。
ほかにも、「道を挟んで向かい合った位置にコンビニがあるけれど、どうしてつぶれないんだろう」や「なんでこのチョコレートは安くて、こちらは高いんだろう」など、買い物は子どもにとって「なぜ?」の宝庫です。その疑問に対して「じゃあ、ちょっと考えてみようか」「調べてみる?」と返事をして、仮説を組み立て検証していきます。必ずしも答えをだす必要はありません。仮説をつくる過程を楽しむことが社会科の力につながっていきます。お父さんやお母さんもプレッシャーを感じることなく、ああでもないこうでもないと推測することを楽しんでみてください。
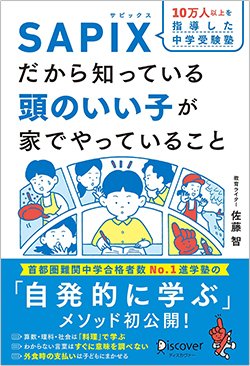 『10万人以上を指導した中学受験塾SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『10万人以上を指導した中学受験塾SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)佐藤智 著
家のなかでのお手伝いなら、食器運びを子どもの役割にしているご家庭がありますよね。食器の並べ方で「どうしてお茶碗と味噌汁のお椀の位置は決まっているの?」といった疑問が子どもからでたことはありませんか?
こうした気づきも、社会科の学びの一つです。実際にSAPIX小学部に通っている子が「あの配置だと食べにくいんだよね。なんでだろう?」と言って、そこから学習が始まったこともあります。
社会科は回り道こそ、おもしろいのです。あれこれ回り道をすることで、さまざまな事柄を知ることができます。そして、知れば知るほど、わからないことも増えていきます。それを繰り返すことによって、社会科の学びは深まっていくのです。
買い物や食器の配膳などのお手伝いから子どもの疑問をすくい上げ、対話を通して答えの仮説を考える