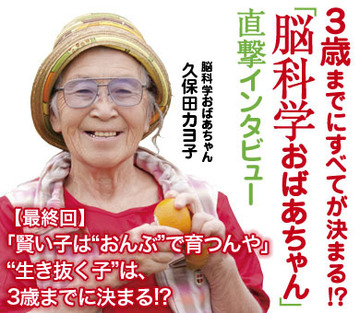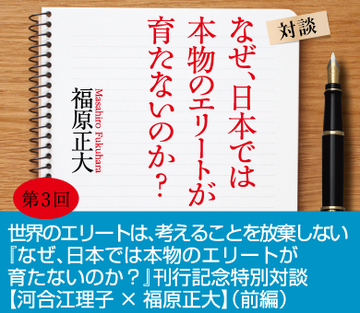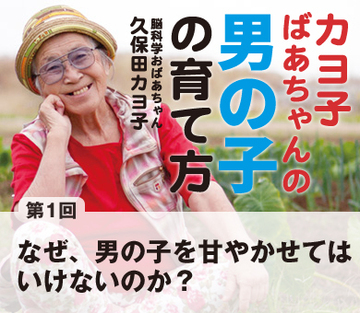本能のままに育てる
――「母子相伝」の子育て
このように言うと、多くのお母さんは「知識」で子育てをしようとします。書店に並んでいる育児の専門書を片っ端から購入し、それを読んで、少しでも育児に役立てようとするのですが、これはあまり意味がありません。
だって、お母さんは育児の研究者ではないのですから。
そもそも育児の専門書というのは、昔から男性の医師や育児研究家が書いているケースが多かったのです。
それをいくら読んでも、実践では役に立ちません。
「病気にならないオムツのつけ方」などが懇切丁寧に説明されていたとしても、それは単なる解説書であって、賢い子どもを育てるための方法にはなにひとつ触れていないのです。
たとえば、赤ちゃんがワーワーと泣き出したとします。
お母さんは一所懸命に抱き上げて、あやします。
このとき、泣いている理由が、体の不調にあるのかどうかを見極めることは必要です。
そうでなければ、なんとか早く泣きやませたいと思うことでしょう。
おそらく書店に並んでいる育児書には、赤ちゃんを泣きやませるためのあやし方や、「とにかく抱いてあげてください」などと書かれていると思いますが、赤ちゃんが泣きたがっているのを、無理やり泣きやませようとするのは、特に生まれたばかりの赤ちゃんにはよくありません。
赤ちゃんのころは、本能のままに育てていくほうがいいのです。
それは後々、子どもの能力を伸ばしていくうえで必要な通過儀礼のようなものですから、ワーワーと泣き出したら、まずは思いっきり泣かせましょう。
もちろん、赤ちゃんのうちは、そんなに長い間泣き続けることはできません。息継ぎで苦しくなるからです。
なので、1分も泣けば自然のうちに、泣きやもうとします。
でも、そこで終わらせるのではなく、お母さんは赤ちゃんが泣きやもうとしたら、声がけをして、さらに泣き続けるように働きかけます。
そうこうしているうちに、泣く時間が長くなっていき、泣きやめば自然と眠りに落ちます。
人間は、自分が赤ちゃんのころに、周りの大人たちがどれだけ自分の欲求をのびのび受け容れてくれたかによって、その後の能力に差が出てきます。
とにかく、泣いている子どもは全身全霊で泣かせることです。
泣いている最中に、「泣くな!」と言うと、子どもは暴れます。
泣くということは、特に産まれたばかりの赤ちゃんにとっては、自分の意思を親に伝えるための手段なのです。
昔は、育児書などありませんでしたが、自分の母親からの口伝によって、こうした子育てのノウハウが代々伝えられてきました。
たとえば、「ピーピー」という弱い泣き声は、休み休み泣くので心肺機能が向上しません。
“泣く子は育つ”は、まさに母子相伝の知恵から来ているのです。
それが、いつのまにか育児書に取って代わられるようになりました。
核家族化が進み、大家族で生活しなくなったことも、その原因のひとつでしょう。
そこに、現代社会の育児の危険性があります。
この状態が続き、さらに歳月がすぎて子どもから孫、そしてひ孫の時代になったら、誰も“母子相伝”の子育て法を伝えることができず、やがては忘れ去られてしまうでしょう。
そうなる前に、“母子相伝”の一般に通じる育児法を書き残しておく必要があります。これは、私にとっての使命と考えます。その“母子相伝”の育児法を参考にするか否かは、それぞれのお母さんの判断でよいのです。