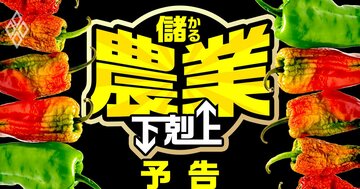むしろ後継ぎがいない農家には、成長した彼らに重要な仕事や経営を任せる柔軟さや切迫感こそが必要なのではないか。農地を貸与し、一定の成果を上げたと認められる段階で、経営権あるいは農地所有権を移譲する。いまはそういった検討をタブー視しているような時代でもない。外国人が離農した際には、その農地を本来の所有権者や国または自治体へ返還することを規定するなど、現在の「外国人土地法」(1925年)という古い法律を改正することと合わせ、農地法の見直しをする時ではないかと思う。
増え続ける耕作放棄地、低下する食料自給率を放置するよりどれほど建設的なことだろうか。例えばアメリカの多数の州では、制度的に国籍に無関係に農地所有権を取得できる。実は筆者も、アメリカのカリフォルニアの農地を共同で買おうとして資金拠出したことがある。残念なことに、資金管理者の不始末に遭い、計画は頓挫する苦い体験をしたのではあるが。
中国でさえ資本制企業の農業参入を自由化
日本の農地制度が適応の柔軟さに欠ける点では、主要国の頂点にあるといえそうだ。企業の農地利用の農業経営参入には厳しい規制が課せられている。それに比べると、社会主義独裁国家でありながら、中国の農地制度は徐々に自由化を進めてきた。中国の農地制度は共産党が政権をとった1949年から数次の改革を進め、農家単位で農地を請け負う制度に変わった。ところが農業離れ・高齢化・生産コスト上昇・農家家族制度の変容などから、この制度は急速にほころびはじめ、これを背景に農地権利の流動化の勢いが激しくなった。