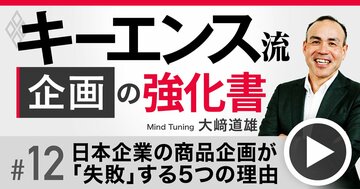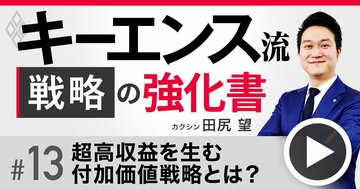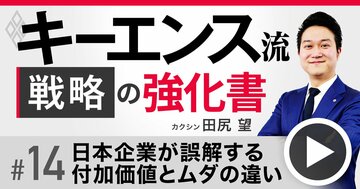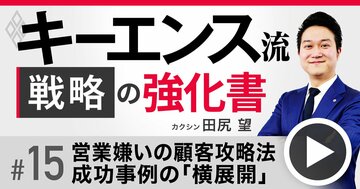ワンマン社長による
「口出し」は絶対NG!
大崎氏が挙げる1つ目の失敗パターンは、「経営陣が商品の企画・開発に関わっている」というものだ。中でも、ワンマン社長が自ら企画・開発を担当し、社員に権限委譲できていない企業からは、ヒット商品も生まれにくいという。
言わずもがなだが、社長が向き合うべき業務は多岐にわたる。中小企業やベンチャーでは、経営や資金繰りをはじめ、人材採用や営業チームの指揮を社長が担っている場合もある。その状況下で、ワンマン社長が「片手間」で企画・開発に取り組んだとしても、良い結果が出ないのは当然だ。
「徹底的な顧客分析、競合の調査、コンセプトの作り込み、仮説検証……。そうした難易度と負荷の高い業務を、社長自身が同時並行で担当するのは現実的ではありません」(大崎氏、以下同)
そこで重要になるのは、やはり適切な権限移譲である。商品の企画・開発を手掛ける部署を新設し、社員を信頼して企画案を考えてもらう。ブラッシュアップなどの実務も任せ、社長はあくまで可否判断に徹する。そうした健全な役割分担を進めることで、良い商品企画も生まれやすくなると言える。
「部署横断型」の企画会議も
対立を生むためNG!
2つ目の失敗パターンは、「多くの部署から人を集めて商品の企画・開発を進める」というものだ。
こうした「部署横断型」の開発体制は、一見すると自由闊達(かったつ)な議論を生む、素晴らしい取り組みのように思えるかもしれない。だが実際は、チーム内に「営業部門」と「生産・開発部門」の人間が混ざっていると、価値観の違いから思わぬ対立を生みかねない。
何しろ、営業部門は「早急に売り上げを得て、予算を達成する」ことを重視しがちだ。一方で、冒頭の通り「売れ線狙いの商品」が良い結果を招くとは限らないため、生産・開発部門は慎重に新商品を企画しようとする。「投資したリソースに見合うだけの利益が得られるか」というコスト感覚も強く持っている。
その折り合いがつかず、企画会議などで「今すぐ売れるものを作ってほしい」(営業部門)、「そんなものが作れるわけがない」「コスト的に難しい」(生産・開発部門)といった形で意見が対立し、開発が頓挫してしまうのも“あるある”だ。
そのため大崎氏は、「商品企画は、案件ごとに1人で担当するのが理想的です」と説く。市場調査・仮説検証・企画案のブラッシュアップといった一連のプロセスは、ノウハウを持つ個人が責任を持って実行すればいいのだ。他部門も交えて販売計画を立てるのは、ある程度企画が固まってからで問題ない。
にもかかわらず、良かれと思って多くの担当者をアサインすることが、逆に企画の「迷宮入り」を招くと言える。