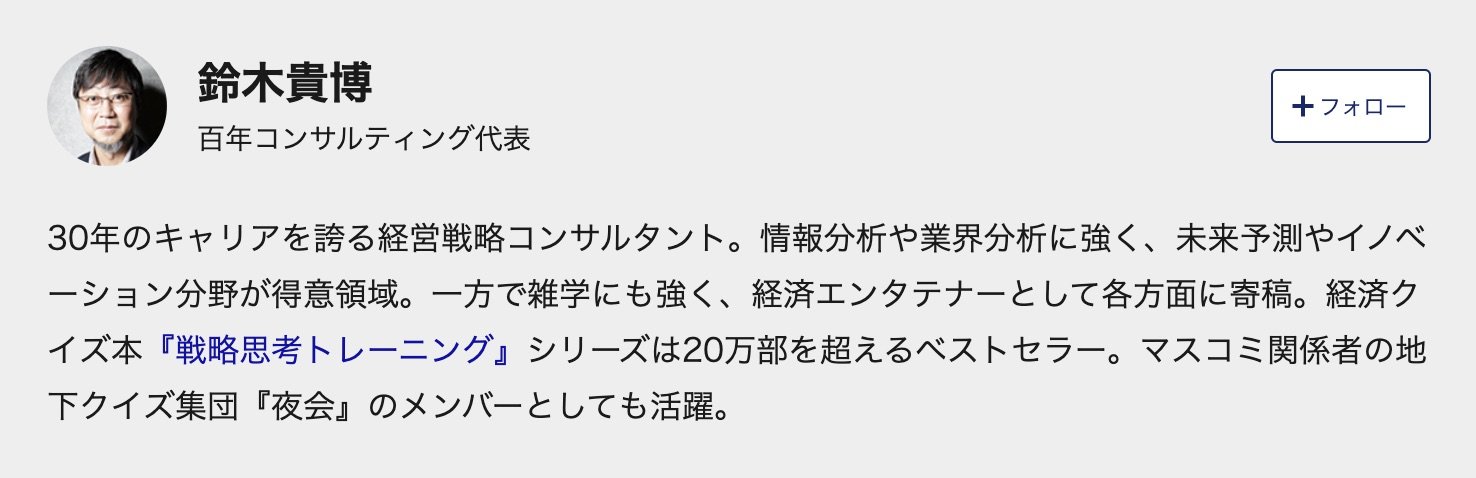視点3 悪意のある会社の存在
さて弁護士ではない退職代行会社が繁盛している理由は、世の中の多くの会社が労働法規に従ってくれているからです。
退職代行会社が上司ではなく人事部にまず連絡を取る理由も、ここにあります。
ただ、世の中には一部とはいえそもそも社員を辞めさせない職場があります。
「辞めるんだったらお金を払え」と言われた実例があると言うと、大企業に勤めている人は信じないかもしれませんが、実際、研修費を払えとか、違約金を払えと言われたことがある人はいます。
退職代行の方によればアルバイトでも退職代行を使うケースが少なからずあります。シフトを勝手に入れられ毎日働かされて、辞めるんだったら店がつぶれるから賠償金を払えとまで言われます。法律知識がない若者はそれを信じてしまうのです。
人手不足の職場では退職届を受理しないと言うケースもあります。違法なのですが、仕事がまわらなくなるので、とにかく受理を拒むわけです。その際、嫌がらせとして未払いの賃金は放棄しろとか、退職金は出ないとか、超法規的なことを上司に言われる場合も出てきます。
そうなると退職するためには会社との交渉が必要になります。
そもそも普通の社員にはそんな交渉の技術もありません。それでプロである退職代行を使うしか方法がなくなります。交渉が前提ですから弁護士の運営する退職代行会社しか選択肢がなくなります。これが料金が高い方の退職代行も繁盛している背景です。
さて、この話はこの後、もうひとつ別の論点があります。
その前提でここまでの話をまとめると、21世紀のこの世の中、退職代行を使って退職すると言う行動には一定の合理性があるということです。
普通にちゃんとした会社を辞めるために2万円支払って心理的に嫌な退職手続きを代行してもらうというのは経済合理的な行動です。普通ではない会社となんとか関係を断ちたいと考えて、たとえ弁護士に10万円を支払ってでも退職を勝ち取りたいというのも、経済合理性で考えれば割に合う行動だと言えます。
そしてそのように行動する若者を、「人間として、マナーとして許せん」と考える管理職や経営者は、善悪に関する常識が古いということになります。
そこで最後にもうひとつだけ考えてみたいと思います。退職希望者が退職代行を使うと損をするのはどのような場合なのでしょうか?
それは会社を辞めた後も、前の会社といい関係を続けたい場合です。
会社を辞めた後も、何らかの形で元上司に相談に乗ってもらうとか、昔の同僚と普通に会える関係性を持ちたいとか、そういった自然な関係を持ちたいと思ったら、会社の辞め方は普通に行ったほうが得策です。
ここで言う「普通に」とは、「昭和の管理職がかちんと来ない辞め方をする」という意味です。
法律上、社員にはいつでも辞める権利があるというのは正しいです。
一方でたとえ昭和のおじさんでも憲法で定められた信条の自由を持っています。
何か言うたびに若い社員から、「それはパワハラですよ」と注意を受ける世代でも、最後の最後で「口には出せないけれどもよく思わないぞ」と腹の中で考える権利だけは法律で認められているのです。
そう考えると退職に関して総合的に見ると、目的が縁を切りたいのかそれとも卒業をしたいのか、そのどちらなのかによって退職代行を使うかどうか判断するのがいいように思えます。あくまで昭和世代の評論家としての意見ですが。