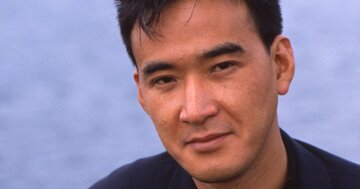脚本家は、押し付けに基づいて書かなければならないので、苦労したことだろう。その苦労の甲斐があって、製作費の削減ができたのである。でも、ストーリーが面白くなければ駄目だ。(同前)
もちろん主演の萩原健一も、市川森一とやり取りをしていた時と同じく、一切の手抜かりなく若手の脚本に注文をつけてくる。
ショーケンも脚本にこだわり
撮影時のアドリブで脚本が変化
設定の不自然さが出るとショーケンから深夜に電話がかかってくる。約1時間にもおよぶ長電話は、役柄のアイデアも含めてのことだ。四六時中、ドラマのことを考え、真面目に取り組んでいるので、一緒に飲みに行っても仕事の話だった。(同前)
でき上がったシナリオも、萩原のアドリブによって撮影時に変わった。しかしシナリオはあくまでも作品の骨組みである。シナリオに書かれた内容を崩さない範囲で、監督の演出と萩原ら俳優陣の芝居によって、ドラマがいい方向に味つけをされていった。
 『永遠なる「傷だらけの天使」』(集英社新書)
『永遠なる「傷だらけの天使」』(集英社新書)山本俊輔、佐藤洋笑 著
でき上がった作品は、必ずしも台本通りではなかった。台本はあくまで作品の方向性で、監督たちも、ショーケンのキャラクターを活かしながら、心情ドラマをつくり上げてくれた。(同前)
あのドラマではアフレコといって、収録を終えた後にセリフを吹き込んでいました。だからアフレコの段階で変えさせられたセリフもある。収録のとき、修は亨の顔を見るたびに勢いで「バカヤロ~!」と怒鳴っていたんですが、プロデューサーから「バカヤローが多すぎるんじゃないかな」と苦言を呈された。だからその部分をアフレコのとき「アキラ~!」と吹き替えたんです。口と言葉が合ってないんですが、そのプロデューサーは「合わなくてもOK。気持ちの問題だから」だって(笑)。(『週刊現代』2012年4月21日号、「週現『熱討スタジアム』」萩原健一の証言)
それに水谷豊が「アニキ~!」と呼応して、結果的に『傷天』名物の2人のやり取りが誕生したのだ。やはりこの作品は優れた脚本を土台に、才能ある俳優たちが美味い味つけを施した逸品なのだと、改めて認識する。