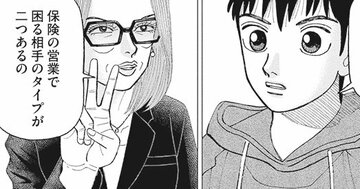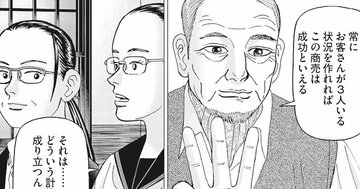『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから紐解く連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第149回は、資産価値が暴落する「ミンスキー・モーメント」について解説する。
「雨の日」こそ助けがほしいのに…
戦前に隆盛を誇った鈴木商店は株式公開を避け、設備投資など事業資金の調達を銀行融資に過度に依存した。主人公・財前孝史は曽祖父である龍五郎に、事業拡大の末に鈴木商店が経営破綻に至った「未来」を明かす。
鈴木商店の弱点は、資金調達を台湾銀行の融資に依存した財務体質の弱さにあった。
「銀行は晴れた日に傘を貸し、雨の日に傘を取りあげる」という言葉がある。業績が良い企業には積極的に貸し出すが、本当に資金が欲しい状態に陥ると融資を引き揚げる。苦しいときに銀行は頼りにならない、という恨み節だ。
とはいえ「雨の日」に回収を優先するのは金貸しの常道だ。銀行の経営者は株主や預金者に対してリターンや利息をもたらす責任を負っている。焦げ付く可能性が高いのなら、傘を取りあげるしか選択肢はない。
そうした平時の市場原理を超えて「負債頼み」が生死を分ける局面がある。金融論で「ミンスキー・モーメント」と呼ばれる状況だ。
経済学者ハイマン・ミンスキーは好況が過剰な借り入れとリスクテークを促し、投機が過熱した先に金融の機能不全が待つという仮説を唱えた。そうした不安定性は市場が内包する本質で、危機は不可避という。
代表例が2008年のリーマン・ショックだ。危機が起きる前、金融市場は長期安定期にあった。欧米では「企業にとって重要なのはキャッシュではなく、必要な時に資金を調達できる優秀なトレジャラー(Treasurer)だ」という風潮が強まった。トレジャラーは日本では財務部や資金部に相当する。企業のカネ回りを多角的に支える専門職だ。
「日本企業は時代遅れ」がひっくり返った瞬間
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
余剰資金を抱えるのは資産効率にはマイナスだ。必要な時に必要なだけ資金を調達できるなら、余った金は自社株買いや配当に回してROEなどを高めれば、株高を呼びこんで投資家から高い評価が得られる。
そんな発想から見ると、資金を貯めこんでいた日本企業は時代遅れに映り、実際にマーケットからも「配当や自社株買いに回せ」というプレッシャーがかかっていた。
リーマン・ショックが来ると空気は一変した。当時の白川方明・日銀総裁が「ドルの流動性が枯渇した」と明言するほどのパニックのなか、企業どころか銀行ですらまともに資金調達できない状態に陥った。
絵に描いたようなミンスキー・モーメントの真っただ中、かねてカネ余りを批判されていた某大手企業のベテラン経営者がインタビューで「どちらが正しかったか、今なら分かるだろう」と答えていたのが印象に残っている。
日本経済新聞によると、2024年の日本の上場企業の自社株買いは過去最高の約17兆円と前年比7割も増える見込みという。上場企業の手元資金は約112兆円と「貯めこみすぎ」なのは確かで、資産効率改善や株主還元が進むのは歓迎すべき動きだろう。
だが、ミンスキー・モーメントがいつ再びやってくるかは分からない。その瞬間「キャッシュ・イズ・キング」へと世界は一変する。そんなリスクを頭の片隅に置いておいて損はない。
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク