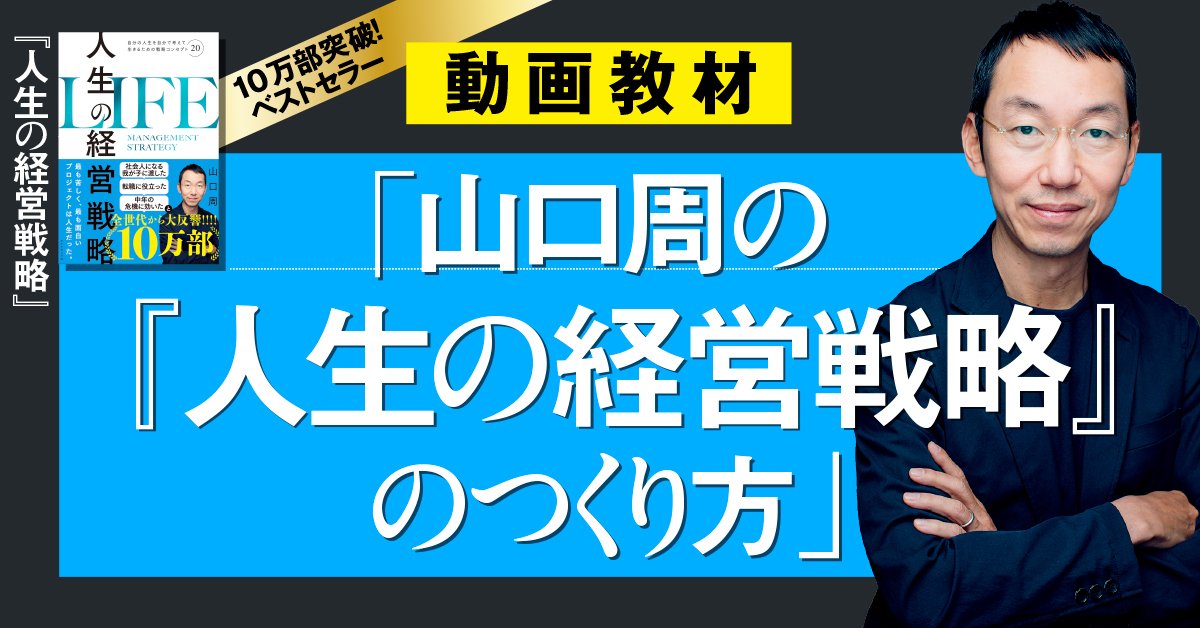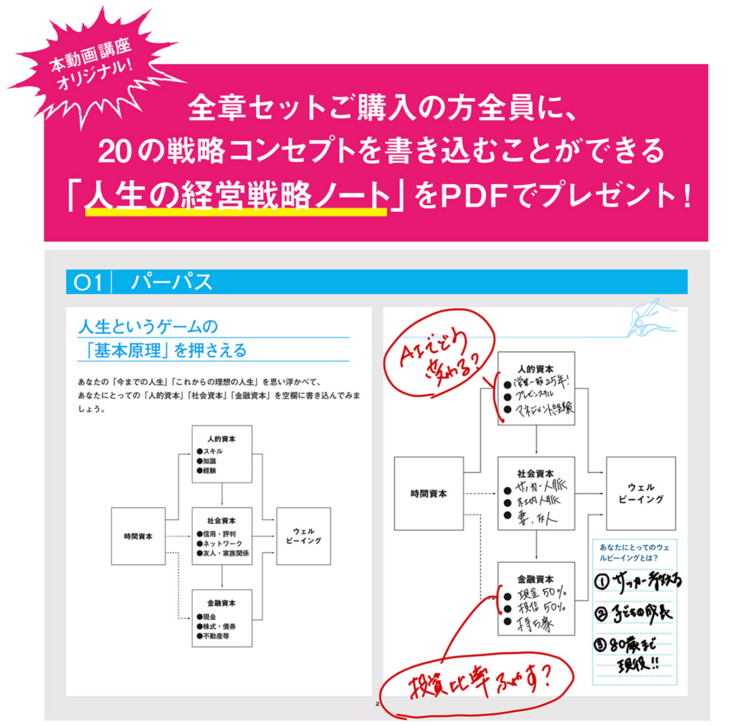「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「全部うまくいっている」は危険な兆候
本書では「経験学習理論」という経営戦略を紹介しています。
そもそも「経験」とはどのように定義されるのでしょうか? 省察の構造を研究したD・A・ショーンは「予測しなかった結果に出会うことができる機会」と指摘しています。
人は、予測しなかった結果に出会ったときに、それまで暗黙的になされていた自分自身の行動を表に出して、批判的に振り返ります。「こうなるはずだ」と思ってとった行動が、思いがけず想定外の結果を招いた時、人は自己のシステムの変容を促すようなきっかけを得るのです。
ショーンによる「経験」の定義は、私たちのライフ・マネジメント・ストラテジーに大きな洞察を与えてくれます。「経験」が学習の起点であり、さらに「経験」が「想定外の結果に出会って困惑すること」なのだとすれば、私たちが望ましいと考えている「何もかも想定通りにうまくいっている」という状態は「学習の停滞した状態」と言い換えることができるからです。
まれに企業研修などの場で「自分はプロジェクトを失敗させたことがない」と自慢気に話している人がいますが、ショーンの指摘を踏まえれば、若い時に失敗経験がないというキャリア自体がすでに失敗だ、とも言えるのです。なぜなら、特に若い時期の失敗は、失敗がもたらすリターンの期間が長期化するためNPV(※本書で紹介している正味現在価値)が大きいからです。
このように考えてみると、若い時ほど良質な失敗体験を積ませることが重要だ、ということになるわけですが、これがなかなか難しいのです。
というのも、現在の日本社会は非常に過保護になっており、若い人を自由に働かせて思いっきり失敗させるということが、なかなかできていないからです。
この問題に追い討ちをかけるのが、社会と組織のピラミッド構造です。日本企業は1990年前後のバブル期に大量採用を行っており、多くの組織において50代の「花のバブル入社組」の層が厚くなっているため、よほど意識的になって「質の良い仕事」を若い世代に回していかない限り、若年層で「経験のデフレ」が起きることになります。