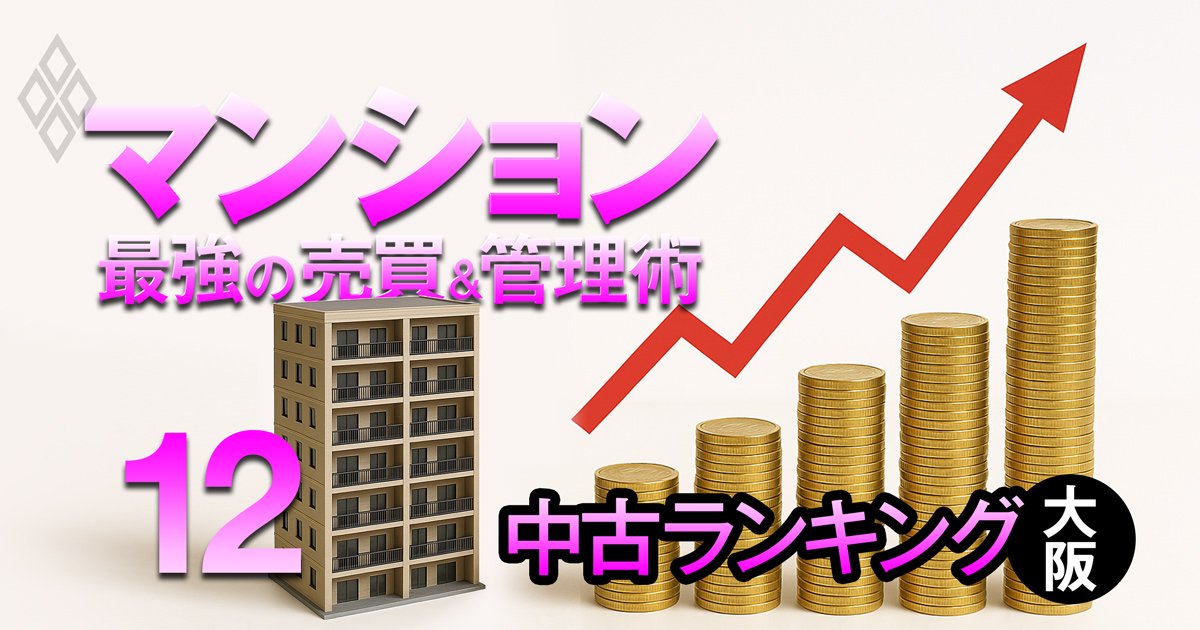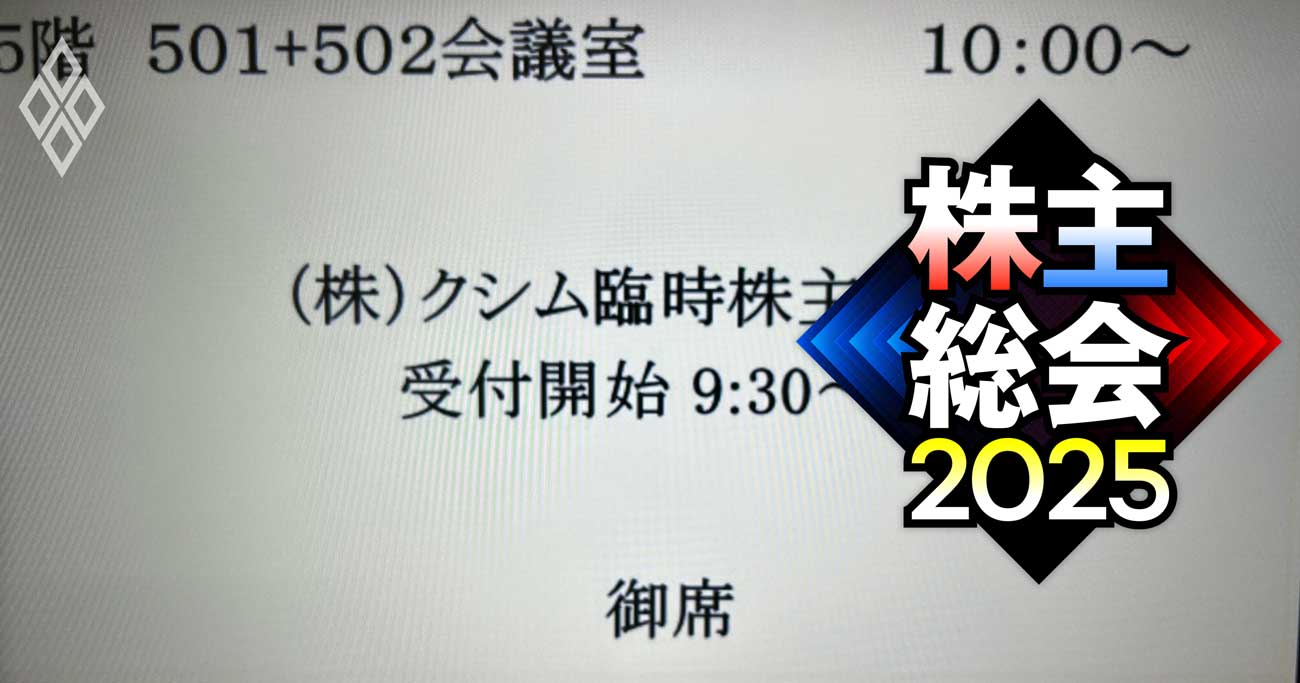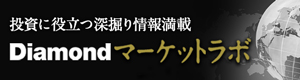社会資本が機能しないとなれば、それに依存するコミュニティーでの生活は極めて困難になる(写真はイメージです) Photo:PIXTA
社会資本が機能しないとなれば、それに依存するコミュニティーでの生活は極めて困難になる(写真はイメージです) Photo:PIXTA
高成長期に集中的に投資
対GDP比率、38%から直近26%に低下
埼玉県八潮市での下水管破損事故をきっかけに、いまの社会資本を維持できるのか、その可能性に関する関心が高まっている。
日本の社会資本は、高成長期(1950代中ごろから80年代ごろまで)に急速に整備された。
耐用年数を50年とすると、2000年から30年代ごろまでの期間に、それらの施設の更新が集中して必要になる。では、必要とされる更新投資を実際に行うことができるだろうか?
これを考える手掛かりとして、まず日本で過去の投資がどのように行われたか、世界銀行のデータベースで見てみた。
ここで示すのは、粗投資(資本減耗引き当てを含む投資額)のGDP(国民総生産)に占める比率だ。政府投資(社会資本投資)だけでなく、民間の設備投資や住宅投資なども含む。
70年代の日本は、高度成長は終えたが、石油ショックを克服して高成長を続けていた。このため、粗投資がGDPに占める比率は38%程度と極めて高かった。
しかしその後、比率は低下し、最近では26%程度になっている。
このデータを用いて、今後の更新可能性について、おおよその見当をつけることができる。