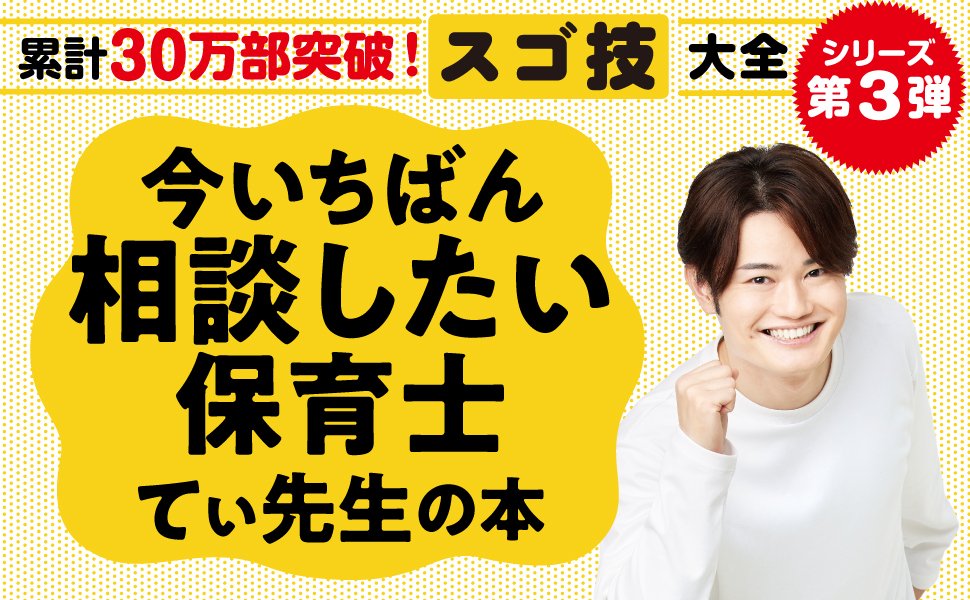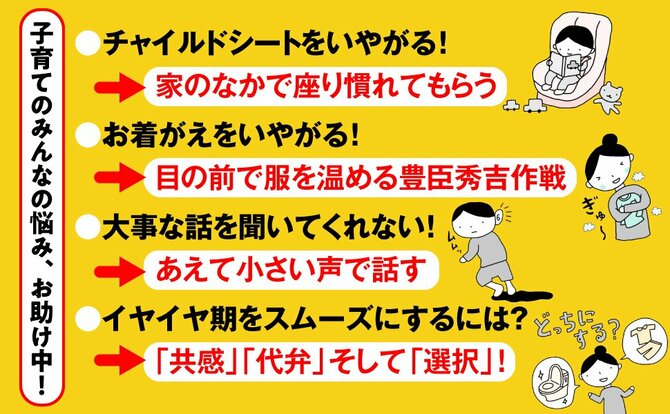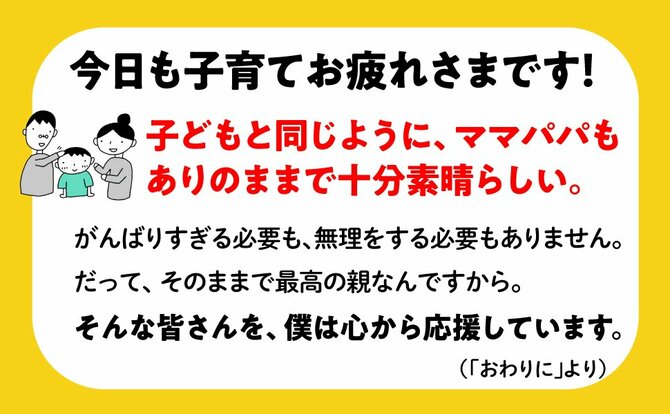【テレビやSNSで大人気】今どきのママパパに圧倒的に支持されているカリスマ保育士・てぃ先生の子育てアドバイス本第3弾『子どもにもっと伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てのみんなの悩み、お助け中!』ができました!
テレビやSNSで大人気、今どきのママパパに圧倒的に支持されている現役保育士・てぃ先生。そんなてぃ先生のSNSには、毎日膨大な数の悩みや相談が届くといいます。
本連載では、そんなママパパたちに向けて、正論だけではない、すぐに使えるリアルな回答をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
【みんなの悩み】子どもがあいさつできません!
「おはよう」「おやすみ」「いただきます」などのあいさつができないのでガミガミ叱ってしまいます。どうしたらできますか?
【てぃ先生の答え】無理にするものではありません
「あいさつしなさい!」と叱られるから、仕方なくするあいさつ。果たして気持ちがいいでしょうか? 答えはノーですよね。もちろん人にあいさつをするということは、大事なことです。習慣づけたいことでもあります。
でも、物事には順序がありますよね。子どものあいさつもそうです。いきなりは難しい。最初は見て、聞いているだけでいいんです。
できたときにほめる。これをくり返そう
親やまわりの大人が気持ちよくあいさつして、それをやってみたい、真似してみたいと思ったときにはじめれば十分。おままごとや遊びのなかであいさつする様子があったら、「おはよう!あいさつってうれしいな~」と、声をかけていけば、生活のなかでも自然と出てくるようになります。
「おはようは?」「いただきますは?」と追い詰めるよりも、子どもからのあいさつを待って、できたときに思いっきりほめる。これをくり返したほうがポジティブにあいさつが習慣化されます。
オン/オフの気持ちの切り替え
子どもにとってあいさつは、「いったん静止してきちんとそのことに向かい合う」「オン/オフの気持ちの切り替えをする」といった意味もあります。
たとえば「いただきます」なら、手を合わせて静止するから「今から食べるぞ!」と、脳が切り替わって食事に集中しやすくなりますし、「ごちそうさま」なら、食事が終わってここからは別の時間だとわかりやすくなります。「おやすみなさい」なら、それを口に出すことで「今から寝るぞ」という気持ちになります。
こんなふうに、あいさつはその言葉の本来の意味を離れて生活の中での「合図」の意味があり、言うほうも言われるほうも、オン/オフの切り替えがしやすくなるわけです。
なので、「絶対あいさつさせなくては!」というよりも、「さあ、ここからは◯◯の時間だよ」という意味で大人が自然に口にしていけば、お子さんもだんだん生活習慣として言えるようになるのではないかと思います。
本原稿は、てぃ先生著『子どもにもっと伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てのみんなの悩み、お助け中!』からの抜粋です。この本では、子育てがラクになって、親子とも幸せになるテクニックを紹介しています。