でも後になって大人から「あのときどうして言わなかったの?」と逆に責められたりして、いっそう子どもを追い詰めてしまうことにも繋がります。
また何か新しいことのチャレンジについて「やってみる?」と大人から聞かれ「うん」と答えた場合、大人は子どもがやると言ったのだから、やる気があるんだ、と受け取ります。
ポジティブ質問よりも
ネガティブ質問のほうが安全?
ところが往々にして子どもはその期待に従わないことも多いです。そんな中、もし子どもが途中で止めたりサボったりすると、子どもが嘘をついたと感じ「自分からやるって言っただろう?」と大人には怒りが沸いてきます。
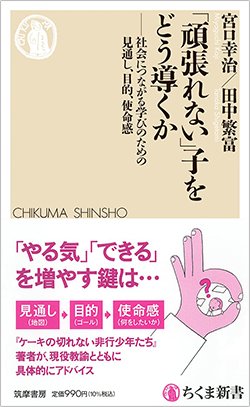 『「頑張れない」子をどう導くか――社会につながる学びのための見通し、目的、使命感』(宮口幸治、田中繁富 ちくま新書、筑摩書房)
『「頑張れない」子をどう導くか――社会につながる学びのための見通し、目的、使命感』(宮口幸治、田中繁富 ちくま新書、筑摩書房)
勉強で、「分かりましたか?」という問いに「うん」と子どもが答えてしまうのも同様です。実際にやらせてみてできないと「さっき分かったって言ったでしょ?」と責めてしまいがちです。「分からない」と正直に言うのは、大人でもなかなかできないはずなのですが。
子どもが「うん」「分かった」と言うときは要注意で、額面通りに受け取るのではなく本心からそうなのか気にかけてあげましょう。実は大人の機嫌を取ろうとしただけで、本当はやりたくないのかもしれない、しんどいかもしれない、分かっていないのかもしれない、ということを前提に問いかけたほうがいいでしょう。
ここでは「本当はやるのは不安ではない?」「お腹を押さえているけど、しんどいのでしょう?」「少し説明が難しくて分かりにくかったでしょう?」といった問いかけがよさそうです。
やはりここで子どもが「うん」と言えば、無理をしていたことや、しんどさを表現できます。たとえその時に子どもが「大丈夫」と言っても、時間をおいて再度聞いてあげましょう。大人は子どもの“代弁者”でもあるのです。







