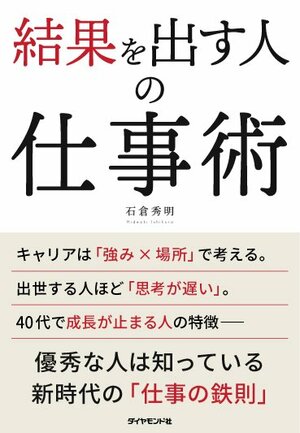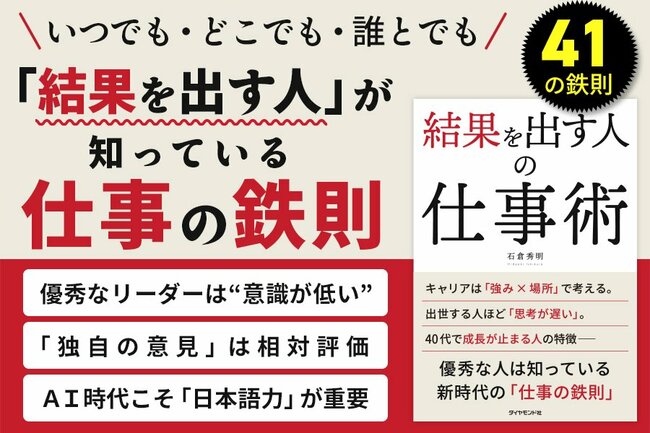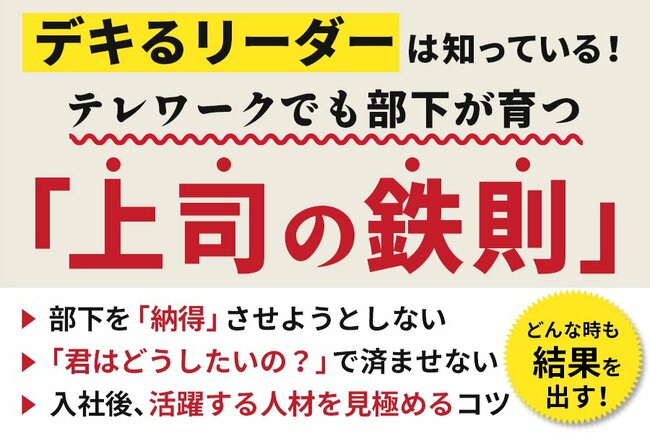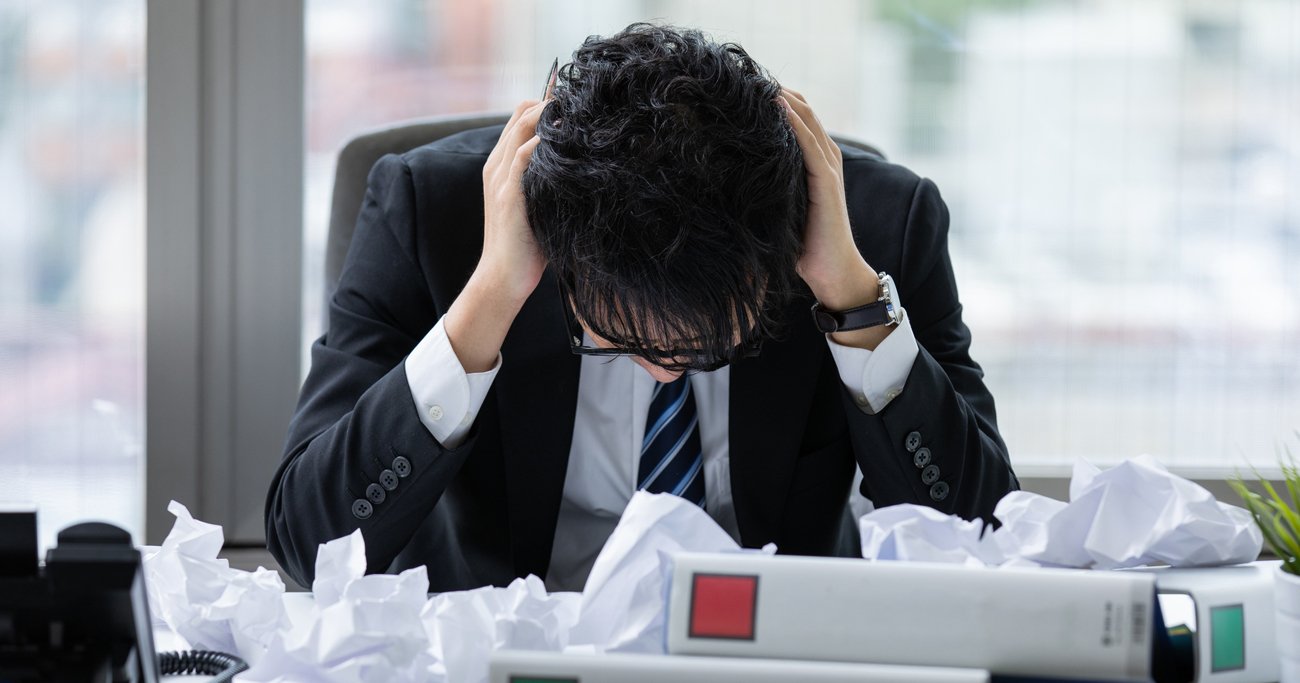 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
ビジネスでは「仕組み化」が大事だとよく言われる。しかし、何でもかんでも仕組み化すればうまくいくというわけではない。仕組み化を成功させるポイントとは?
ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の本連載をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』(石倉秀明著)の発売を記念して、特別編をお届けする。(構成/ダイヤモンド・ライフ編集部)
「仕組み化」がうまくいかない
組織の問題点とは?
最近、「仕組み化」という言葉をよく耳にするようになりました。
マネジメントのキーワードとして注目され、多くの企業が取り組もうとしています。しかし、私は「安易な仕組み化」には注意が必要だと考えています。なぜなら、「仕組み化」はそれ自体が目的ではないからです。
私が考える仕組み化の本質は、「うまくいっていることや成果が出ていることを、再現性高く、誰でもできるように拡大・定着させること」にあります。つまり、仕組み化をする前に、まず「成果が出ている」とか「うまくいっている」という事実があることが、絶対条件なのです。
特にスタートアップ企業では、「仕組みにしないと!」という声をよく聞きます。しかし焦るあまり、まだ成果が出ていない段階で仕組みを作ろうとするケースも少なくありません。営業チームが顧客を獲得できていないのに、そのプロセスを仕組み化しても、ダメなものが量産されるだけです。これは全く意味がありません。
まずは、実際に成果を出している人やチームのやり方を徹底的に分析し、それが本当に良いものなのか、仕組みにする価値があるのかを見極めることが何より重要なのです。
「仕組み化=マニュアル化」
ではない
また、「仕組み化」と聞いて「マニュアルを作る」ことだと思っている人も少なくありません。しかし、ただドキュメントに書いただけでは、それは「仕組み」とは言えません。それは単なる「ドキュメント化」です。
良い仕組みとは、メンバーが意識しなくても、その通りに動いていれば高い成果が出るとか、ルールを決めることで組織全体の収益が最大化するとか、さらには、それをやりたくなるようなインセンティブが設計されている状態のことです。
単に「みんなが見られるようにしました。さあ、どうぞ」では、誰も積極的に活用せず、結局形骸化してしまいます。
仕組み化を考える上で最も重要なのは、「何のために仕組み化するのか」という目的を明確にすることです。そして、その仕組みが「本当に良い成果」を生み出すものなのか、立ち止まって考える必要があるのです。
山田進太郎D&I財団 COO。2005年に株式会社リクルートHRマーケティング入社。その後、リブセンス、DeNA、起業などを経て2016年より株式会社キャスター取締役COOに就任(2021年より取締役CRO)。2023年10月の東証グロース市場上場に貢献し、2023年12月からは働き方について研究、調査を行うAlternative Work Labを設立し所長就任(現在も兼任)。FNN系列「Live Newsα」、AbemaTV「ABEMAヒルズ」レギュラーコメンテーター。著書に『これからのマネジャーは邪魔をしない。』(フォレスト出版)、『THE FORMAT 文章力ゼロでも書ける究極の「型」』(サンマーク出版)など。
ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の連載『「40代で戦力外」にならない!新・仕事の鉄則』の人気記事をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』が発売中。