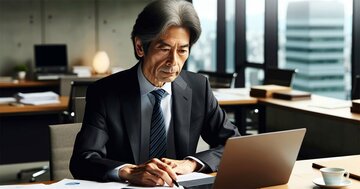働き方が多様化するなか、「定年=引退」というモデルは過去のものとなりつつある。「現役時代のようなフルタイム勤務ではなく、ストレスなく、少ない時間で続けられる仕事があれば……」と考える人も少なくないだろう。では、65歳以降に無理なく働ける仕事にはどんな選択肢があるのか。本記事では『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の著者・坂本貴志氏にインタビューを実施。仕事の実態を、就業データと当事者の声をもとに紐解いてもらった。(構成・聞き手/ダイヤモンド社書籍編集局、杉本透子)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
――定年後も働くかどうかを迷っている方にとって、「65歳以上の方が多く就いている仕事は何だろう?」というのは、とても気になるポイントではないでしょうか。
坂本貴志氏(以下、坂本):そうですね。65歳以上で働く人が多い職種というのは、それだけ年齢を重ねても続けやすい環境や条件が整っている場合が多いです。また、多様な働き方や役割が存在する職種である可能性も高いでしょう。
もちろん向き不向きはありますが、“多くの人が選び、続けている仕事”を知ることは、自分の選択肢を広げるきっかけになるかもしれません。
私が総務省の「就業構造基本調査」をもとに、65歳以上に絞って職種別の就業者数を算出したところ、トップ3は
1位 農業 100.5万人
2位 生産工程 95.8万人
3位 事務 89.4万人
という結果でした。
65歳以上で最も多い就業先は「農業」
――では、第1位の農業について教えてください。65歳以上の就業者が100万人以上いるのですね。
坂本:はい、私が調査した19職種のうち、農業は65歳以上の就業者数が100.5万人と最も多く、65歳以上の比率も最も高い職種です。
特徴的なのは年齢別の推移で、55~59歳が13.5万人、60~64歳が23.1万人に対し、65~69歳は35.7万人と、他の職種と異なり65歳以上で逆に人数が増えています。
これは、多くの職種で見られる「高齢になるほど就業者数が減る」という傾向とは異なっていて、農業ならではの特徴のひとつといえそうです。
――なぜ65~69歳の層で人数が増えるのでしょうか?
坂本:都市部での会社勤めを終えた後、実家の農業を継ぐ「定年帰農」や、新たに農業を始める「新規就農」といった動きも一定数あると考えられます。こうした背景が、65歳以上でも農業に従事する人の多さにつながっているのでしょう。
――農業は高齢になっても続けやすい仕事なのですね。一方で、担い手不足や高齢化が進んでいるというイメージもあります。
坂本:おっしゃる通りです。農業は75歳以上の就業者数が39.8万人と、他の職種に比べて非常に長く働き続ける方が多いのが特徴ですが、その背景には高齢化の進行もあるでしょう。
データを見ると、65歳以上の農業従事者の8.5割が自営業で、定年制がないため体力や気力が続く限り働ける環境にあります。一方で、農村地域の人口減少や高齢化、担い手不足などが進んでいることも事実です。
――高齢になっても収入や労働時間はあまり変わらないのでしょうか?
坂本:65歳以上の年収分布を見ると、年収100万円台が26.6%と最も多い一方で、年収500万円以上の方も9.6%おり、幅があります。
労働時間は職業の特性上、季節や作業内容によって変動しますが、平均的には週35~42時間程度働く方が最も多く、比較的長めの作業も少なくありません。
ただ、天候や作物の生育にあわせて自分で作業時間を調整できる点は、自営業ならではの柔軟さといえるでしょう。
――定年後に未経験で農業を始めるのはやはりハードルが高いでしょうか。
坂本:不可能ではありませんが、やはり事前の準備は欠かせないと思います。農地の確保や初期費用、収穫までに時間がかかることなど、考えておきたい点はいくつかあります。
JAや自治体、全国新規就農相談センターの就農相談窓口、研修や短期講座、各地で開かれる就農イベントなど、支援制度や知識を学べる場は各地にあります。こうした制度や機会を活用すれば、経験のない方でもまずは少しずつ必要な知識を身につけていけるのではないでしょうか。
身内から資源を受け継ぐ定年帰農の場合は、すでに農地や設備が整っていることも多く、費用や手続きの面で比較的有利に始められるケースが多いですね。
――実際には、どのような働き方をしている方がいらっしゃいますか?
坂本:たとえば、定年帰農で実家の農園を引き継いだ70代の方は、午前中に2時間、午後に2時間と、1日計4時間ほどの作業を続けています。農作物がよく育つと「いいものができた」と大きな喜びを感じるそうです。
一方で、大変なこととしては、農作物を詰めた18キロほどのコンテナを運搬する作業が挙げられていました。近年は後継者不足で廃園になる農家も増えており、そうした農家から新規就農者が設備や農地を引き継ぐ機会は広がっているのではないか、というのがその方の実感でした。
2位は経験と技術が生きる「生産工程」の仕事
――2位の生産工程は、具体的にどのような仕事を指すのでしょうか。
坂本:主に工場や製造現場での仕事を指します。
男女比は男性が65.4%と男性が多い職種です。就業者数を年齢別に見ると、70歳を超えると割合は減るものの、人数としては依然多く、65歳以降も現場で働き続ける方が少なくありません。
年収は200万円以上稼ぐ方が全体の約44%を占め、比較的安定した収入を得やすい仕事といえます。
――製造の仕事は体力が必要なイメージもありますが、なぜ高齢になっても長く続けられるのでしょうか。
坂本:生産工程といっても、部品の組み立てや検品など、比較的体力的な負担が少ない作業も多くあります。
週の労働時間はフルタイムに近い人が多く、65歳以上の就業形態を見ると、自営業が44.5%、非正規雇用が42.6%と大半を占め、正規雇用は12.9%と少数です。これは熟練の技術や正確な作業力を評価され、65歳以降も再雇用などで働き続ける方が一定数いらっしゃることが考えられます。
技術を身につければ長く続けやすく、「ものづくりが好き」という方には特に向いている仕事といえるでしょう。
3位は事務職 女性が多く、体力負担の少ない働き方が可能
――3位は事務職ですね。農業、生産工程と比べてどのような特徴がありますか?
坂本:事務職は女性の割合が多いのが特徴です。65歳以上の男女比は女性が60.5%で、特に70代以降は女性の割合が高くなります。
65歳以上の就業者数も多いですが、年齢別の推移を見ると50代から減少傾向で、農業のように65歳以降に人数が増えるわけではありません。
――収入面はどうでしょうか。
坂本:収入水準は比較的高めで、年収100万円台が28.4%と多い一方、500万円を超える人も1割近くいます。週35~42時間働く人が最も多く、フルタイムよりやや短めの勤務が多い傾向です。
就業形態は非正規が44.9%、自営業28.9%、正規26.3%と幅があります。書類やデータを扱う業務が中心なので、「体力的な負担を抑えて働きたい」という方には合いやすい職種といえます。会社の人事制度に左右されますが、再雇用制度などが整っている企業であれば、定年後も同じ仕事を続けることを検討してもよいでしょう。
――実際にはどのような働き方をしている人がいますか?
坂本:たとえば、一般企業を定年退職後、会計スキルを生かして公益法人に再就職した方は、契約社員としてフルタイム勤務を続けています。ほかにも、英語を使える環境を求めて外資系メーカーで週2~3日勤務をする方や、旅行会社を退職後に関連会社で事務サポートを続ける方もいます。いずれもこれまでの経験を活かしつつ、新しい職場や働き方に柔軟に適応されています。