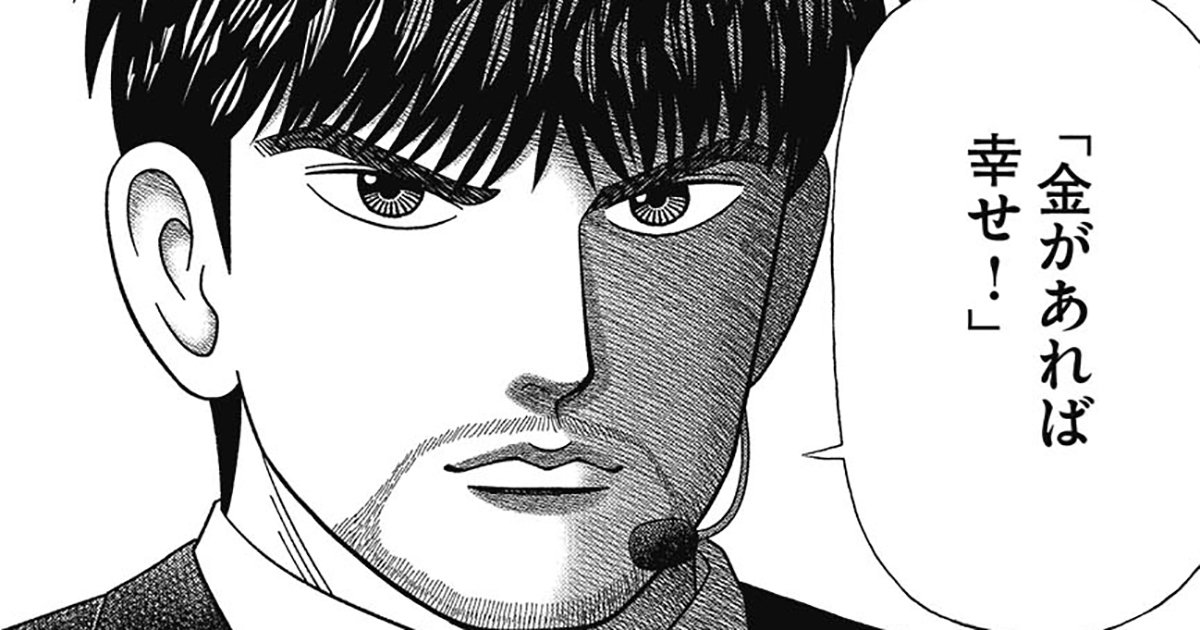 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第103回は、学校における金融教育について考える。
金融教育が「中途半端」になる理由
東大合格請負人・桜木建二は、龍山高校の教職員の前で学校改革を訴える。新たな教育の軸として「お金の勉強」を主張する桜木に、教員たちは拒否反応を示すのだった。
2022年度から、小中高の各段階で金融教育が義務化された。高校では公民と家庭科の2つの教科において、実際の制度と自分のライフステージとの関わり方について学ぶことになる。だが、高校での授業を思い出すと、自分を含めてそこまで熱心に取り組んでいたようには思えない。
なぜだろうか。
まず、受験に関わらないことだ。日本の高校教育は良くも悪くも大学受験を大きなゴールとして設計されている。そのため、公民や家庭科といった受験科目としてメジャーではないものは、先生からも生徒からも自然と後回しにされてしまう。
次に、学ぶ過程そのものが「面白い」と感じにくい点がある。体育のように身体を動かして楽しめるわけでもなく、音楽や美術のように創造性を刺激されるわけでもない。将来の役に立つと頭ではわかっていても、「今この瞬間の興味」と結びつかないため、抽象的な制度理解のまま終わってしまうのだ。
結果として、学校での金融教育は「中途半端な知識の確認」に留まりやすい。社会保障制度や税金の仕組みを覚えたとしても、それが自分の将来の資産形成やリスク管理にどう関わるのか、具体的なイメージを持てない。定期テストのための一夜漬けで終わってしまう人も多いだろう。
だが、実際には中高生のうちから主体的に学んでいる人はいる。NISAで積み立て投資をはじめている友人は多いし、少数ではあるものの株式投資やFXで数百〜数千万円を稼いでいる友人もいる。ただ、これらは高校での学びの成果というより、自主学習の成果や家族の勧めといった側面が大きい。
「学びたくなるお金の勉強」の作り方
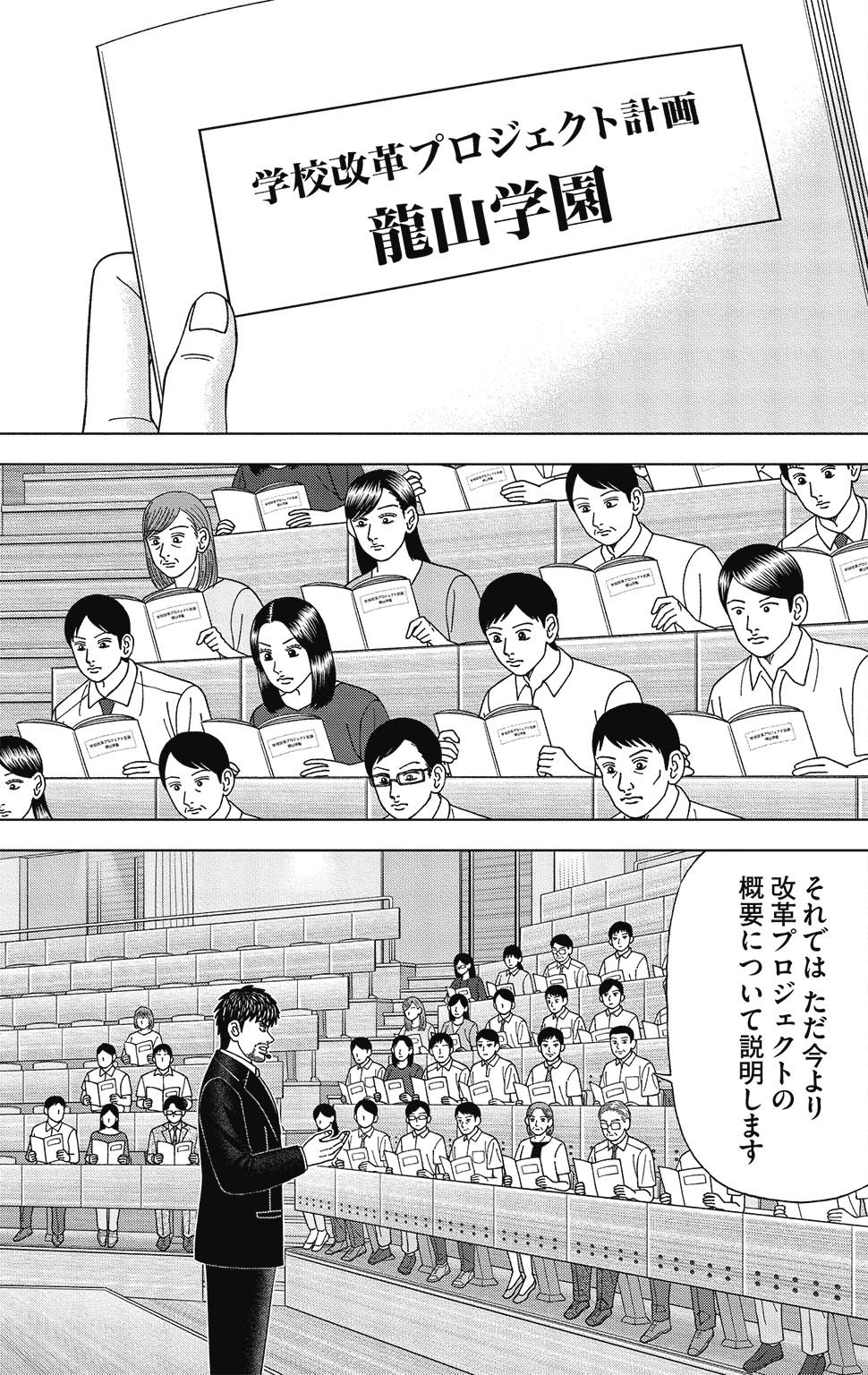 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
どうすれば「お金の勉強」を生徒が自ら学びたくなるものにできるのだろうか。
1つの方向性は、他教科との連結だ。
たとえば、経済学や数学、さらにはプログラミング教育と組み合わせるのもいいだろう。金融商品や市場の仕組みを本質的に理解するには、複利計算や統計、微積分、線形代数などの数学的思考が不可欠だ。実際にシミュレーションをプログラムで組めば、数字の背後にある「経済の動き」を体感できる。
こうした統合的な学びは、単なる知識ではなく、現実世界を分析する力として定着する。あえてアカデミックな分野と連携させることで、キャリア教育の一助にもなるだろう。とはいえ、この方向性は発展的すぎて、進学校などの一部の生徒にしか刺さらないかもしれない。
もう1つは、教育機関と金融機関の連携だ。学校内だけで完結させるのではなく、証券会社や銀行と協働し、模擬投資や資産運用を体験できる環境を整える。
株式だけでなく、債券、保険、年金といった多様な選択肢を含め、「リスクとリターンのバランスをどう取るか」を体感的に学ぶ。すでに民間には優れたシミュレーション教材やアプリもある。それらを教育現場に取り入れることで、より実践的な金融教育が可能になるだろう。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







