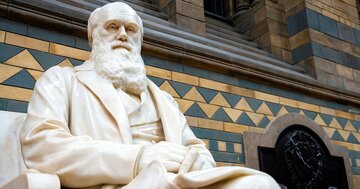ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
美しい自然と大きな代償
ダーウィンやその同時代の人々が見慣れていたイギリスの田園風景は、まさに穏やかで平穏だった。森では鳥たちがさえずり、川では魚たちがゆるやかに泳ぎ、草原ではキツネが跳ね回る。
この世は慈愛に満ち、生き物たちは平和に共生しながら、幸せに暮らしている。こういうロマンティックな自然観は、ダーウィンの時代のイギリスだけではなく、いろいろな時代にいろいろな場所でいろいろな人々によって、はぐくまれてきたことだろう。
しかし、実際には、このような美しい自然は、見えないところで大きな代償を払って、はじめて成り立つものだ。どの生物が作った子も、その大部分が命を落とすことによって、この美しい自然は維持されているのである。
共生や平和だけでは見落としてしまうもの
ところが、そういう自然の真実を見抜くことができずに、美しい自然の表面だけを見ていると、つい「共生の進化論」とか「平和な進化論」みたいな勘違いを主張してしまう。
そういう人は、いつの時代にも世界のどこにでもいるので、ダーウィンの生存闘争という考えは、あまり人気がないのだろう。
たしかに自然界には、競争だけでなく共生もある。残酷なこともあるけれど、平和なこともある。しかし、競争も共生も残酷も平和も、すべては生存闘争という基盤の上で生じたものである。
生存闘争という掌の上で、競争や共生や残酷や平和などの、すべての生物の活動が行われているのである。
屋久島の巨大なスギと生存闘争
日本の屋久島には、樹齢2000年を超えるスギが生えている。中には樹齢3000年に達するものもあると言われている。これらの巨大なスギを見ていると、その荘厳な姿に打たれ、誰しも人間のはかなさに思いを馳せるのではないだろうか。
それはそうなのだけれど、これらの荘厳なスギは、他の無数のスギの犠牲があって、はじめて数千年の時を超えて生きてこられたのである。
スギは大量の種子を作るけれど、屋久島はそんなに広くないので、すべての種子が生きていくことはできない。大部分の種子が犠牲になって、はじめて一本か二本のスギが生長できるのだ。
したがって、屋久島のスギの平均寿命は、あきらかに一年未満である。ほとんどの種子は、発芽しても一年以内に枯れてしまうのだ。
生存闘争に勝ち続けてきたスギだけが、2000年も3000年も生きることができるのである。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を編集、抜粋したものです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。